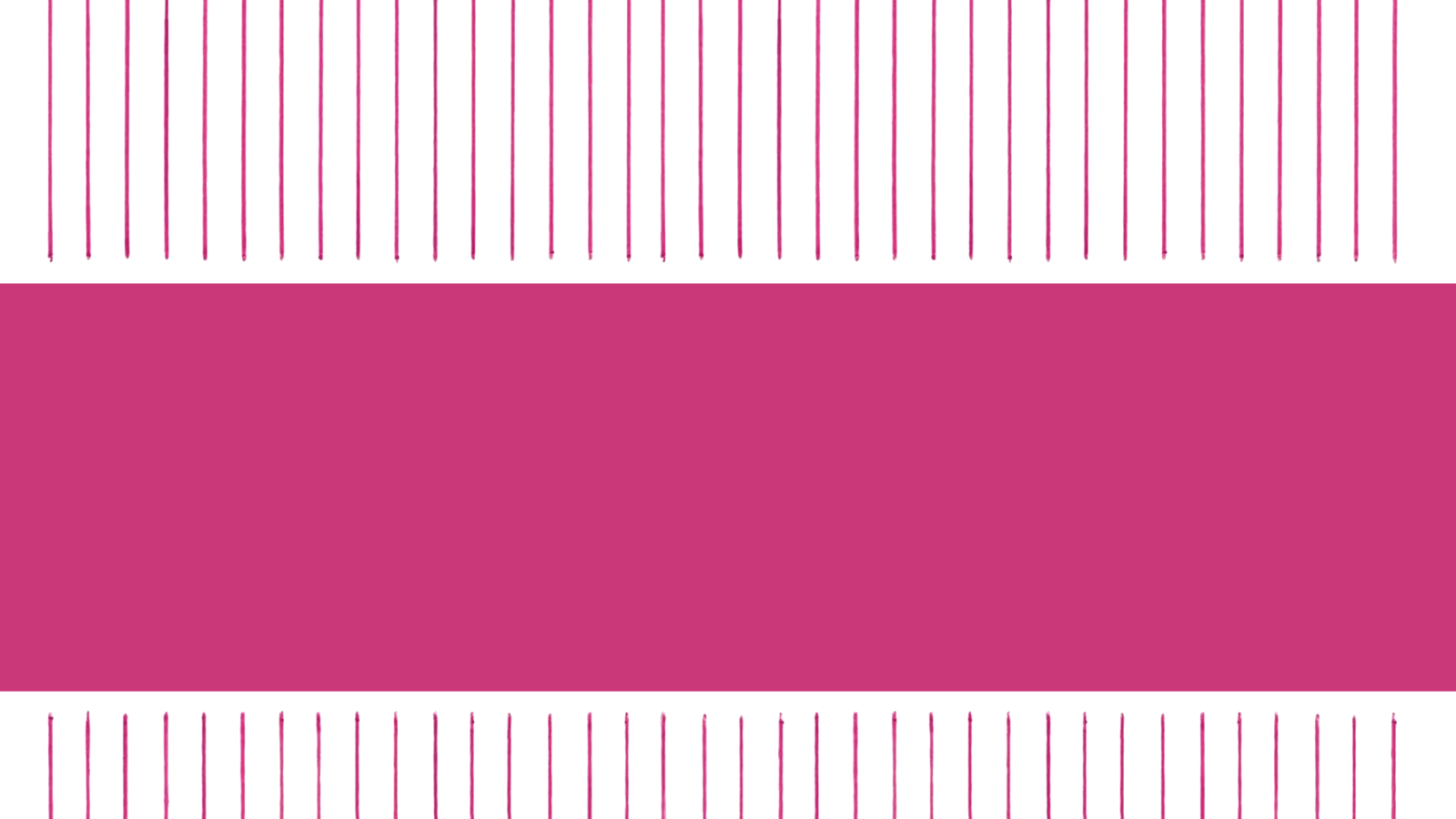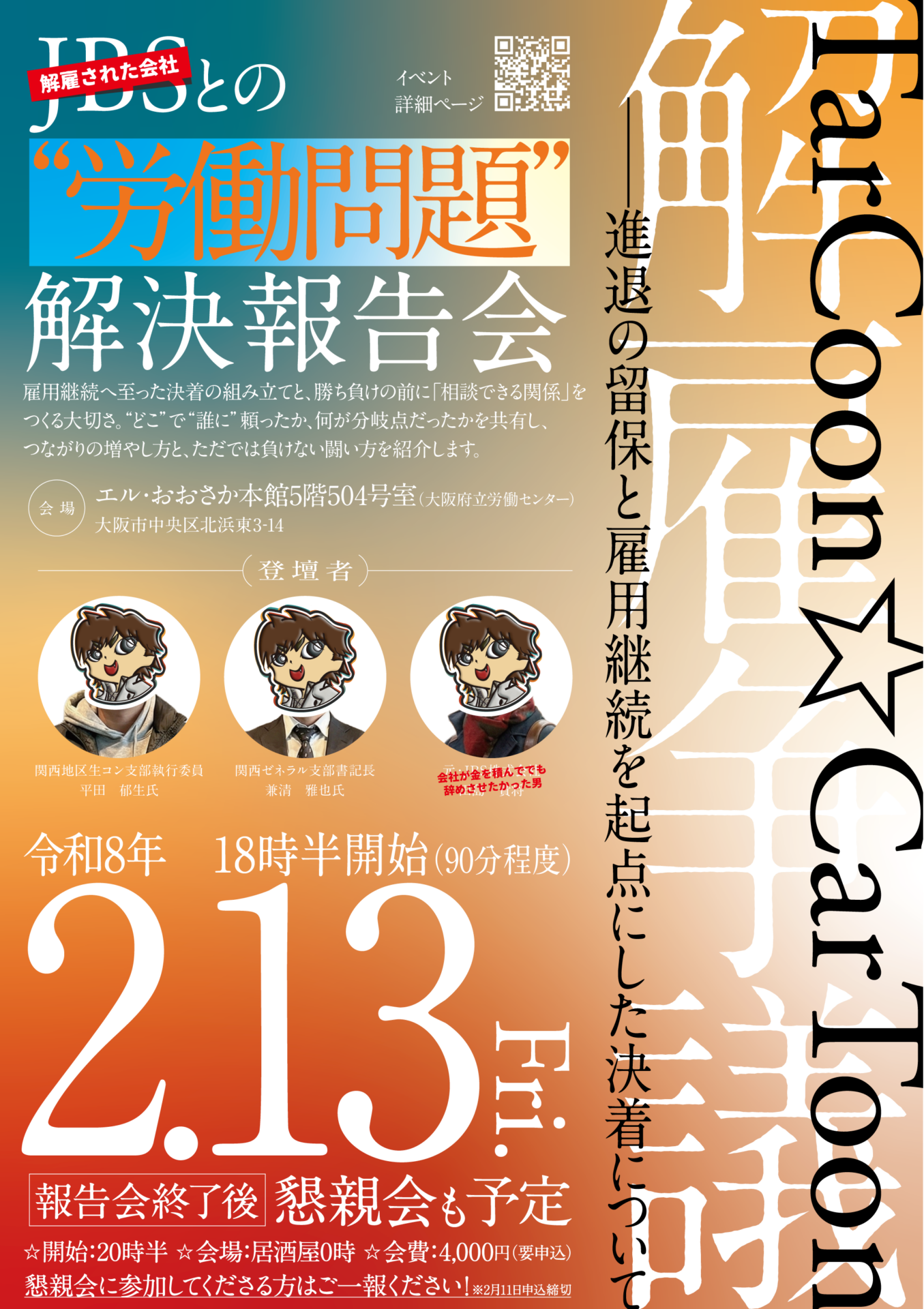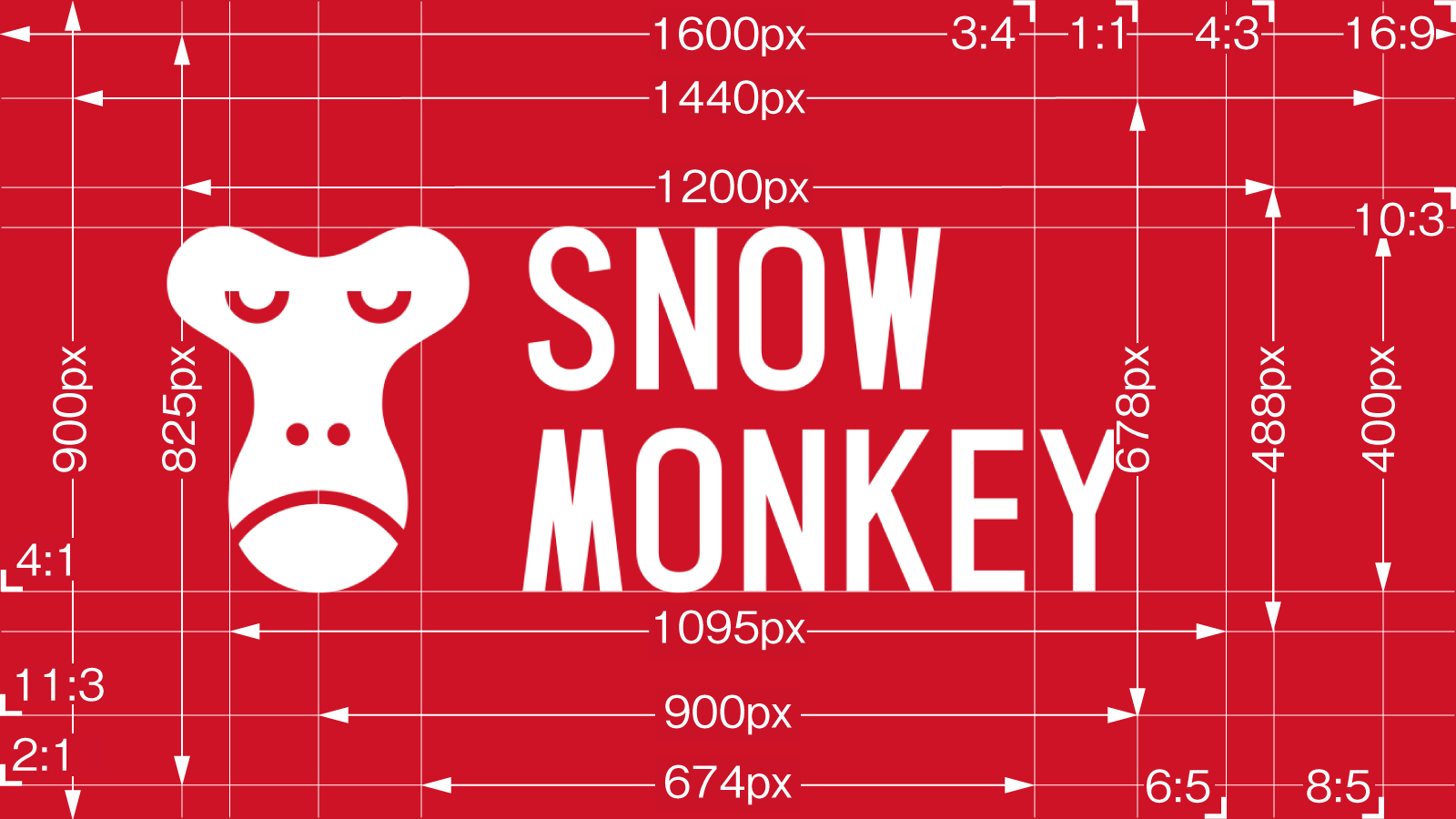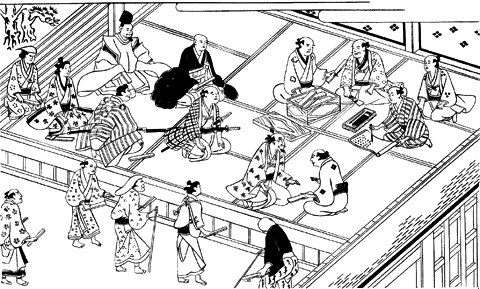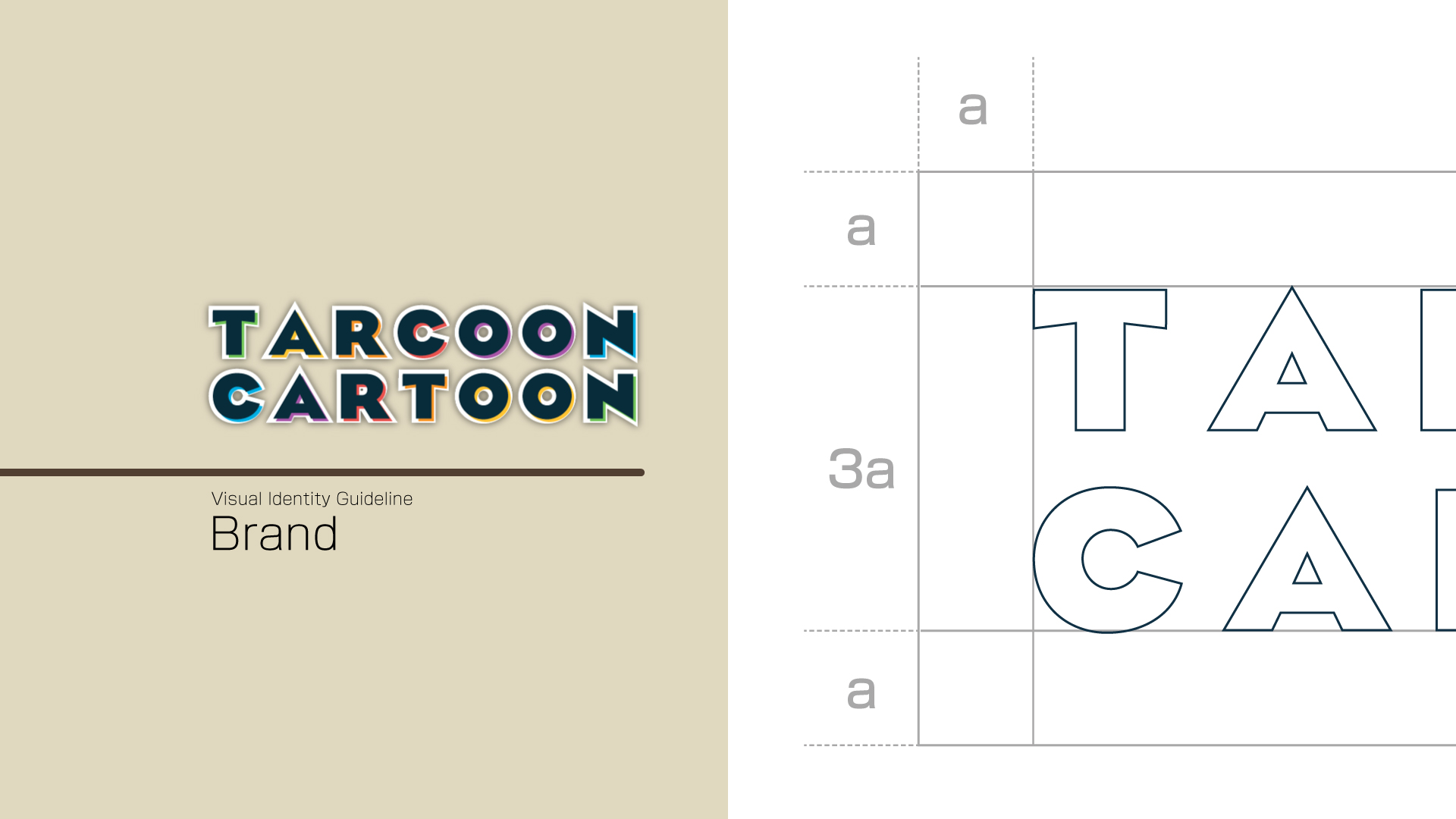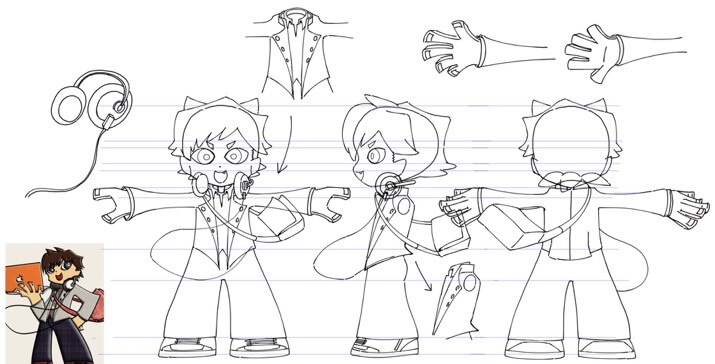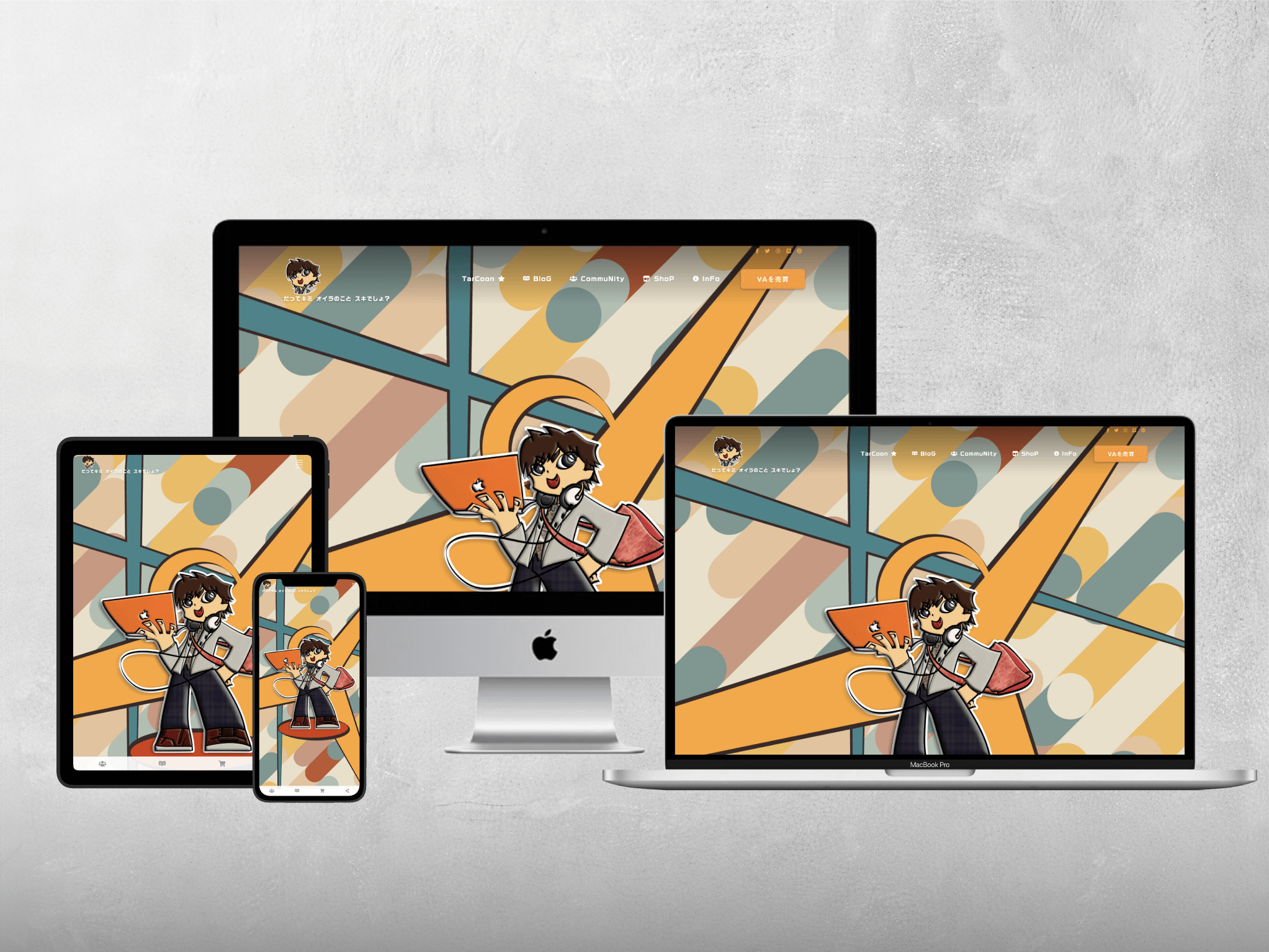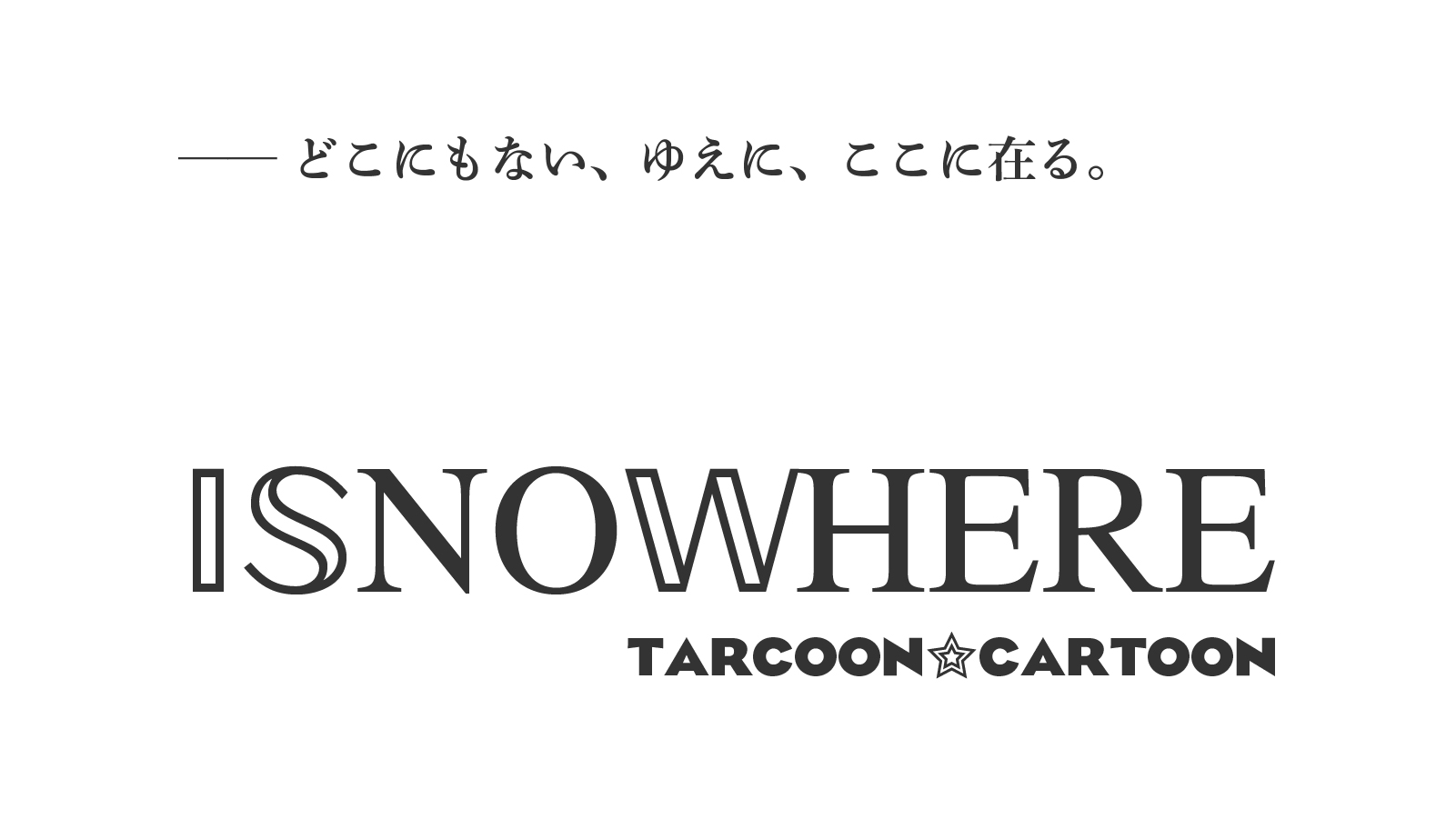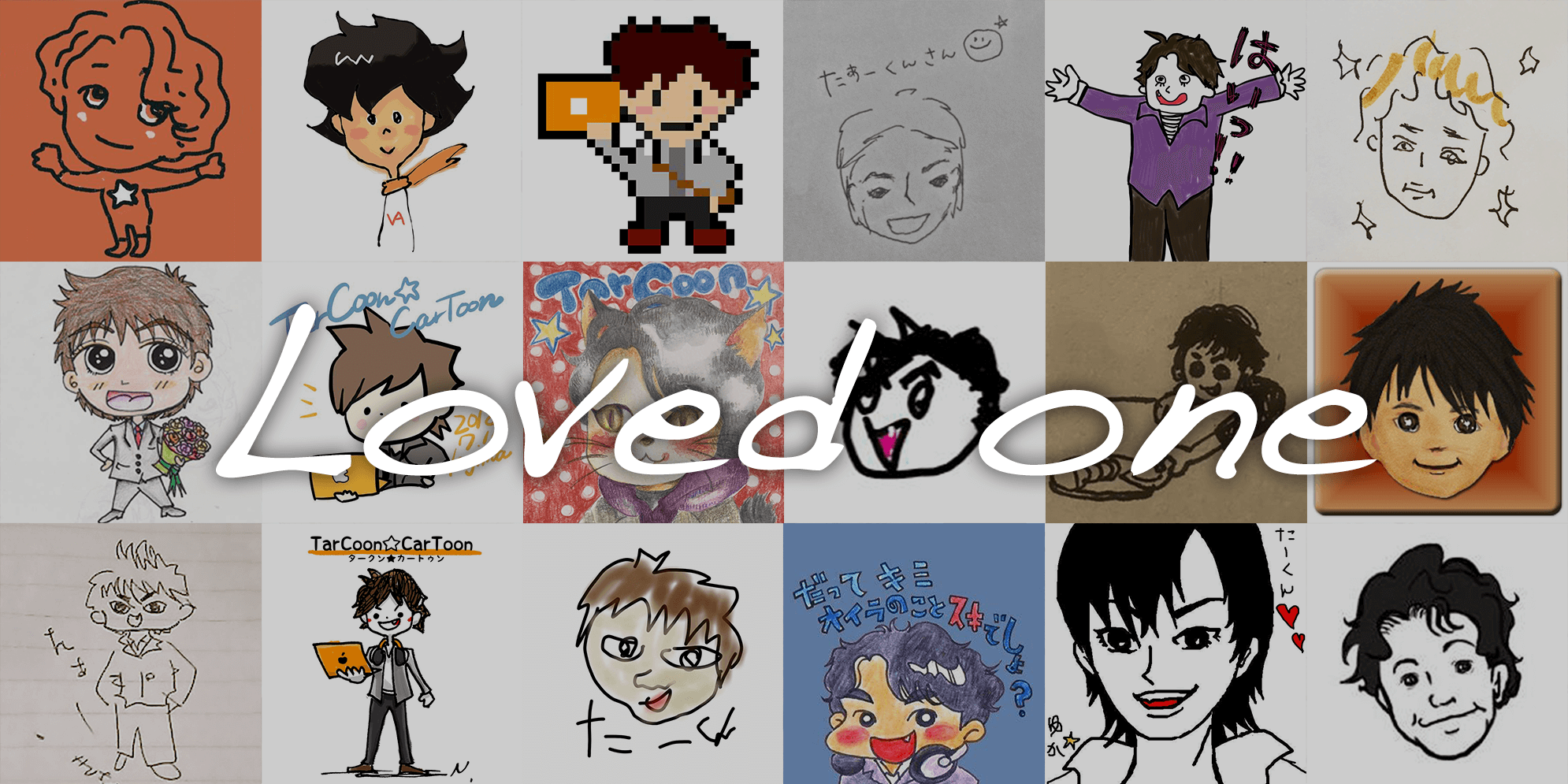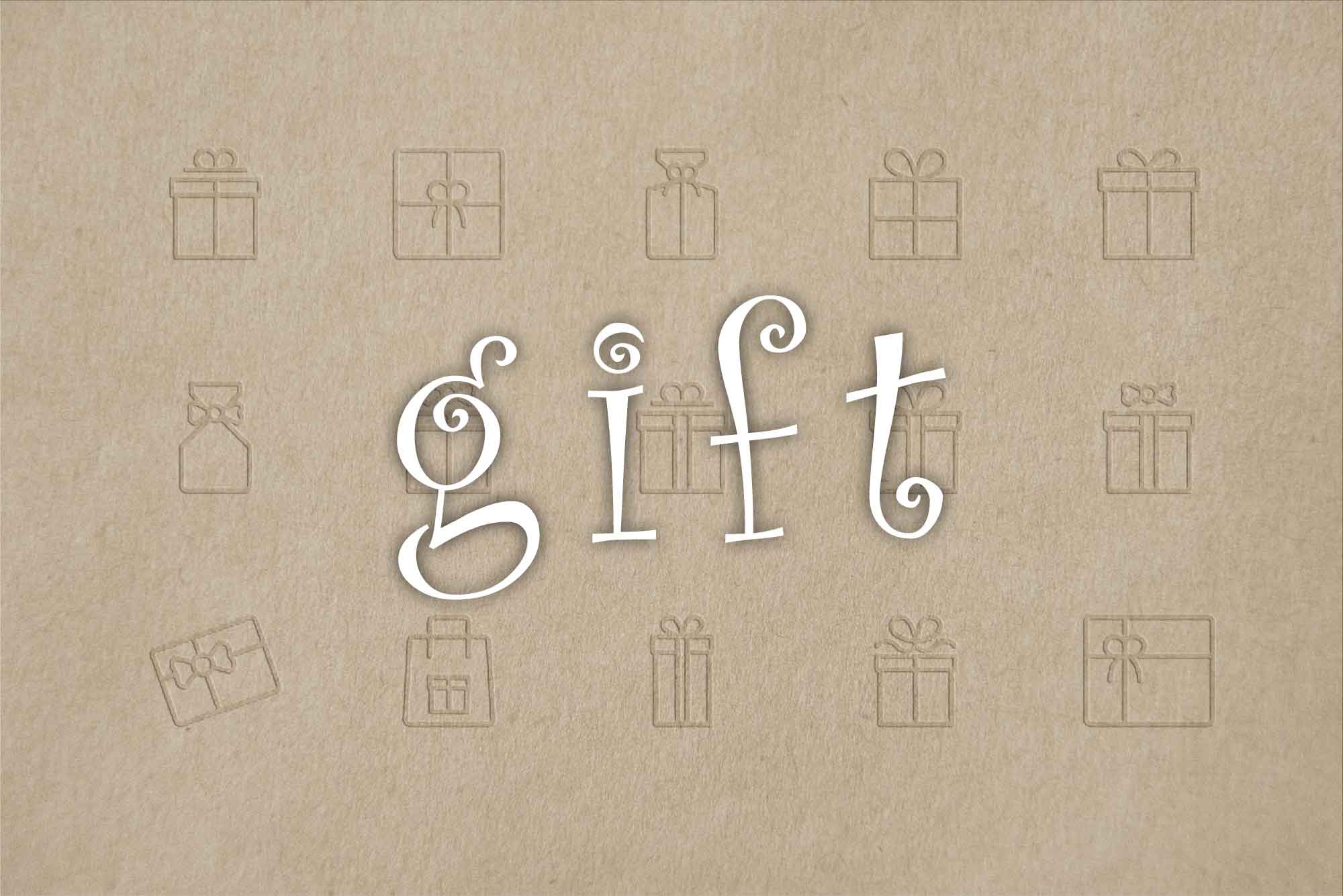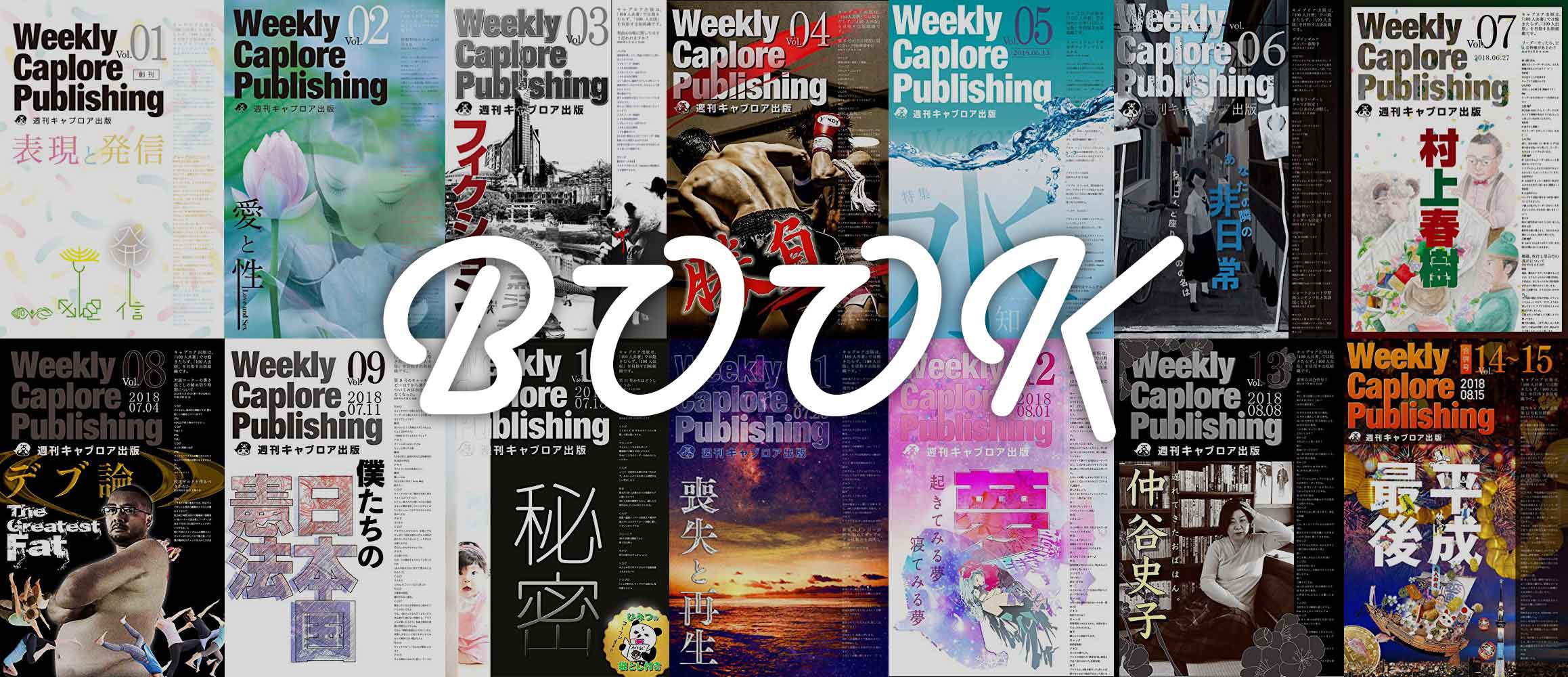「語ってほしい」と求められる空気のなかで、語らないことを選ぶのはなぜだろう?
共感、配慮、代表性──それらすべてが、善意の仮面をかぶって、語りを引き出そうとする。けれど、オイラは語らなかった。「演じきらないこと」「語りきらないこと」の中にも、誠実さがあると信じてきたからだと思う。
本記事では、電子文芸誌『ハツデン...!』9月号「Disability(障害/障がい者)」特集に寄せた寄稿文をもとに、TarCoon☆CarToonとして、「感動ポルノ化」「語りの引き出され」「共生の演技化」など、現代社会における“語ることの圧力”と“語らないことの倫理”について自分の体験をお話しします。
それは、「わかりあえなさ」のまま共にいることができるか?という問い。
「善き生とは何か?」という問いを軸に、語りと沈黙、理解とズレのあいだで揺れ続ける生の倫理を描き出す試みです。
“在り方の誠実さ”をめぐる倫理エッセイ──TarCoon☆CarToonが綴る、もうひとつの「障害を引き受ける」という姿。
寄稿した雑誌「ハツデン…!」9月号発売してました!
— TarCoon☆CarToon (@TKMS_all4A) August 30, 2025
みなさん買ってください!https://t.co/tmsFriCHOL pic.twitter.com/bkPhxZZPuG
*本記事は、雑誌『ハツデン...!』9月号「Disability(障害/障がい者)」に「語りえなさの隣に立つ──障害を引き受けながら、演じきらないという構え」というタイトルで寄稿しています。ぜひ本誌でもご覧ください。
*本記事は、雑誌掲載版に加筆・再構成した増補版です。
語ることとは何か──他者を通しての思索
ある人物と出会って以来、オイラは「語る」という行為の持つ倫理的な重みについて、あらためて考えるようになった。その人物は生まれつき身体に障害を抱えていたが、そのことを殊更に説明するでもなく、また隠すわけでもなかった。ただ、障害という事柄を「語る」ことに対して、独特の慎重さと距離感をもっていたように思われた。
オイラが初めてその人と言葉を交わしたとき、たとえば「障害は辛くなかったのか」といった問いを投げかけることには、何か後ろめたさのようなものがつきまとった。けれど、その人物はむしろオイラよりもはるかにフラットな態度で、自身の身体の状態を口にした。そこにあったのは、障害を「語ること」によって他者の共感を得ようとする姿勢でもなければ、語ることそれ自体を拒絶するような自己防衛的な姿勢でもなかった。
それはむしろ、語るべき時にだけ語る、というような、ごく限定的な語りへの許可と、その範囲を逸脱させないことへの意志のように見えた。いや、むしろ「語らないでいる」ということを一つの選択として引き受けている──そう言った方が適切かもしれない。
現代において、「語らないこと」はしばしば「隠している」「無関心である」「不誠実である」といった否定的なニュアンスを伴って理解されることがある。しかしその人物は、語らないことが必ずしも自己防衛や他者からの断絶ではなく、むしろ語ることそれ自体への慎重な倫理的態度であることを体現していた。
障害という事柄を語ることには、一般的に幾つかの社会的な機能が紐づけられている。たとえば、周囲の理解を得るため、偏見を和らげるため、制度的支援を受けるため、あるいは共感を喚起するためといった語りの目的がある。それらはいずれも必要不可欠なものとして、当事者に“当然”のように求められる。しかし、そうした語りが過剰に制度化され、機能化されるとき、語り手の主体性はむしろ失われてしまうのではないか。
実際、障害を語ることが「語らなければ理解されない」という前提に基づいて要請されるとき、そこにはすでに語りの自由は存在していない。「語ること」は一見、自発的な選択のように見えるが、その背景には沈黙が許されないという構造的な圧力がある。社会の側が、障害者に対して「語ってもらわなければわからない」と主張することで、語る/語らせるという非対称な関係が生まれてしまうのである。
このような状況において、障害を語らないという姿勢は、沈黙による抵抗であると同時に、語りそのものを選び直す行為でもある。沈黙とは、語ることの放棄ではなく、むしろ語りの輪郭を引き直すための技術なのだ。
オイラにとって、冒頭に述べた人物の「演じきらない」という構えは、まさにこの沈黙の倫理を体現しているように感じられた。彼/彼女は、障害を「演じる」こと──つまり、定型的な語りや想定されたナラティブに自らを適合させること──を拒否していた。むしろその人物は、「語る/語らない」という選択肢のあいだでバランスをとりながら、自分の言葉を慎重に編み上げていたのである。
これは、「語らないことでしか語れないものがある」という逆説の実践である。語ることは、しばしば相手の理解という“成果”を得るための手段に回収される。だが、語らないことには成果がない。ただ、そこに在るだけである。しかし、その「在るだけ」の存在が、語ることを越えて他者を揺さぶる瞬間があるのだ。
オイラはそのとき、言葉の限界に触れていた。語られた内容以上に、語られなかった余白がオイラの中に残り続けた。そしてその余白においてこそ、「障害とは何か」「語るとは何か」という問いが、はじめてオイラ自身の問題として浮かび上がってきたのである。
このように考えると、「障害を語る」という行為は、それ自体がすでに社会的役割を担わされており、ある種のパフォーマティブな空間において、制度と情動のあいだで配置されていることがわかる。であるならば、「語らないでいる」という構えは、その配置からの逸脱を意味する。そこには、語られるべきことを語らずに生きることの困難と、同時にそれを引き受ける強さが含まれている。
そして何よりも、その姿勢にオイラは一つの美しさを見た。語られることのないものに目を凝らし、語られざることの中に倫理のありかを見出す。その生き方は、決して声高ではないが、確かにひとつの抵抗であり、構えであり、そして問いであった。
語らないということ。それは、何も言わないということではない。むしろ、何を語るべきか、どのように語るか、あるいは語ることそのものが必要なのかを問う姿勢のことである。
その問いを生きること。その沈黙を保つこと。
そこにこそ、「演じきらない」という態度の本質があるのではないかと、オイラは今も考え続けている。
語らされる構造と沈黙の倫理
「障害を表明している人たちは、弱者アピールをしているのではない。説明を求められるから言わなければならないのだ。」
この言葉にオイラは、深い不自由と、静かな抵抗の気配を感じ取る。障害をめぐる語りは、しばしば「自発的な自己表現」として解釈される。理解を求め、偏見を取り除き、支援制度へアクセスするために、語ることは必要なのだと。だが、その語りの背景にあるものが「説明しなければならない」という社会的な強制であるならば、それは本当に「自由」な語りと言えるのだろうか。
現代の公共空間において、「語ること」は美徳とされる。沈黙は不誠実と見なされ、語らなければならない空気が、当事者に沈黙の選択肢を許さない。とりわけ、障害や病気、マイノリティ性といったテーマにおいては、「きちんと説明すること」が、配慮や共感、承認を得るための必須条件となる。だが、その構造において本当に問われるべきは、なぜ“語らせなければ配慮できないのか”という、聞き手の倫理の問題である。
障害当事者が語らないとき、周囲は「なぜ言ってくれなかったのか」と責めることがある。だが、そもそもその責めは、理解の主体を相手に委ね、自らは待つだけの姿勢にとどまってはいないか。理解したいのなら、なぜ語られない沈黙にこそ耳を澄まそうとしないのか。
「語ってくれないとわからない」という言葉は、聞き手の受動性の表明にすぎない。その態度が結果的に、当事者に語ることを強いる。「あなたのために知っておきたいから教えてほしい」という姿勢は、善意のように見えて、その実「語らなければならない」という空気を生み出すことで、語り手の選択を奪ってしまうこともある。
つまり、障害を「語らせる」構造そのものが、すでに制度的なバイアスを含んでいる。そしてその語りが「わかりやすい物語」であるほど、社会は安心する。苦労してきたこと、困難を乗り越えてきたこと、助けを求めていること──そのように整えられた語りは、聞き手が共感しやすい形をとっている。しかし、それは語り手の複雑さや沈黙の重みを、往々にして排除してしまう。
オイラがここで考えたいのは、「語る自由」と「語らない権利」との区別である。語ることができる自由は重要だ。だが、それと同じくらい重要なのは、「語らなくてもよい」という権利が社会のなかでどれだけ尊重されているかである。
障害者は、語ることで自身の立場を正当化しなければならない立場に置かれてきた。自らの障害の程度、苦労の歴史、必要な配慮の内容、周囲との関係──それらを語り尽くすことで、ようやく配慮や支援が正当化される。だがこの構造こそが、障害者に「常に説明責任を負わせる」という、持続的な負荷を課している。
逆に、語らないことを選んだ当事者は、「無責任」「不親切」「自意識過剰」といったレッテルを貼られやすい。語らなければ理解されない、そして理解されなければ支援されないという二重の構造が、語らない選択肢を事実上封じてしまう。
これは、沈黙を尊重しない社会の構造的な問題である。沈黙とは、語らないことで生まれる「無言の自己主張」であり、語りとは異なる方法で社会に対して関わろうとする試みである。しかし、制度や他者の想像力がその沈黙を読み取ろうとしないとき、それは単なる“拒絶”や“閉じこもり”と見なされてしまう。
だが本来、沈黙は語りと同様に、社会的な言語行為である。語らないという姿勢は、語ることを強制される構造への抗議であり、また、自らの存在を制度化された物語から切り離そうとする意志の表れでもある。そこには、語られざる経験、分類不能な感情、名づけられない痛みが宿っている。
そして、そうした沈黙に対して耳を澄まし、想像力をもって関わることが、共生の出発点であるべきだ。語られる内容だけでなく、語られなかった言葉、言いよどまれた沈黙、逸らされた視線、そのすべてを「関係のなかの言葉」として受け止める感性。それがなければ、共生は「語ってもらえた人」だけに限られてしまう。
オイラは、「語らないままでいること」にこそ、より深い倫理的選択があると考える。それは自らを語られた物語に還元せず、制度の文脈に包摂されず、ズレたまま関わりつづけるための実践である。語ることによって“理解されてしまう”のではなく、語られなさのまま他者と出会うこと。その不確かさに耐えられる社会こそが、成熟した公共性を持つ社会ではないか。
沈黙は、回避ではない。退却でもない。それは、語らなければならないという強迫のなかで、なお「語らないことを選ぶ」ことでしか立ち上がらない倫理の場である。
語ることと語らないことの間に、優劣はない。あるのは、その選択がいかに尊重されるか、という問いである。語る自由だけでなく、語らない権利を守ること。それが、障害者の尊厳を担保する最も根本的な条件であり、ひいてはすべての人にとっての自由の基礎である。
だからオイラは、語られる内容よりも、語られない決断をこそ信頼したい。語らないままであることに誠実であろうとする、その姿勢にこそ、人が語る以前の「存在の声」があると信じている。
障害の特権化に抗して──関係の倫理へ
「障害あるくせに生きているのを特権にするな」
この発言を初めて聞いたとき、オイラは一瞬、反射的な違和感と共に、言葉の背後にある倫理的な緊張に惹きつけられた。あまりに率直で、あまりに攻撃的で、けれどその言葉は、単なる排除や嘲笑の言葉ではなかった。それはむしろ、「語ること」や「語らせること」の圏域から身を引き、あらためて「関係」の場そのものを問い直す呼びかけとして響いていた。
障害を語ることが、しばしば当事者の「正当性」や「理解の獲得」の手段として機能していることは、すでに前項で述べた。だが、その語りが社会的文脈において「特権」として作用し始めたとき、つまり、「語る資格」によって「他者の発言を封じる力」を持ち始めるとき、そこにはある種の非対称な倫理が生まれてしまう。
弱さ、痛み、被害性といった言説が、社会的に正当なものとして承認される構造のなかでは、相手の言葉を受け止める余地が狭められる。たとえば、「オイラは傷ついているのだから、あなたの発言は控えてほしい」「あなたの言葉はオイラの生を脅かす」といった主張が、「議論の中止」を倫理的に正当化する力を持ちうる。もちろん、そのような声が必要な場面は確かにある。しかし、それが常態化したとき、語る側は不可侵の領域となり、聞く側は「触れてはならないもの」として自らを抑制せざるをえなくなる。
その人物が語った「特権にするな」という言葉は、こうした非対称性を告発するものだった。語ることによって自らを「批判不能な存在」に仕立てるのではなく、語りを通してもなお「他者と関係し続けること」の困難を引き受けるべきだという姿勢である。つまり、語りが「免責の装置」としてではなく、関係を生み出すための回路として機能するべきだ、という立場である。
この視点に立つとき、障害は「配慮されるべき属性」ではあるが、それを根拠に「絶対的な正しさ」を主張するものではなくなる。障害は、それ自体で他者の発言を無効化する理由にはならないし、また、当事者性は自動的に倫理性を保証するものではない。むしろ、その人物は「障害があるからこそ謙虚でいなければならない」と語っていた。これは、障害を「特別な地位」ではなく、「常に他者と折り合いをつける必要のある条件」として引き受ける態度である。
ここで重要なのは、「関係の倫理」という視点である。倫理とは、個人の内面の問題ではなく、関係のなかで生じる力学である。障害を語ることが、他者に対する「義務の要求」としてのみ機能するならば、それは支援や共感を通しても、関係そのものを開くことにはならない。他者はそこにおいて、常に「支援者」「共感者」として位置づけられ、それ以上の関係性──たとえば、対話者、批評者、同伴者──としての地平を失ってしまう。
その人物は、障害を語りながらも、他者との関係を「一方向的な支援の構造」へと閉じなかった。むしろ、しばしば意図的にズレた態度をとり、相手に思考の負荷を与えようとさえしていた。それは、障害を「わかりやすく伝える」ための語りではなく、「そのわからなさも含めて関わってほしい」という要求であったように思う。
関係は、均衡によってではなく、緊張によって成立する。わかりやすさや安心感が先にあるのではなく、違和感やズレ、不快さを含みながら、それでも断絶せずに共にいること──そのような関係の形式が、障害という出来事のなかではとりわけ重要になる。
現代社会において、「わかりやすい障害者像」が氾濫している。努力している、明るくふるまっている、自分の特性を説明できる、制度を正しく利用している──そうした人物像に当てはまらない者は、「協力的でない」「社会性に欠ける」といった否定的評価を受けやすい。そしてその評価は、障害者に「理解されるための振る舞い方」を内面化させる圧力となる。
だが、そうした自己表現が、他者との関係を「管理されたもの」に変えてしまうならば、それは果たして“生きやすさ”なのだろうか。
その人物は、決して“生きやすさ”を選ばなかった。むしろ、自らの「ズレ」や「誤解されやすさ」を引き受けたうえで、それでも関係の場にとどまりつづけた。その構えは、安易な理解や配慮よりもはるかに困難で、しかし深い信頼に満ちたものであった。
語りとは、他者と結ばれるための入口であると同時に、他者を排除する境界線にもなりうる。そのことを強く意識しながら、それでも語ることをやめないという姿勢。その語りが免責ではなく、関係の中でこそ成立するという信念。そこにこそ、障害という出来事をめぐる「倫理の臨界」があるのだと、オイラは思う。
そして、この構えは決して障害者に限られるものではない。あらゆる語り手が、自らの立場性や経験を盾にすることなく、関係の中で問い続ける構えを持てるかどうか──それが、言葉の倫理を決定づける。
「特権」として語るのではなく、「応答可能性」として語る。語ることで他者を巻き込み、語ることで他者に触れられることを許容する。
それこそが、オイラ──TarCoon☆CarToon──が示している、「ズレたまま関わる」という、生き方のかたちなのではないか。
贖罪としての生──傷つけることと、なお生きること
「自分の障害で父と母の人生を狂わせてしまった」
この言葉を耳にしたとき、オイラは深い静けさに包まれるような感覚を覚えた。それは、自責というにはあまりにも穏やかで、断罪というにはあまりにも柔らかかった。むしろ、それは一種の「祈り」のように響いていた。
この言葉は、決して演技的な悲壮感に支えられたものではない。むしろ、その人物が日々の生活のなかで、静かに、繰り返し、自己の存在がもたらした影響を引き受けてきた、その時間の厚みに裏打ちされた言葉である。そしてそのように、自らの「存在の重み」を絶えず意識することによって生きること──それを、オイラは「贖罪としての生」と呼びたい。
ここで言う「贖罪」は、宗教的な意味での罪の贖いとは異なる。むしろそれは、「意図せずして誰かを傷つけてしまった者が、それでも他者との関係の中に留まり続けるための倫理的な構え」である。
オイラたちは通常、「加害」とは意図的な行為であると考える。だが現実には、人はただそこに「在る」ことによっても、他者に深い傷を残してしまうことがある。障害を持って生まれた子どもが、そのことで親の人生を変えてしまう。生まれた環境や身体や条件が、誰かの期待や未来を奪ってしまう。そこには、誰のせいでもない、しかし消しがたい事実がある。
こうした「非意図的な加害」に対して、人はどのように応答できるのだろうか。多くの場合、それは沈黙か、あるいは「自分にはどうしようもなかった」という自己正当化へと向かう。責任の回避か、無力の受容か。けれど、その人物は違っていた。
彼/彼女は、自らの障害が他者にもたらした影響を否定せず、消去せず、また過剰に背負い込むこともせず、ただ粛々とそれを受け止めていた。そしてその上で、なおも他者の幸福を願い続けるという、ある種の信仰のような姿勢をもって日々を生きていた。
この「他者の幸福を願う」という行為は、一見すると美談のように見えるかもしれない。だが、その実践は決して容易ではない。なぜなら、それは「他者に理解されたい」「自分を赦してほしい」という欲望を抑制しなければ成り立たないからである。
贖罪として生きるということは、自らの傷や負い目を“語って赦される”ことではない。それはむしろ、「赦されなくてもよい」という立場に立ちながらも、なお他者との関係に留まり、祝福のまなざしを向け続けるという構えである。その構えは、関係における“贖罪の演技”ではなく、関係そのものを支える“倫理の基盤”である。
ここで想起されるのは、哲学者エマニュエル・レヴィナスが言う「責任」の概念である。レヴィナスにおいて、責任とは何かの報いを受けることでも、法的な義務を果たすことでもなく、「他者の顔」に直面することによって呼び起こされる、終わりなき応答可能性のことである。
TarCoon☆CarToonという存在が示しているのは、まさにそのような「終わりなき責任」のかたちである。
他者に何かをしてしまった。その“してしまった”という事実の前で、人は語ることも、消すこともできない。ならば、残されたのは「それでも他者のために祈ること」であり、「関係に留まり続けること」なのだ。
その人物が、ときに諧謔的に、ときに突き放すように他者と関わるのは、自己防衛や達観の表現ではない。むしろそれは、関係のなかに居続けるための、苦肉の技法である。祝福すること、応援すること、冗談を言うこと、距離を取ること──それらすべてが、「関係に裂け目を作りすぎず、かといって馴れ合いすぎない」ための、微細な調整として行われている。
障害を持って生きることは、それ自体が多くの制度的困難と社会的偏見に晒されることである。だが、TarCoon☆CarToonはその生の苦しさを、「正当化」や「免責」の根拠にするのではなく、「誰かに届かないままでも、誰かのために生きる」という方向へと昇華している。
それは、「語られる苦しみ」ではなく、「語られないまま捧げられる配慮」である。
その倫理は、静かであるがゆえに見過ごされやすく、自己犠牲的であるがゆえに誤解されやすい。だが、その姿勢こそが、「障害者」という言葉の持つ固定的なイメージを打ち壊し、まったく別の「存在の倫理」を照らし出している。
生まれてきたことそのものが、誰かにとって負担であるかもしれない──その事実を、演技ではなく、実存の厚みとして引き受けながら、それでも「今、自分のまわりにいる人たちの幸せを願う」こと。それは贖罪というより、祈りに近い。それも、決して届く保証のない祈りである。
だが、届くかどうかではなく、祈るという姿勢そのものに意味がある。
それが、贖罪としての生という構えなのだ。
「演じきらない」ことの美学──物語からの逸脱
この世界は「語りやすい物語」を欲望している。
それは、制度の言葉でも、支援のための説明でもない。
もっと曖昧で、もっと感情的で、しかし確実にオイラたちの意識に根を張っている一つの形式──つまり、「感動のナラティブ」と呼ばれる類型である。
障害者が苦しみを乗り越え、困難に立ち向かい、社会に認められていくというストーリーは、オイラたちの想像力の中で常に歓迎されている。苦しみを語ること、再起すること、周囲の支援によって「回復」し「成長」すること──そのように美しく整えられた物語は、読む者や聞く者にカタルシスと安心を与える。
だが、それは果たして「語り手の自由な語り」と言えるのだろうか。
その人物──TarCoon☆CarToonは、そうした物語への組み込みを一貫して拒んでいる。障害者として期待される言葉、苦悩の履歴書、回復のエピソード、社会的意義を証明するような成果──そのいずれにも積極的に関与しない。むしろ、自らのズレをズレのまま提示し、誤解されるままに放置し、理解されることへの欲望すら引き受けないという態度で、語りの外縁をさまよい続けている。
この「演じきらなさ」は、倫理というより、むしろ美学の問題として捉えるべきである。
それは、道徳的な正しさや制度的な正当性とは異なる軸線であり、「どのようにあるか」「いかなる姿勢を選びとるか」といった、存在の様式にかかわる問題である。善悪の問題でも、有用性の問題でもない。ましてや、「障害者として社会に何ができるか」といった功利的な問いからも遠く離れている。
TarCoon☆CarToonの「ズレたまま」の構えは、他者にとってはしばしば“わかりにくさ”や“とっつきにくさ”として現れる。彼/彼女は明確な立場を提示しないし、被害者としての振る舞いにも与しない。にもかかわらず、常に「関係の中にとどまり続けている」。そのズレを、ユーモアと皮肉、暴言と沈黙のあいだで絶妙に保ち続けるその姿は、一種の「美的身振り」として理解されるべきものだ。
現代において、障害者の語りが制度や支援の文脈で流通していく中、語ることは徐々に「理解されること」と同義になっていった。けれど、「理解されること」には常に代償がある。それは、自らの複雑さや矛盾、揺らぎを切り捨て、「理解されやすい形」に自己を変形することである。
物語の中に回収されるとは、そういうことだ。
回復の物語、成長の物語、支援に感謝する物語──そうした枠組みに自らを組み込むことで、語り手は社会に居場所を得る。しかし、同時にそれは、語る側の自由を著しく制限していく。語ることは、社会との交渉であると同時に、社会への従属でもある。
TarCoon☆CarToonは、その従属から逃れようとする。
語らず、断言せず、矛盾のままに語り、ユーモアと沈黙のあいだで揺れ続ける。
この姿勢に対して、「不真面目」「不明確」「政治的でない」といった批判が向けられることもある。だが、その批判こそが、「語りやすさ」によって成立する社会的制度の側の美学の欠如を露呈しているのではないか。
理解されようとしないこと。
説明しようとしないこと。
役立とうとしないこと。
そのすべてを選び取るという「身振り」には、確かに“非効率”や“誤解”が伴う。だが、それでもなおそこにとどまり続けることでしか開かれない関係があり、問われないままでいられる沈黙がある。
この構えを「美しい」と感じられないのであれば、その感性こそがすでに制度化され、物語に毒されてしまっているのではないか。
美しさとは、整っていることではない。
むしろ、美しさとは、矛盾やズレを引き受けたまま、折れずに存在していることではないだろうか。
オイラたちは、無意識のうちに、障害者に「意味のある苦しみ」「語りのある人生」「成長する困難」という物語の型を求めてしまう。だが、その欲望こそが暴力であり、他者を回収し、分類し、理解可能にしてしまうことで、その人が持っていたはずの“ズレ”を殺してしまう。
TarCoon☆CarToonは、「ズレのままに生きること」を通して、この暴力から逃れようとする。
あるいは、逃げきれないまま、常に“またがっている”。
その構えは、制度的に評価されるものではなく、他者にとって「わかりにくい」ものかもしれない。けれどもオイラは、そこにこそ美しさがあると信じている。なぜなら、そのズレこそが「世界に適合しない人間の姿」の、もっとも誠実な証明だからだ。
社会の物語に回収されない生。それでもなお、他者と関わろうとする構え。
それが「演じきらないことの美学」である。
そしてその美学を感じ取れない社会こそが、最も深い意味での貧しさ=美学の欠如を抱えているのではないか。
善き生とは何か──語りの外で生きること
「50まで生きられたら良い方だと言われてから、善き生とは何かを考え続けてきた」
この言葉は、TarCoon☆CarToonという存在を最も根源的に支えている命題のひとつであるように思う。そこには、生の有限性に直面した者だけが抱く問いの重みがある。そして同時に、それはあらゆる人間に共通する問いをも、静かに投げかけている。「善き生」とは何か──と。
この問いは、誰もが一度は口にしながら、しばしばその意味を明確にしないまま日常のなかに埋没してしまう。しかし、人生においてあらかじめ“カウントダウン”が始まっていると告げられたとき、この問いは突如として抽象的理念ではなく、きわめて具体的で切実な問題となる。
「善き生」とは何か。それは、社会的な評価を獲得することなのか。役割を果たし、有用な人間として承認されることなのか。賞賛されるような困難の克服、または模範的な自己形成こそが、“善さ”を示す尺度なのか。
TarCoon☆CarToonの語りから見えてくるのは、これらの問いに対する静かな否定である。
「善き生」とは、称賛や承認によって測られるものではなく、むしろ誰からも評価されない場所で、誰にも理解されないまま、なお生を引き受け続けることのなかに潜んでいるという感覚である。
それは、他者のまなざしの内側に入って「意味づけられる」ことよりも、その外側で「意味づけを拒みながら関わり続ける」ことを重んじる姿勢である。
語ることが、しばしば承認のための手段に変質してしまう現代において、「語らないまま生きる」ことは一つの困難な選択である。語れば理解されるが、同時に規定される。語らなければ誤解されるが、同時に自由を保てる。TarCoon☆CarToonは、このあいだにあるギリギリのバランスを生きている。
その姿は、まるで「善き生」が語りによって成立するものではなく、「語りの外」で絶えず立ち上がり続けるような在り方であることを示しているかのようだ。
つまり、善き生とは「意味を与える」ことではなく、「意味から外れることを恐れず、なお他者とともにあること」にあるのではないか。ズレのままで関係し続けること、黙っている誰かの沈黙を背負いながら生きること。共感されることを前提とせず、理解されることに頼らず、それでも関わりの手を差し出し続けること。
TarCoon☆CarToonが日々行っているのは、まさにそうした「語りの外の倫理」であり、「語りを超えた共在」の実践である。自らの障害や限界を、特権や自己免罪の根拠とするのではなく、むしろ他者と共に生きるための条件として受け入れる。その姿は、古典的な徳倫理にも似た「実践としての善さ」を体現している。
たとえば、アリストテレスが語った「善き生」は、技術的な成功や効率ではなく、人間としていかにふるまうか、いかに徳を身に付け、いかに共同体に参与するかという問いのなかにあった。TarCoon☆CarToonが示すのは、まさにそのような徳的実践でありながら、現代においては「制度的に正しくふるまうこと」とも、「政治的に規範を提示すること」とも違う、もっと根底的な、「誰にも気づかれないところで、他者の幸せを願い続ける」という構えである。
この構えはまた、自己物語をつくることに疲弊した人々への応答でもある。
現代社会において「自分らしさを語れ」と繰り返されるなか、語りが商品となり、自己がパッケージ化される。しかしそのなかで、TarCoon☆CarToonは「語りすぎずに、なおも関わる」ことを選んでいる。自己を語りきらず、解釈させず、説明し尽くさずに、関係のなかに留まる。その不完全なまなざしの中にこそ、「善き生」の萌芽が宿るのではないか。
そして何より、オイラ(TarCoon☆CarToon)は、自らの生を通じて問い続けている。
「善き生は、成果ではない。日々の歩みに宿る」と。
それは、朝起きて深呼吸をし、何かを笑い、誰かを祝福し、小さな違和感に少しだけ足を止める──そのような極めて具体的で、何のドラマにもならない時間の重なりの中に、確かに存在している。
その生は、感動的ではないかもしれない。
だが、それは決して「空虚な生」ではない。
むしろ、意味を与えられることなく、祝われることもなく、それでもなお誰かの幸福を願い続ける生こそが、最も美しく、最も倫理的であり得るのではないか。
語りの外で生きること。
沈黙のなかで他者と共にあること。
理解されずとも、他者を信じること。
そのすべてが、「障害を引き受ける」という行為のもう一つの姿であり、
そしてまた、「善き生」と呼ぶにふさわしい実存のあり方なのだと思う。
おわりに──重なりきらなさを生きるという倫理
オイラは、その人物──TarCoon☆CarToonの存在を通して、「障害とは何か」という問いを、やがて「語るとは何か」「関わるとは何か」「生きるとは何か」という、より根源的で逃れがたい問いへと導かれていった。
彼/彼女(あるいは彼ら)が見せるふるまいは、自己を語り尽くすことを避け、あらかじめ設計された役割を演じきることから逸れている。それは「わかりやすさ」や「共感」という通路をあえて通らずに、別の道筋を辿るような姿勢である。
その態度は、しばしば距離を生み、誤解を招きもする。けれども、その曖昧さのなかにこそ、オイラは、一つの確かな倫理的態度を感じ取っている。
それは、「理解されたい」という欲望を軸とした関係ではなく、「関わりたい」という誠実さに支えられた姿勢である。他者を自らの世界に取り込もうとするのではなく、交わらぬままに隣り合うことを引き受けようとする、その静かな決意のようなもの。
この関係性は、決して滑らかな融合を目指さない。むしろ、響きあいながらも決して完全には共鳴しきらない距離のなかで、おのおのが声を持ち、沈黙を保ち、まなざしを送りあう関係である。それは、詩のように「たしかな意味」を持たぬまま、それでも人の心に深く届くやりとりのように見える。
このような関係のなかでは、障害という言葉すら相対化される。もはやそれは「特殊な状態」や「欠如」として捉えられるのではなく、**全ての人が抱える“他者になりきれないことの痛み”**として再認識される。
誰しもが、自分と他者のあいだにある非対称を完全には埋められないまま生きている。障害とは、そうした非対称がより強く、よりはっきりと現れてしまう状況にすぎないのではないか。だとすれば、それは排除されるべき異常ではなく、誰もがすでに抱えている「届かなさ」や「行き違い」の極限的な形である。TarCoon☆CarToonは、その極限に立ちながらも、そこを「断絶」ではなく「共生の入り口」として開こうとしている。
重要なのは、「わかりあうこと」よりも「わかりあえないことを受け入れながら、ともにいること」なのである。
この構えは、たとえばハンナ・アーレントが『人間の条件』で述べた「他者とともに現れる」という人間の根源的あり方にも通じる。他者は、決して自分の延長線上にはいない。それぞれが固有の始まりを持ち、固有の世界を持っている。だからこそ、完全な一致や同一性ではなく、呼応しきらないままにそばに在ることが、関係の始まりなのである。
TarCoon☆CarToonの生き方においては、この「呼応しきらなさ」こそが出発点となっている。彼/彼女の活動は、誤解を恐れず、時に滑稽さをも引き受けながら、「それでもあなたと共にいたい」という姿勢を貫いている。それは、コミュニケーションの成否ではなく、「共に在ろうとする意思」そのものを価値とみなす、非常に誠実な生の構えである。
また、その構えには、ある種の美的感覚が宿っている。整ってはいないが、確かにそこに「美しさ」がある。完成ではなく生成、均衡ではなく余白、調和ではなく多声。それらの要素が互いに反響し合いながら、TarCoon☆CarToonの思想と存在を形作っている。
美とは、観念のなかに閉じこもった秩序ではなく、どこまでも現実に食い込み、関係の傷痕や未完を抱えながらもなお、人と人とを結びなおす力なのではないか。
倫理とは、ルールや規範の体系ではなく、そうした美しさを絶えず生き直す営みなのではないか。
このような意味において、TarCoon☆CarToonは、単に障害者というカテゴリに回収されるべき存在ではない。むしろ、「他者のままに生きること」「完全には重なり合えないまま、しかし関係を断たずにいること」──そうした倫理的・実存的課題を我々に提示してくる、きわめて現代的で普遍的な思想の担い手である。
善き生とは何か。
それは、おそらく「理解されること」ではなく、理解されなくともなお、生き続けること。
そして、他者の理解をあてにせずとも、その場に佇みつづけ、関係しようとすること。
語りの外で、制度の下ではなく、人と人とのあわいで、そっと息をつくように生きること。
そのような生にこそ、倫理の始まりを、美のかたちを、そして善き生の輪郭を、オイラは見出している。
そしてその輪郭は、これからも更新され続けるだろう。
TarCoon☆CarToonの実践が、誰かの静かな共振を誘い、言葉にならない経験が、また別の誰かの生を照らす──
そのような、「語られぬ連帯」のネットワークとして。
これは、断言されるべき主張ではない。
ただ、問いかけの形で、今もあなたの傍らに息づいている。
──オイラたちは、どのように「共に在る」ことができるのだろうか。