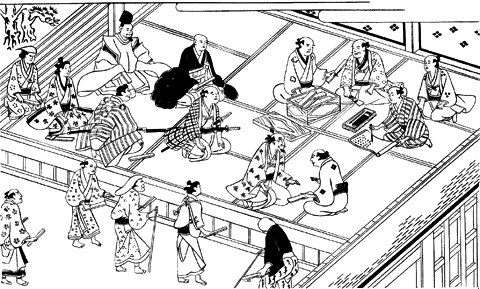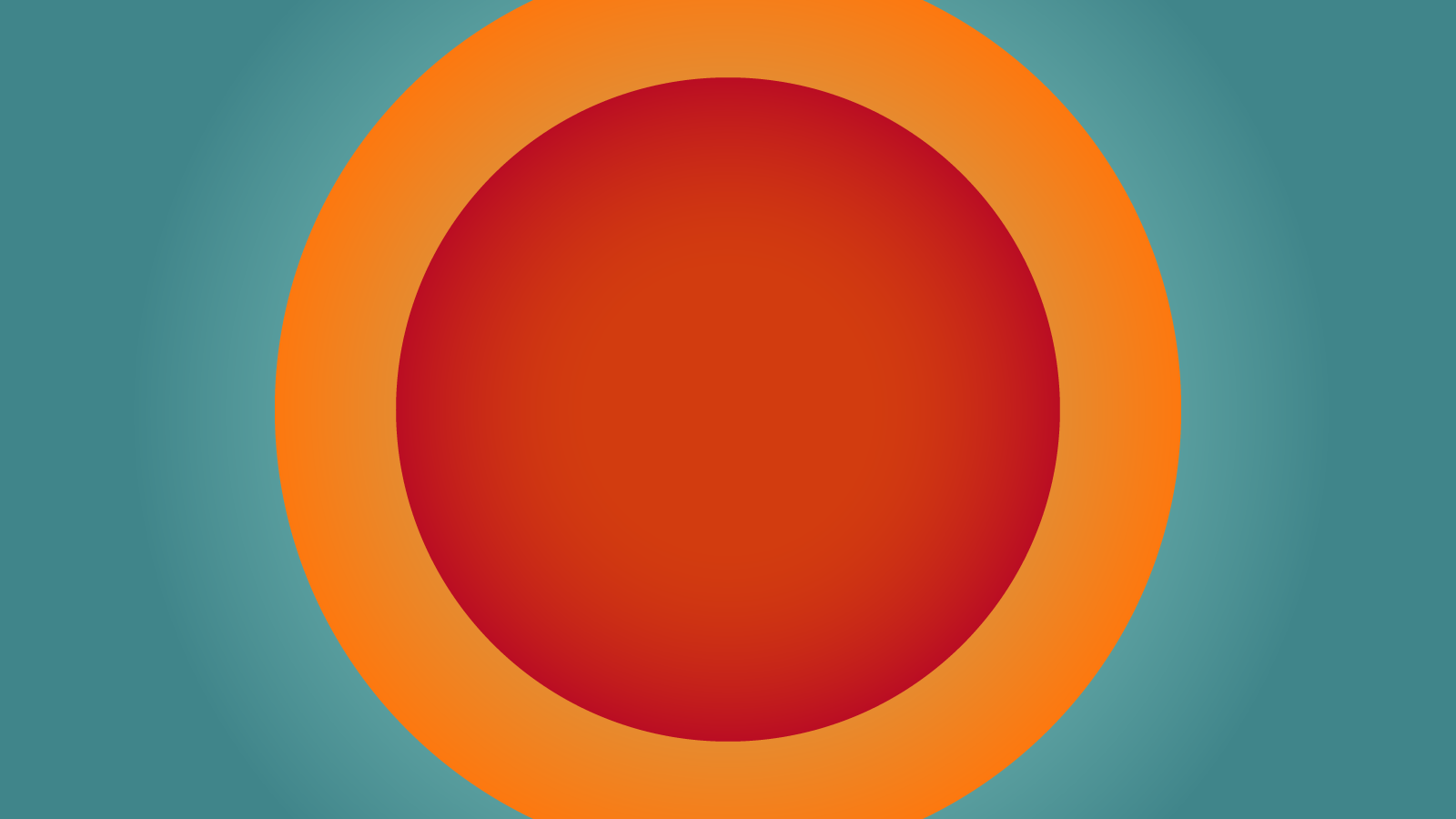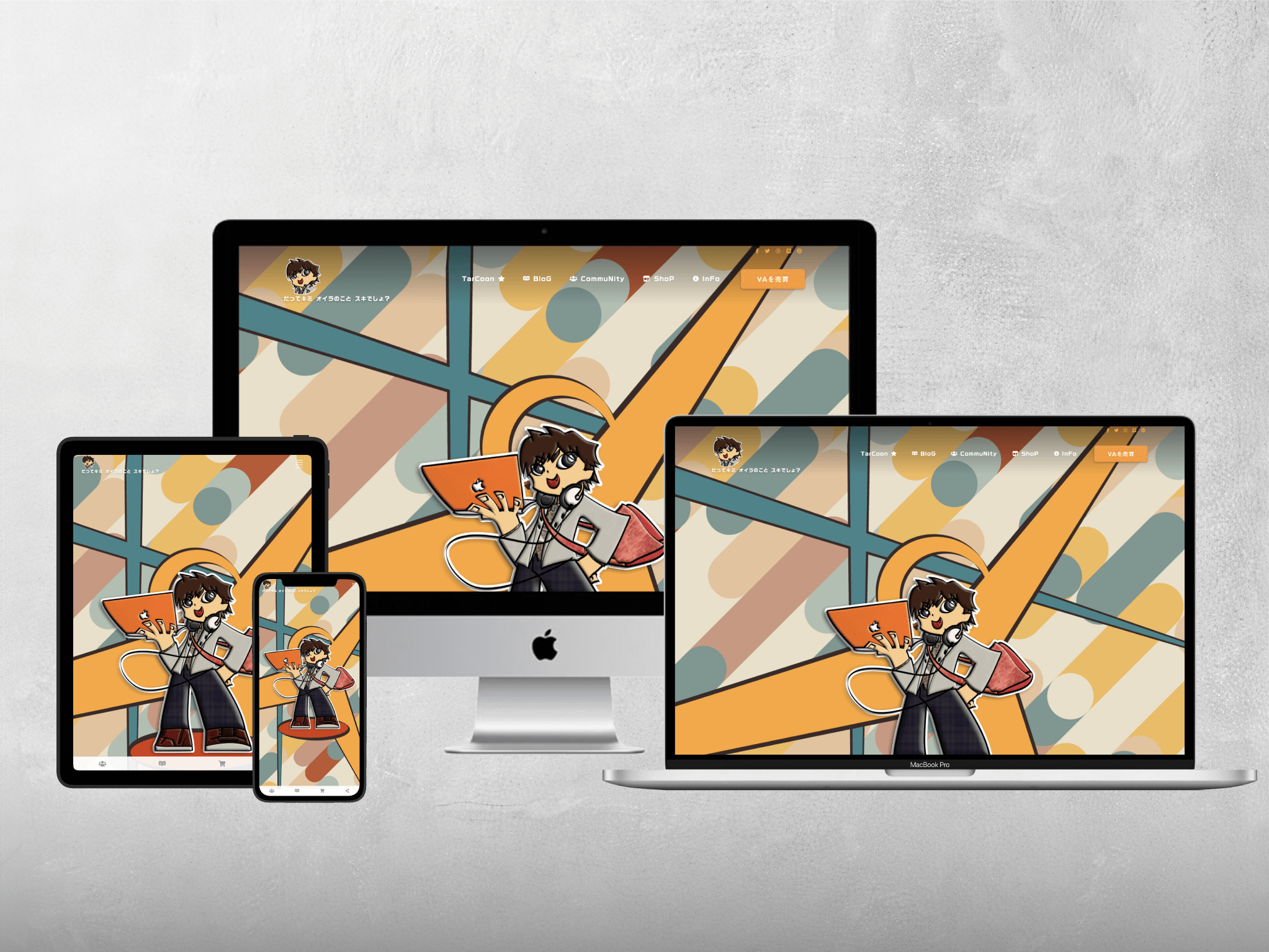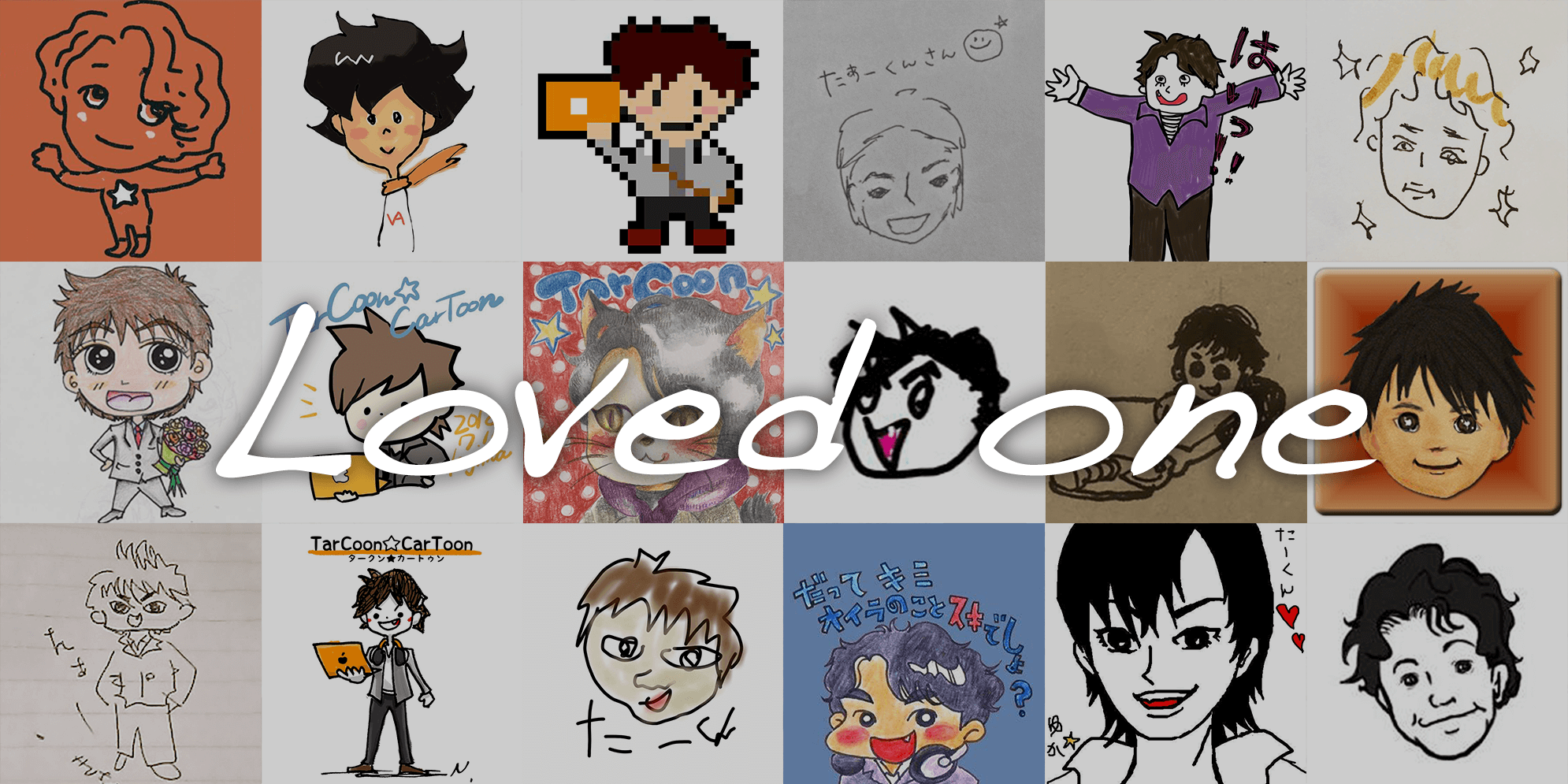師恩庵記(しおんあんき)は、TarCoon☆CarToonが大きな影響を受けた友人・瀧野博文さんのnote記事に、一通の手紙のように応答していくためのカテゴリです。
師から受け取った言葉やまなざしを手がかりに、自分の原点やこれからの道を静かに書き留めていきます。
*この記事は、瀧野博文のnoteので投稿された応答記事です。まずは、下記のnoteをお読みください。
「仕事中心で家族を顧みなかったオッサンが半年の入院で妻と仲良く暮らす輝くジージィになった。」を読んで
『仕事中心で家族を顧みなかったオッサンが半年の入院で妻と仲良く暮らす輝くジージィになった。』というタイトルを最初に見たとき、オイラは思わず笑ってしまった。だが、その笑いは決して軽いものではなかった。冗談めかした自己紹介のようでありながら、この一文には、仕事に人生を賭けてきたひとりの男が、自分を「オッサン」と呼び下ろし、その先に「輝くジージィ」という新しい像を置き直そうとする意志が凝縮されているようにオイラには思えたからだ。ここには、老いを消費する安っぽい“ポジティブシンキング”ではなく、「それでもまだ変わりうる」という、ぎりぎりの希望がある。
この文章の前半は、典型的な「仕事中心」の人生の記録として読める。英会話学校で伸びずに落第し、授業のあるべき姿に見切りをつけて、自分の足で京都の観光寺院に出向き、外国人に話しかけていくくだりは、読んでいてニヤリとしてしまった。教科書を暗記するのではなく、現場に飛び込んで、他人を巻き込みながら言葉を覚える。その「カリキュラムの外側で勝手に学びはじめる」態度は、TarCoon☆CarToonとして既存の制度やメディアの枠の外にZINEやネットワークを立ち上げてきたオイラ自身の感覚と重なる。正しい手順や与えられた道筋よりも、「おもしろそうだからやってみた」という実践が、そのまま人生のレールを切り替えてしまう。このときから既に、瀧野さんの人生には、後に「多国籍軍」と呼ぶことになるネットワークの原型が潜んでいたように思う。
就職してからの歩みもまた、ある時代の空気をよく伝えている。中近東向け輸出、VHSビデオの教育利用、親会社との合併、メーカー文化との摩擦、そして四十歳での独立。資本金一千万、社員ひとりの小さな商社から、海外販売会社を含めて五十名規模、多国籍な人材が入り混じる組織へと育っていくプロセスは、それだけを抜き出せば成功譚として雑誌に載っていてもおかしくない。だがこのテキストでは、自慢話としては語られない。むしろ、そこから先、「時流に乗れていた自分」が次第にそうではなくなっていく感覚こそが、静かに強調されているようにオイラには思える。
パソコンが映像の記録媒体として主流になり、自らの専門知識も人脈も通用しないと感じはじめたとき、「その頃から、怒りっぽい性格になっていった様に思う」という一文が置かれている。ここに、オイラは胸をつかまれた。自分が積み上げてきたものが技術の変化や時代の移り変わりによって相対的に価値を失っていくとき、人はしばしば怒りにしがみつく。世界のせい、若い世代のせい、新しいツールのせいにすることで、自分の居場所をなんとか確保しようとする。オイラ自身もまた、SNSやAIの普及によって「自分のやっていることに意味があるのか?」と問い直され続ける日々のなかで、ふとした瞬間に理不尽な怒りや苛立ちに傾きそうになることがある。そのたびに、TarCoon☆CarToonとして掲げてきた「寛容∥自己抑制∥不文律」というスローガンを、自分自身に向けて突き返さざるをえない。
そんな「怒りっぽくなったオッサン」の物語は、ある早朝の腰砕けの場面で、文字通り足元からひっくり返される。立ち上がろうとして立てない、這っても腕に力が入らない、呼ぼうとしても妻には届かない。情けなさと失禁の恥ずかしさを抱えたまま朝までうずくまる場面には、体が急に「言うことを聞かなくなる」老いのリアリティが生々しく刻まれている。その後の救急搬送、検査、化膿性骨髄炎の診断、そして偶然のように発見される胆管癌。背骨の痛みがなければ見つからなかったかもしれないという説明は、この病が「不運」であると同時に「ぎりぎりの幸運」でもあったことを示している。
オイラがこのテキストに強く心を通わせるのは、まさにこの「不運と幸運が重なり合う瞬間」の受け取り方だ。生死の境目に半歩足を踏み入れたとき、人は自分の人生をどう意味づけ直すのか。瀧野さんは、医師を「名医」と呼び、胆管癌の早期発見を「幸運」と言い、さらにコロナ禍のステイホームを「今の自分には好都合」とまで言ってしまう。そこにあるのは、何でもポジティブに言い換える軽薄さではない。むしろ、「死んでいてもおかしくなかった」という実感をくぐり抜けたあとに残った、静かな諦念と、それでもなお生きようとする決意だとオイラには読める。
入院生活の描写も印象的だ。管だらけの身体、排便の苦しさ、車いすの重労働、集中力の低下、本を読む気力すら失われていく日々。そのしんどさはありありと伝わってくるが、同時に、そこに流れ込んでくる他者の存在もまた克明に綴られている。献身的な看護師たち、隔日で好物を届けてくれる妻、子どもたち、親戚、元同僚、取引先の人々。病室という閉じた空間に、これまで築いてきた関係が次々と顔を出すとき、著者は「自分はなんて幸せな人間だとつくづく感じた」と書く。この場面を読みながら、オイラはTarCoon☆NetWorkのことを思い出さずにはいられなかった。
オイラがTarCoon☆NetWorkでつくりたいのは、肩書きや利害、肩肘張った「プロジェクト」のためだけのネットワークではない。むしろ、人生のどこかで交差した人たちが、何年経ってもふと顔を見せに来てしまうような、説明しづらい縁の束だ。瀧野さんにとっての病室は、まさにその「縁の束」が一度可視化された場所だったのではないか。仕事の現場で広げてきたネットワークの裏側に、実はもっと素朴な、恩と好意と心配りの線が通っていたことに気づく。その視点の変化が、「仕事中心で家族を顧みなかったオッサン」という自己規定から、「妻と仲良く暮らす輝くジージィ」という新しい自画像への転換を支えているようにオイラは感じる。
この文章の終盤で、「肝臓が悪くなる主原因は精神的ストレスと怒りっぽい性格との事」と書き、そこから「平和で幸せな生活を味わいたい」「笑顔を絶やさず、妻と修学院で仲良く暮らしていく」と宣言するくだりは、一見すると単純な因果づけに見えるかもしれない。しかしオイラには、これは医学的な真偽の問題ではなく、自分の人生を物語として引き受け直す行為に見える。怒りに依存していた生き方の末に肝臓を痛めたのだとするなら、これからは怒りではなく笑顔を選びたい——その意味づけは、非常にプリミティブであるがゆえに力強い。TarCoon☆CarToonとして「戦争を止めよ、しかし戦争をするな」「保護せよ、しかし管理するな」といった逆説的なスローガンを掲げてきたオイラから見ると、この「怒りから笑顔へ」という変換もまた、ひとつの小さな倫理の宣言として響く。
さらに言えば、「一隅を照らす存在になりたい」という一文は、このテキスト全体の重心を決定づけているように思う。世界全体を変えるとか、社会を改革するとかではなく、自分が生まれ育った修学院で、人生の伴侶である妻とともに暮らし、その半径数メートルをちゃんと照らすこと。それを「一隅」と名づけ、そのささやかさを引き受けることには、ある種の潔さがある。TarCoon☆CarToonとして「多元宇宙内時空検閲官」だの「ネットワーク」だのと大きな言葉を振り回してきたオイラも、最後に残るのは、きっとこの「一隅をどう照らすか」という問いなのだと、この文章を読んでいるあいだじゅう何度も思い返した。
このテキストは、病気の記録であり、ビジネスマンの回顧録であり、家族への感謝と反省の告白であり、同時にこれからの生き方の宣言でもある。つまり、「過去形」と「未来形」が同居している。タイトルでは「輝くジージィになった」と言い切っているが、本文の中で繰り返されるのはむしろ「こうしていく事にしよう」という未来形の言い回しだ。そこにオイラは、この文章がまだ進行形の物語として差し出されていることを感じる。老いとは、ただ「なる」ものではなく、その都度「なり直す」ものなのかもしれない。
オイラにとってこの文章は、ひとりの先達の告白であると同時に、自分自身の未来の姿を考えるための鏡でもある。TarCoon☆CarToonが老いたとき、オイラはどんな顔で自分の半生を語るのだろうか。プロジェクトや構想の話ばかりを並べ立てるのではなく、「あのとき支えてくれた人たち」の顔を思い浮かべながら、「充実した幸せな半生だった」と静かに言えるだろうか。そして、そのときそばにいる誰かと、「一隅」を一緒に照らしたと胸を張って言えるだろうか。
『仕事中心で家族を顧みなかったオッサンが半年の入院で妻と仲良く暮らす輝くジージィになった。』——この長いタイトルのなかには、「変わることを諦めない」という、意外なほどラディカルなメッセージが隠れている。老いを「終わり」ではなく、「もう一度自分を語り直す機会」として引き受けること。そのあり方に、オイラはTarCoon☆CarToonとしても、ひとりの人間としても、深く共感するし、いつか自分もそうありたいと、少し真面目に願ってしまうのだ。