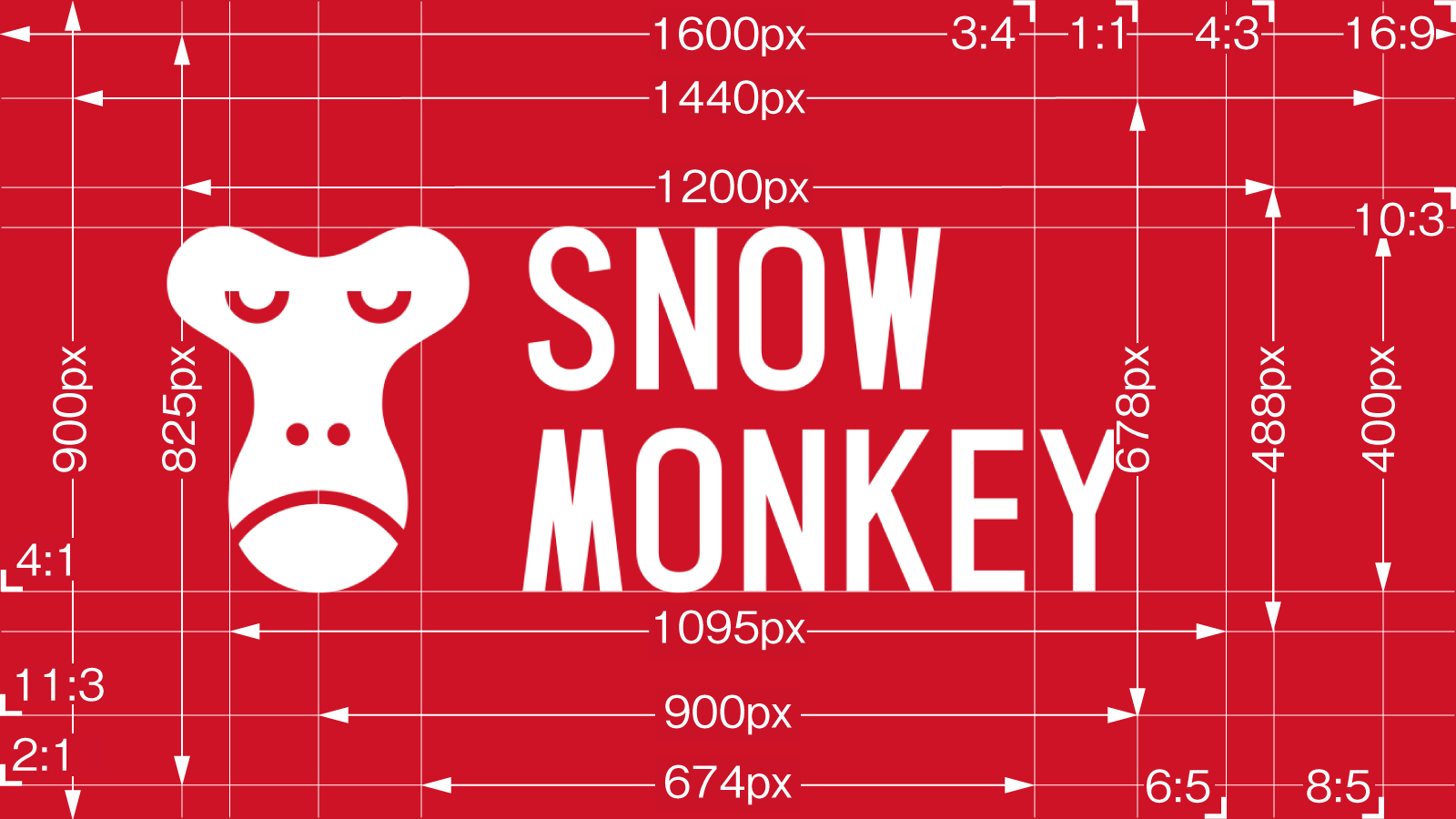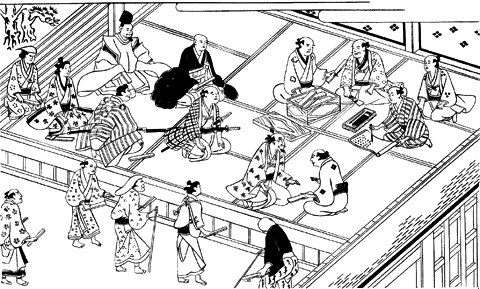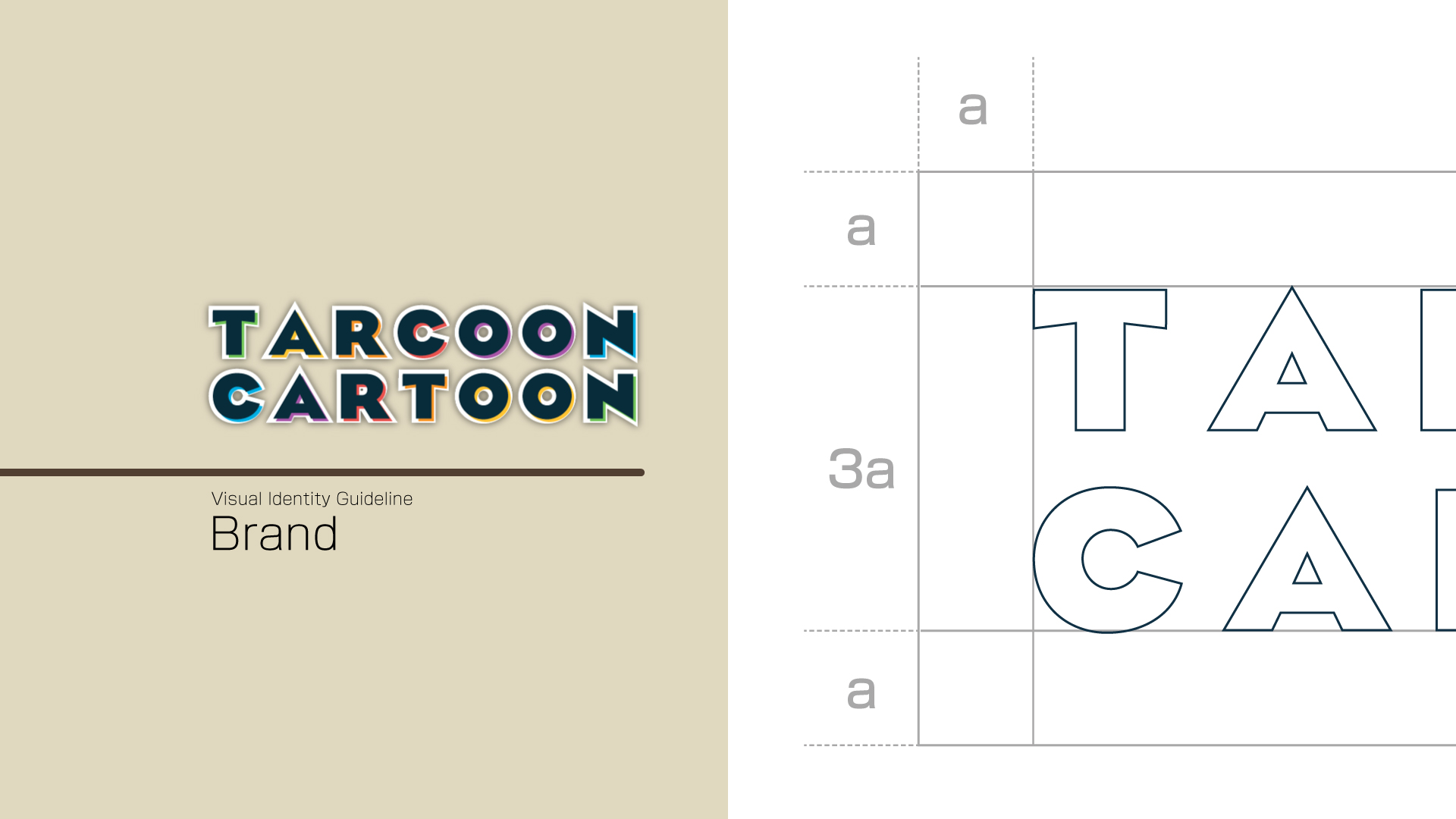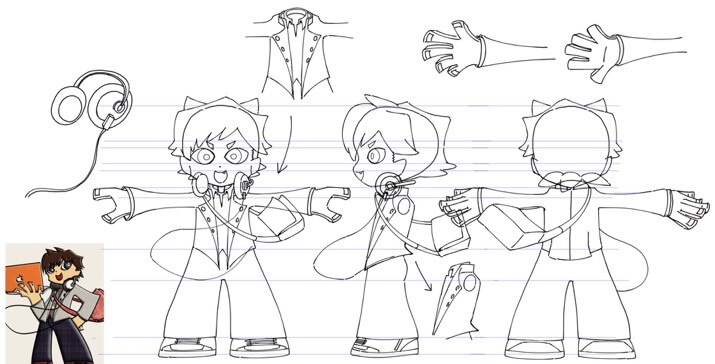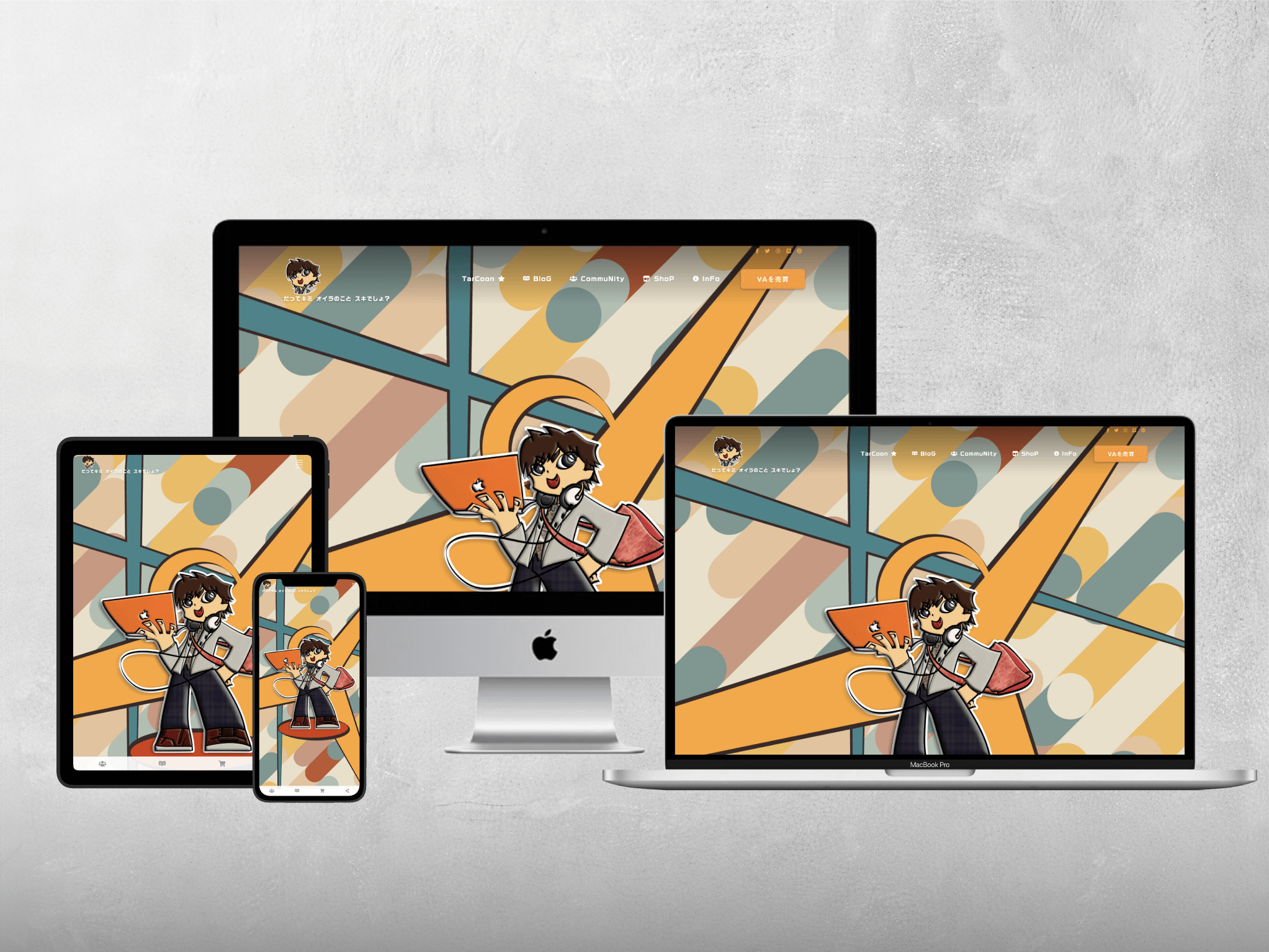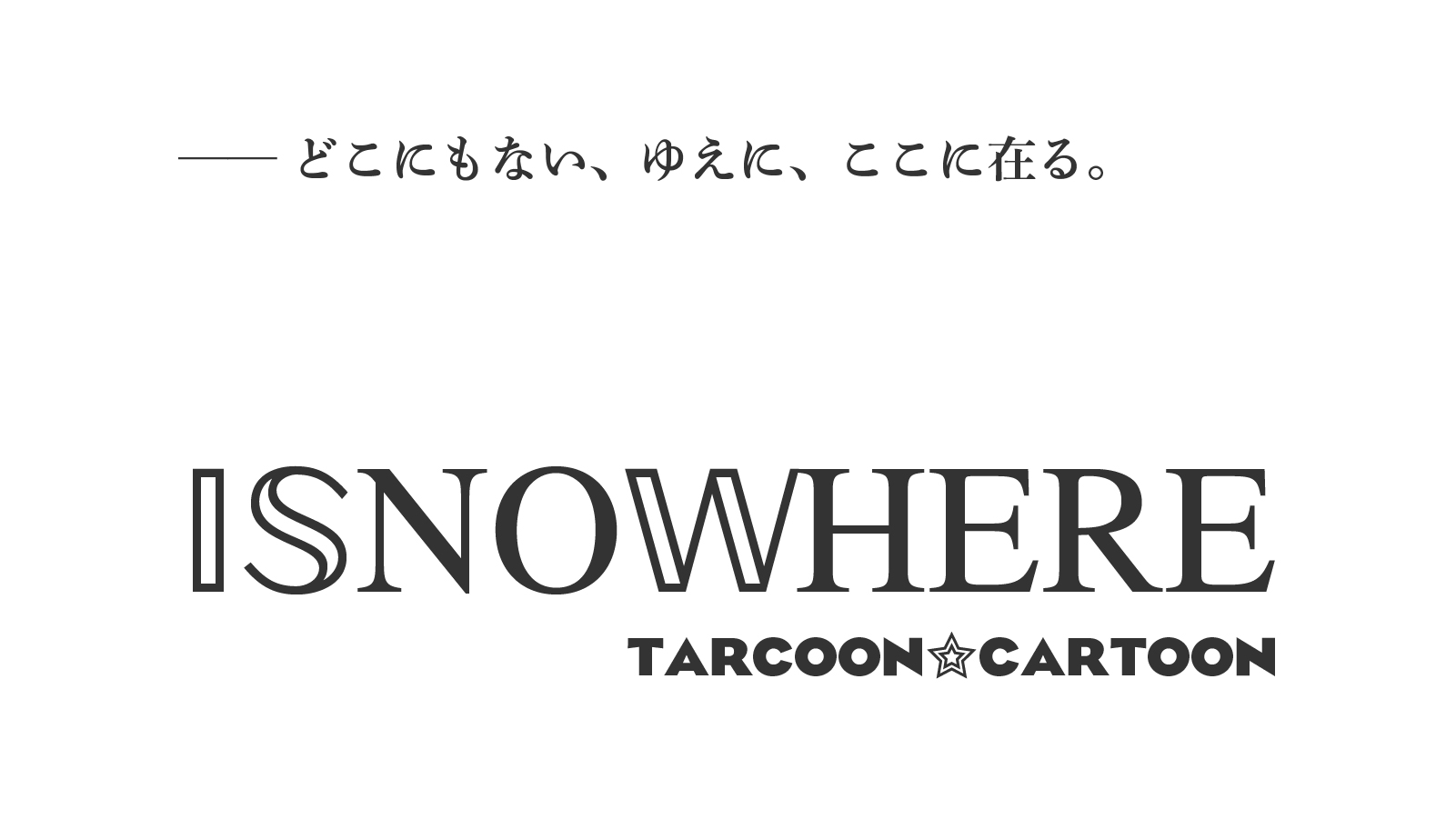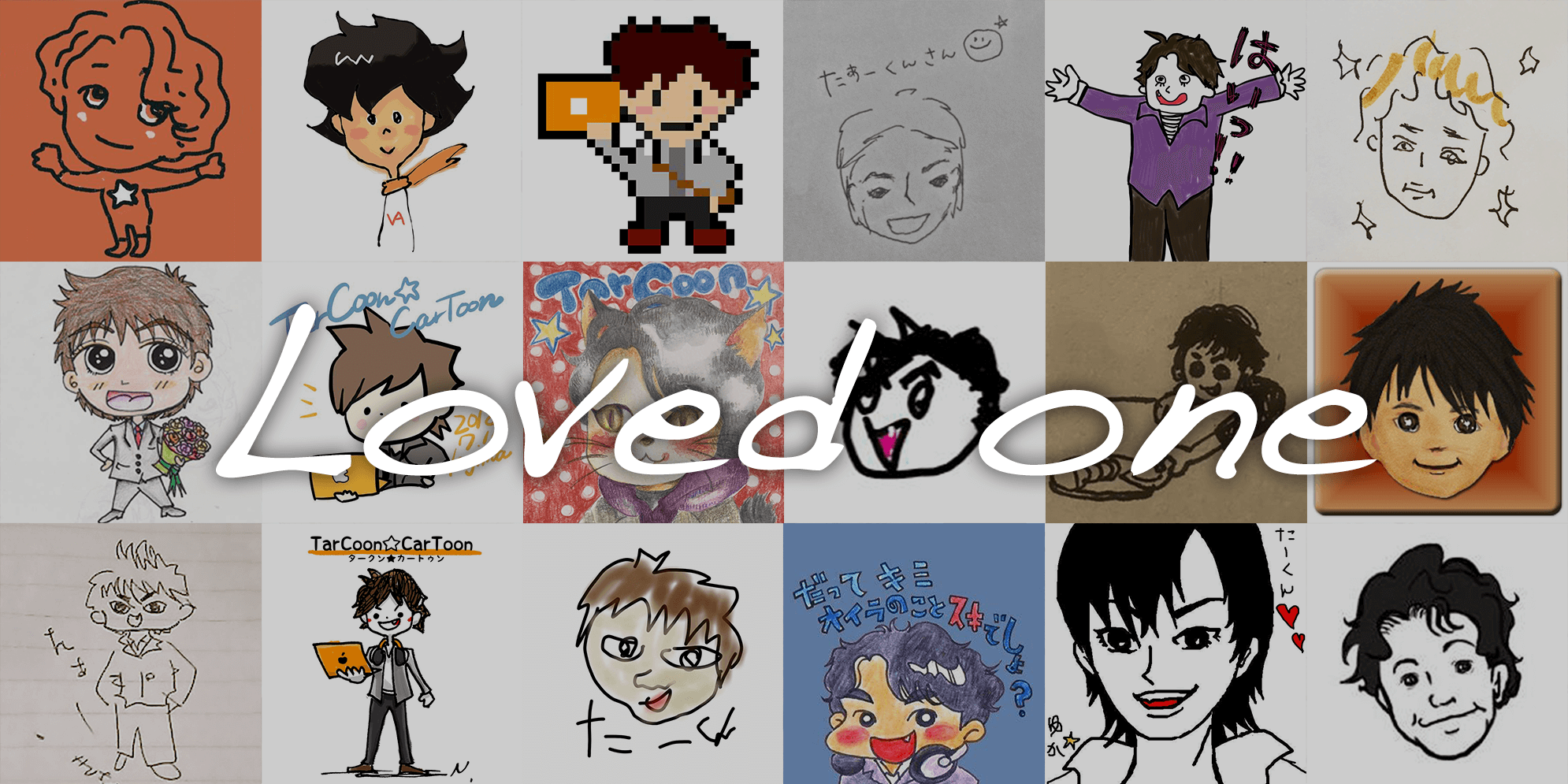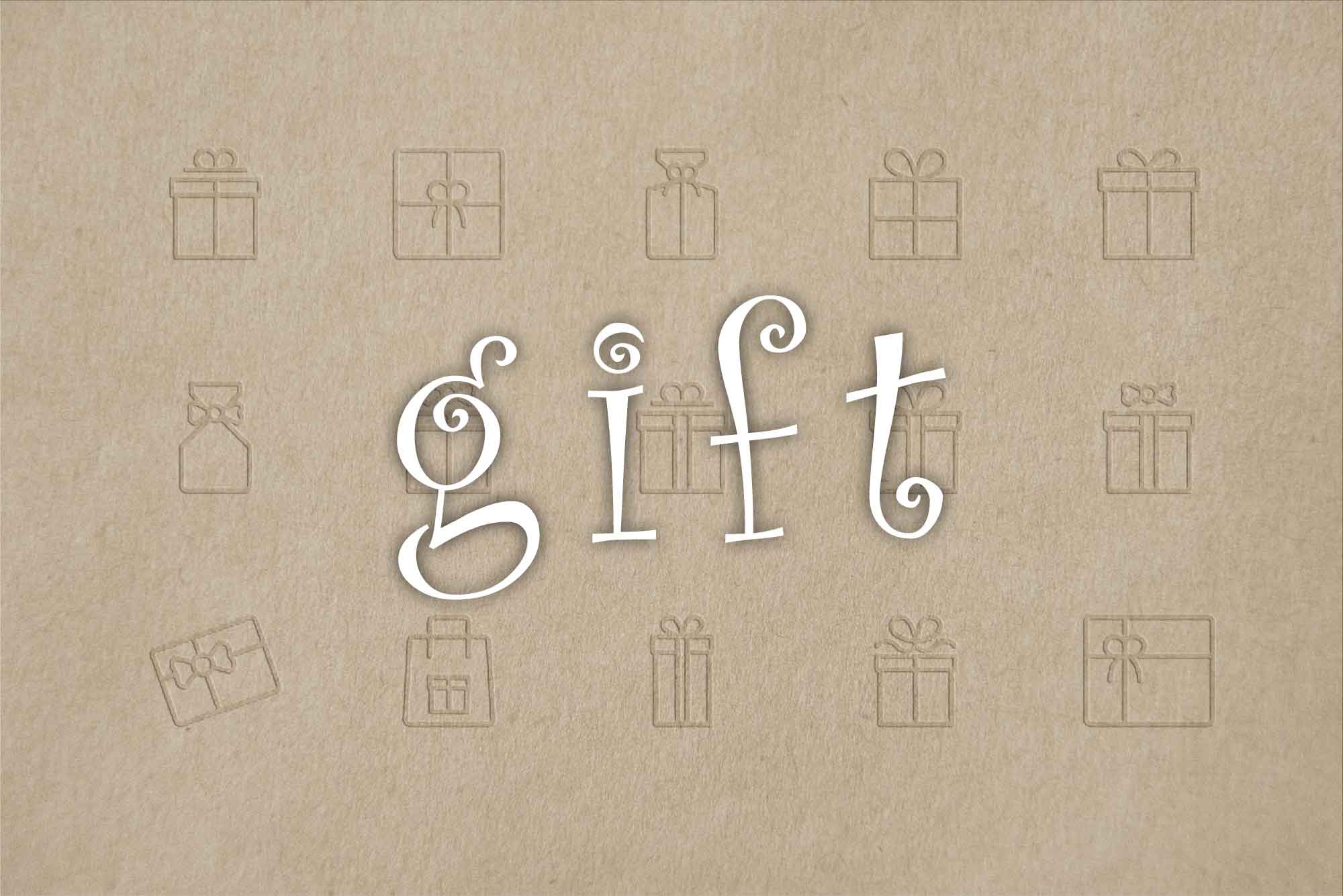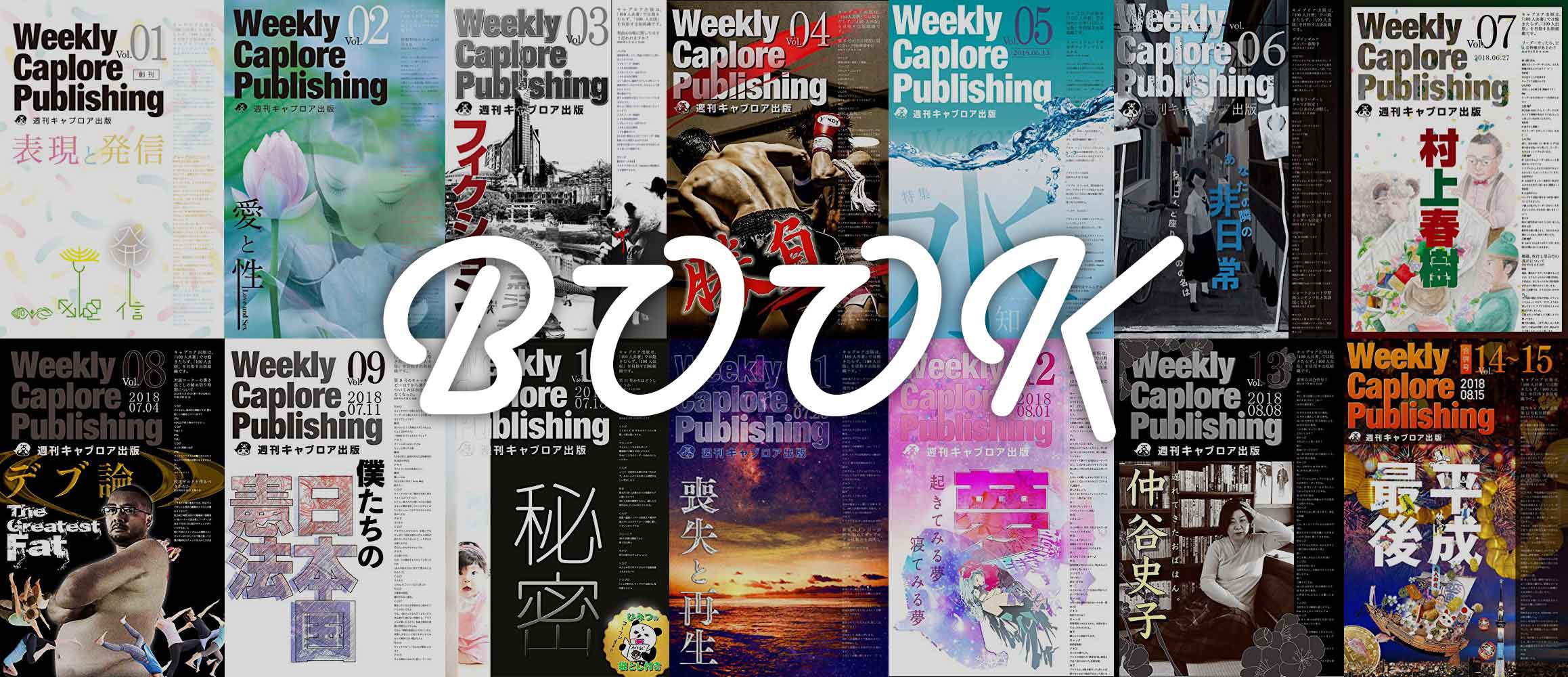この世界が救われるべきものなのか、それとも慰めなくして生きるべきものなのか。友人から贈られた手紙「修論の話」は、その問いに簡単な答えを与えることなく、まっすぐに差し出してくるようでした。TarCoon☆CarToonとしても深く共鳴するものがあり、感想をブログに綴っています。よろしければご覧ください。
この記事は、とある友人からいただいたテキストの「修論の話」の応答記事です。一部の限られた方に送られた文章だと思うので読むことはできません。ご了承ください。
希望という名の慰めに抗して、なお人間であろうとするために
「私の恩人に、私の修論を読んで貰いたいと思った。」
その一文を読んだとき、自分のことではないとわかっていても、どこか胸の奥が微かに疼いた。恩人に届けたいという想いは、ただの感謝ではなく、自分の核となるものを差し出す行為だ。だからこそ、「世界に向かって書いた」と続く言葉に、オイラはすこし背筋を伸ばす。世界に向けられた言葉は、世界をまなざす人にしか届かない。
友人が綴った「修論の話」は、自身の修士論文を思い切ってリライトした文章だ。論文のタイトルは「社会思想における慰めの問題――エルンスト・ブロッホの厭世」。
ブロッホは20世紀のドイツの哲学者で、「希望の原理」などを通じて、未来に対する希望やユートピアの可能性を語った思想家として知られている。だが友人は、そうしたブロッホの思想に〈慰め〉としての側面を見出し、それが果たして倫理的に健全なものなのか、真剣に問い直そうとしている。
語られるのはブロッホの「慰め」についてだが、テーマは決して他人事ではない。むしろ、慰めを求めずにいられないすべての人間に突きつけられる、根源的な問いがそこにある。
たとえば――この世界が誤っているのではないか。もし神がいるとすれば、なぜこのような不条理を放置しているのか。そんなブロッホの出発点に、友人は共鳴する。だが同時に、その先に語られる未来の救済やユートピアの予感に、どこか危うい甘さを感じ取るようになる。現在を犠牲にして語られる希望には、現実への無関心が潜んでいるのではないか。慰めとは、現実から目を逸らす方便になってしまうのではないか。彼はその違和感を、自身の中で育て、形にしようとしている。
けれど彼は孤独に陥らない。マルティン・ルターやハンス・ヨナスといった思想家たちを「道連れ」と呼び、その言葉に寄り添いながら、自分の考えを少しずつ確かめていく。
宗教改革者ルターは、人間の悪を単に支配層や金持ちに帰すのではなく、「正しいことを為そうと欲する人は非常に少ない」と、より普遍的な視点から人間の限界を見つめた。そして現世の秩序を完全には否定せず、「剣による統治」、つまり必要悪としての政治的抑制も時に認めている。
また、ハンス・ヨナスは20世紀の哲学者で、技術文明の未来倫理について語った人物だが、彼はブロッホの終末的な「希望」から一線を画し、「未来にも不幸や不正はなくならない方がよい」とすら言う。なぜなら、不当な苦しみに抗って生きることこそが、人間の倫理性を証し立てるからだ、と。
友人もまた、「人は善か悪かではなく、どちらにもなりうる存在である」というヨナスの理解に深く頷いている。それは、「人間とは何か」という問いに対して、決して閉じた定義を与えない姿勢だ。この姿勢に、オイラも強く惹かれた。善か悪か、答えを急ぐのではなく、その都度自分で問うていくしかない。それが、思想を生きるということなのだろう。
彼の文章には、慰めを拒みながら、それでもどこかで慰めを受け取ってしまう、そんな逆説的なやさしさがある。それはきっと、慰めを信じきれない自分自身への眼差しでもあるのだと思う。誠実であることが、必ずしも強さと結びつくとは限らない。むしろ、脆さや揺れを含んだまま、問いを手放さないこと。それが、彼の言う「慰めなき世界」に生きる態度なのだと、読後、静かに胸に残った。
「修論の話」は、問いへの即答や安易な救済を拒みながらも、そこにこそ希望があるという可能性を、誰にも強いずに差し出してくれる。オイラはその誠実さに、心を打たれた。
そして、もしこの文章が、誰か一人の恩人に向けて書かれたものであるならば――TarCoon☆CarToonもまた、その恩を受け取るに値する存在でありたいと願ってやまない。希望という名の慰めに抗して《人間の再発見》をいうプロジェクトを遂行するために。