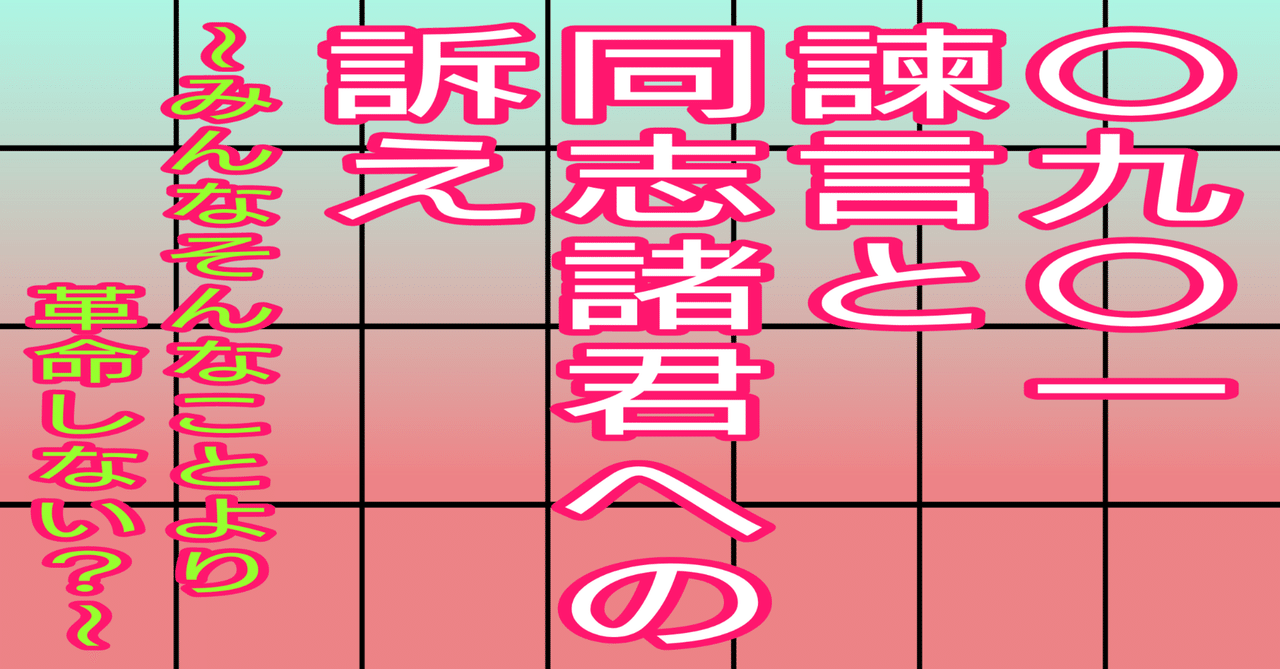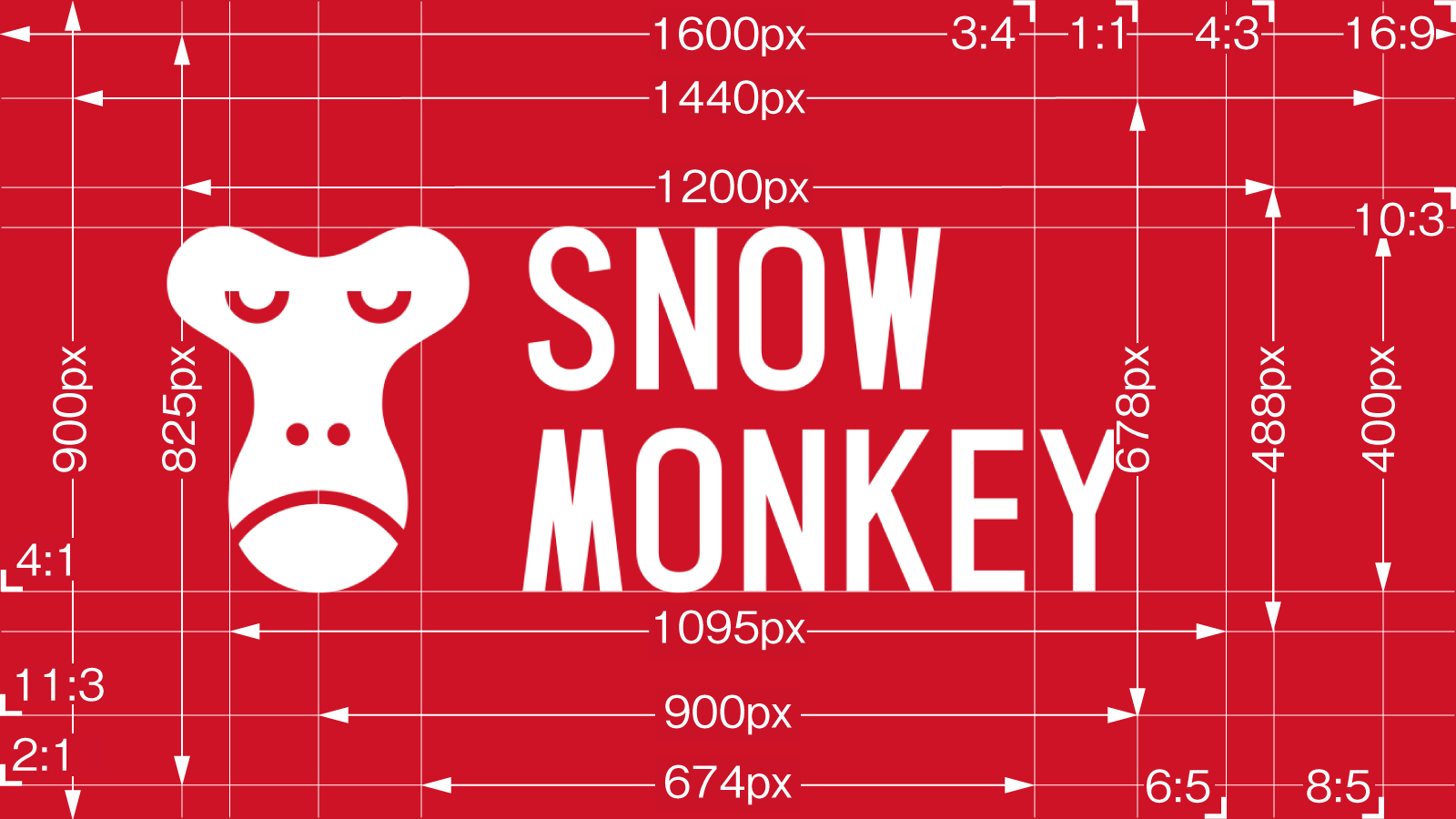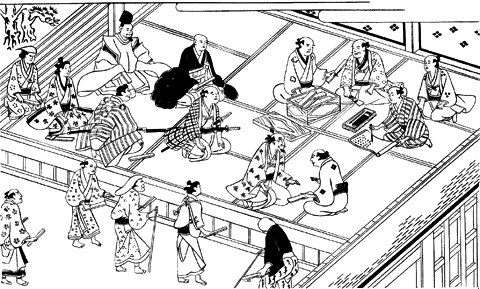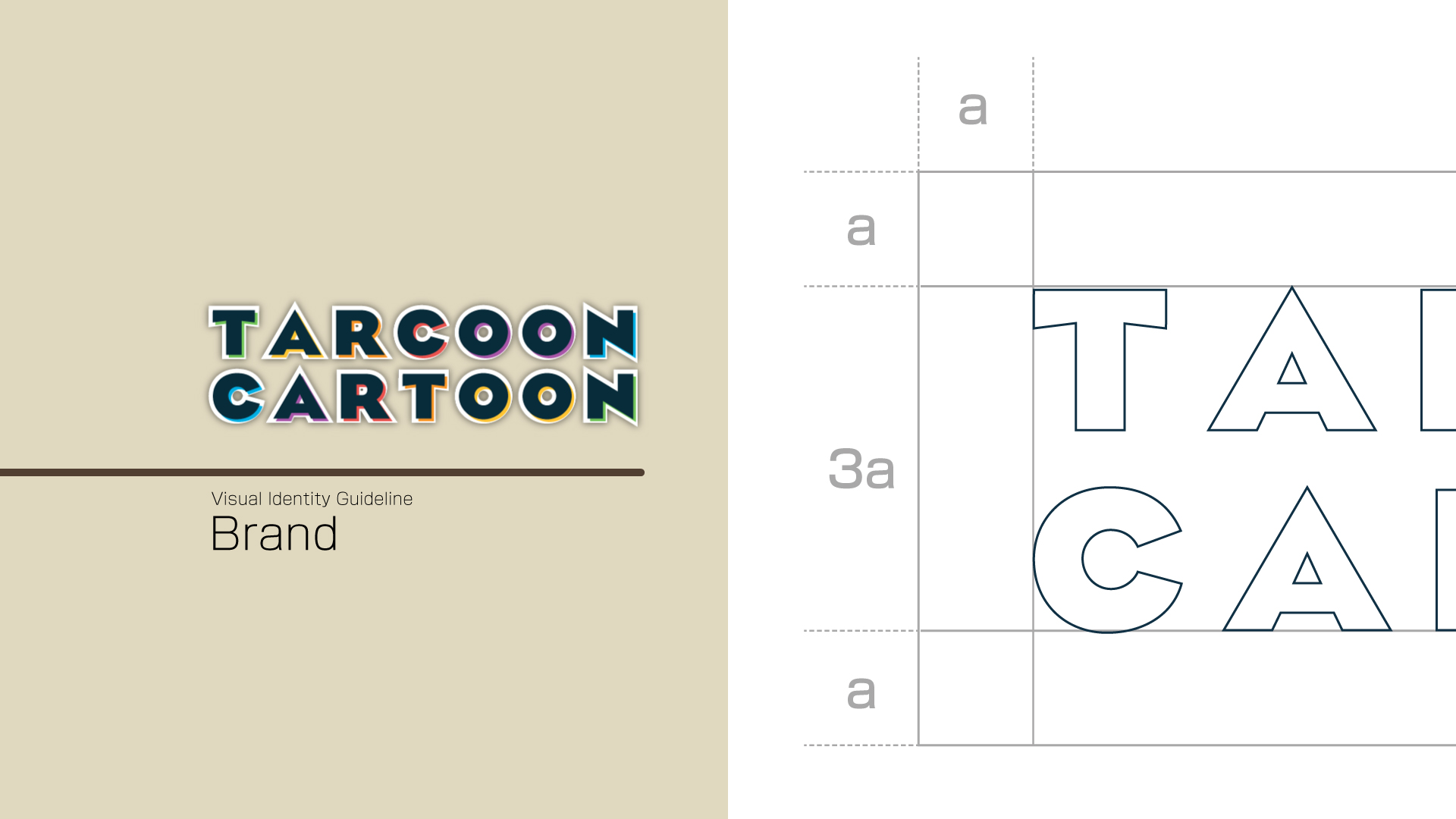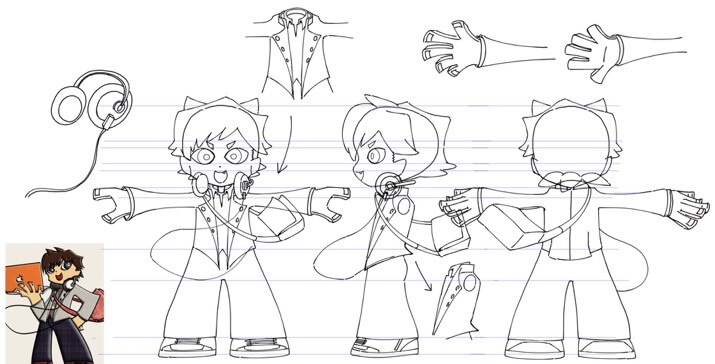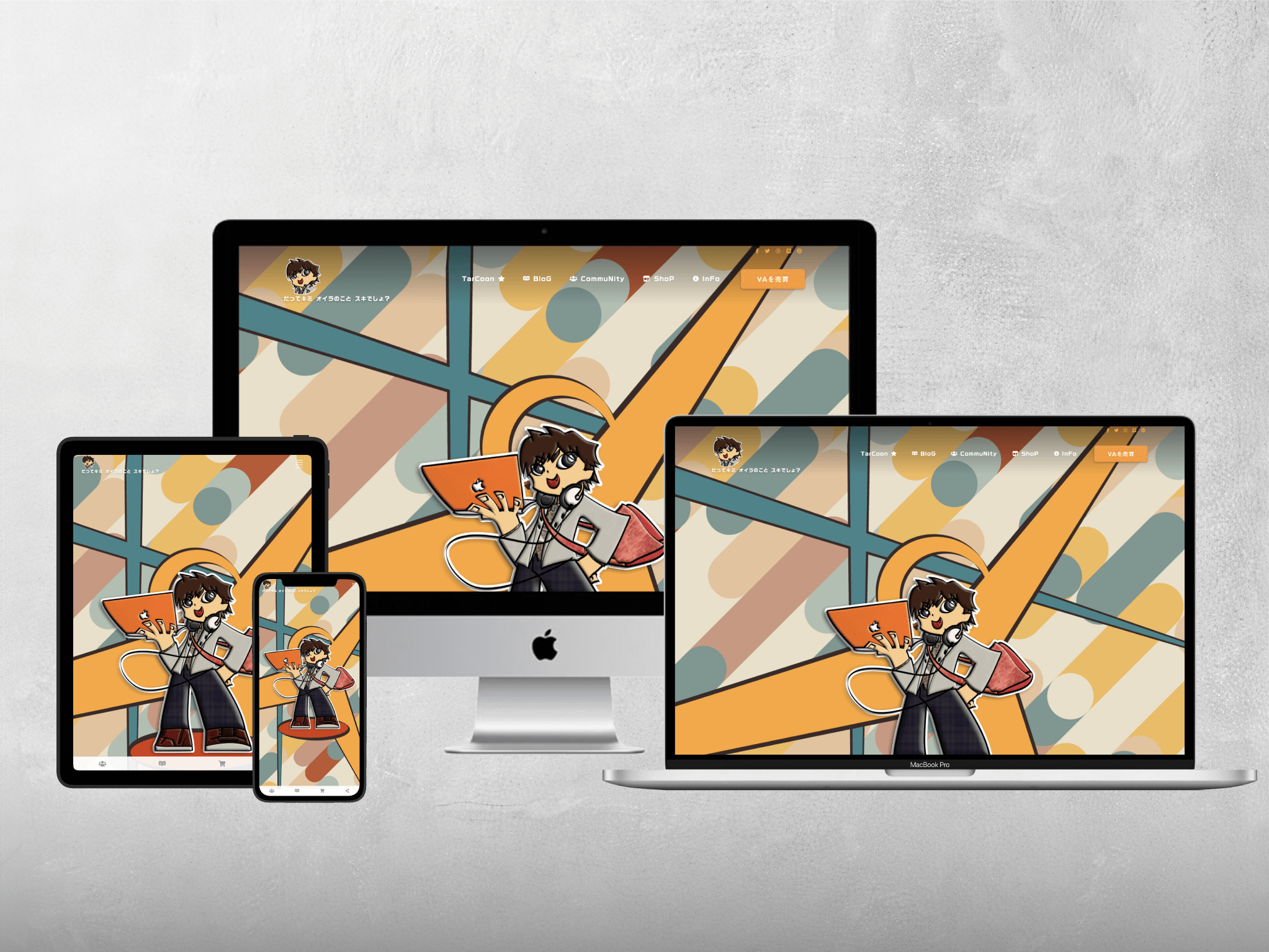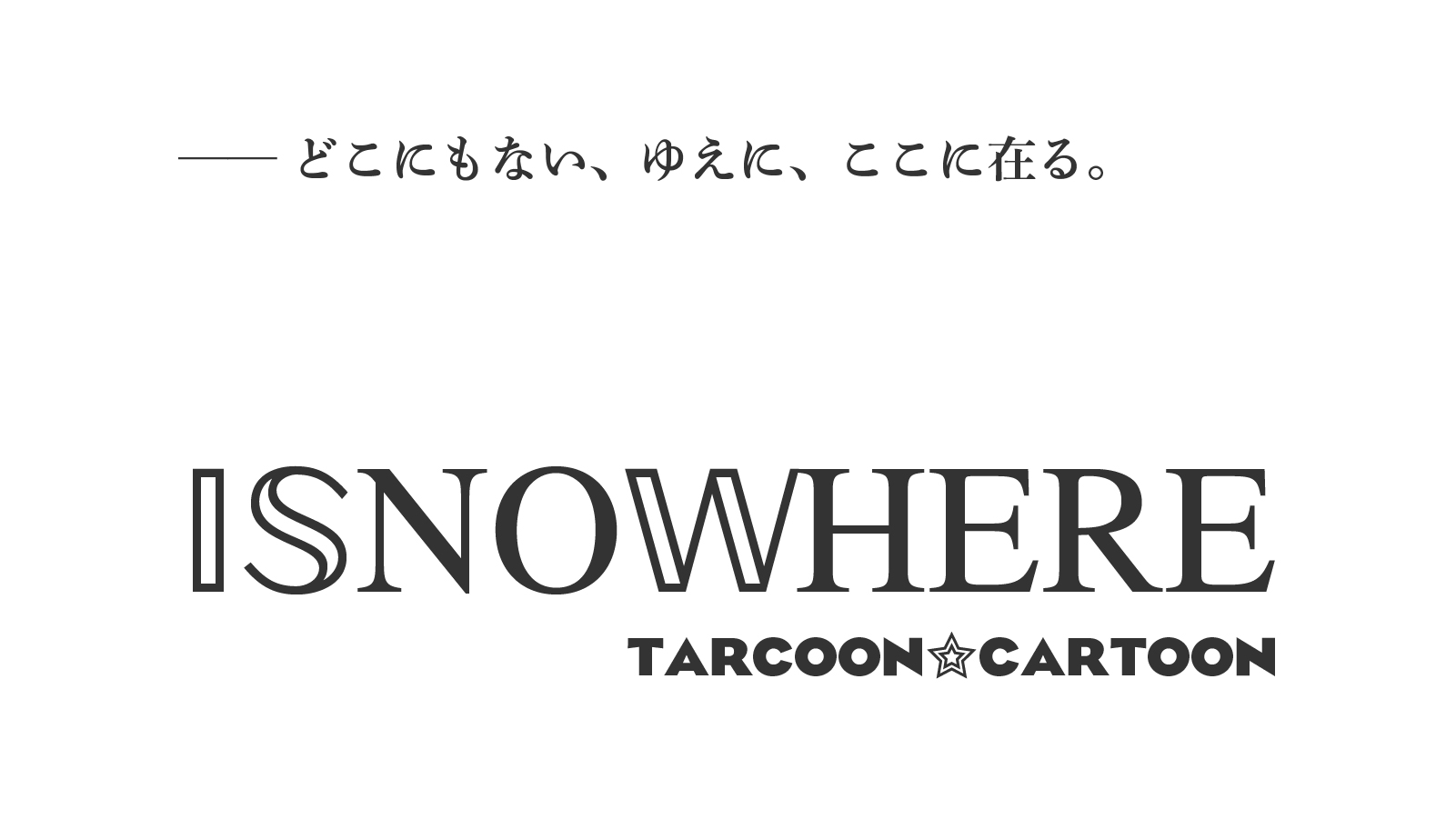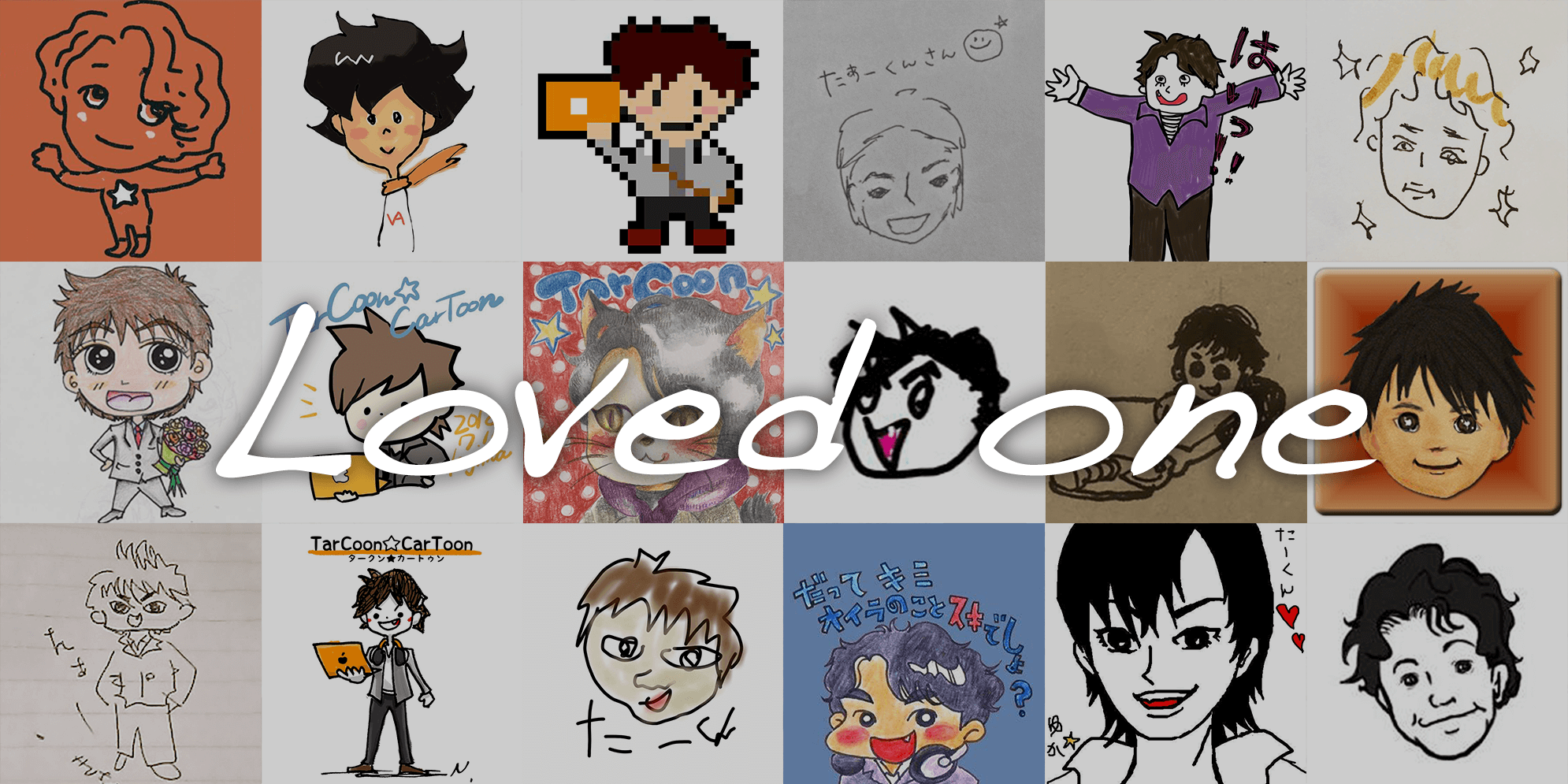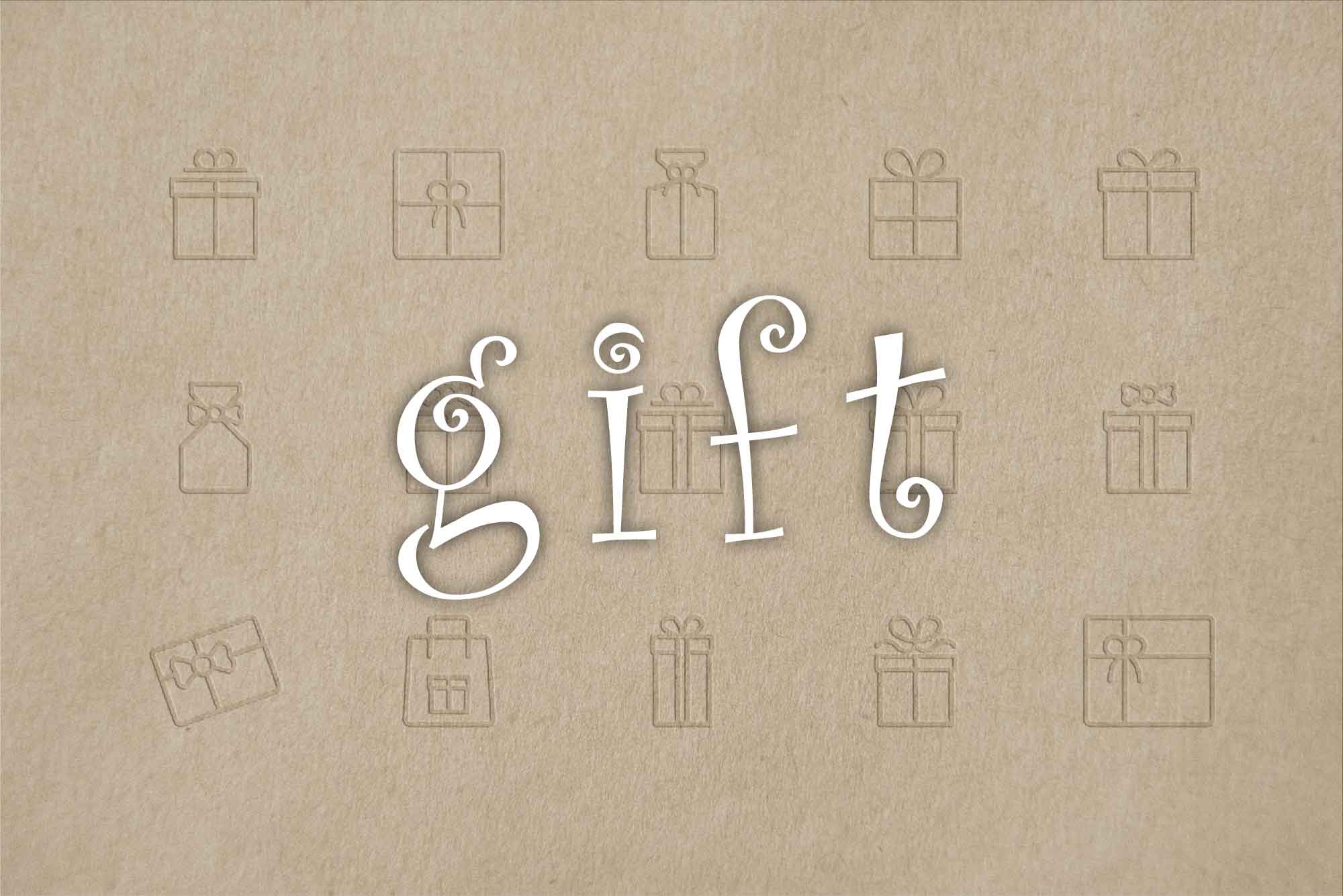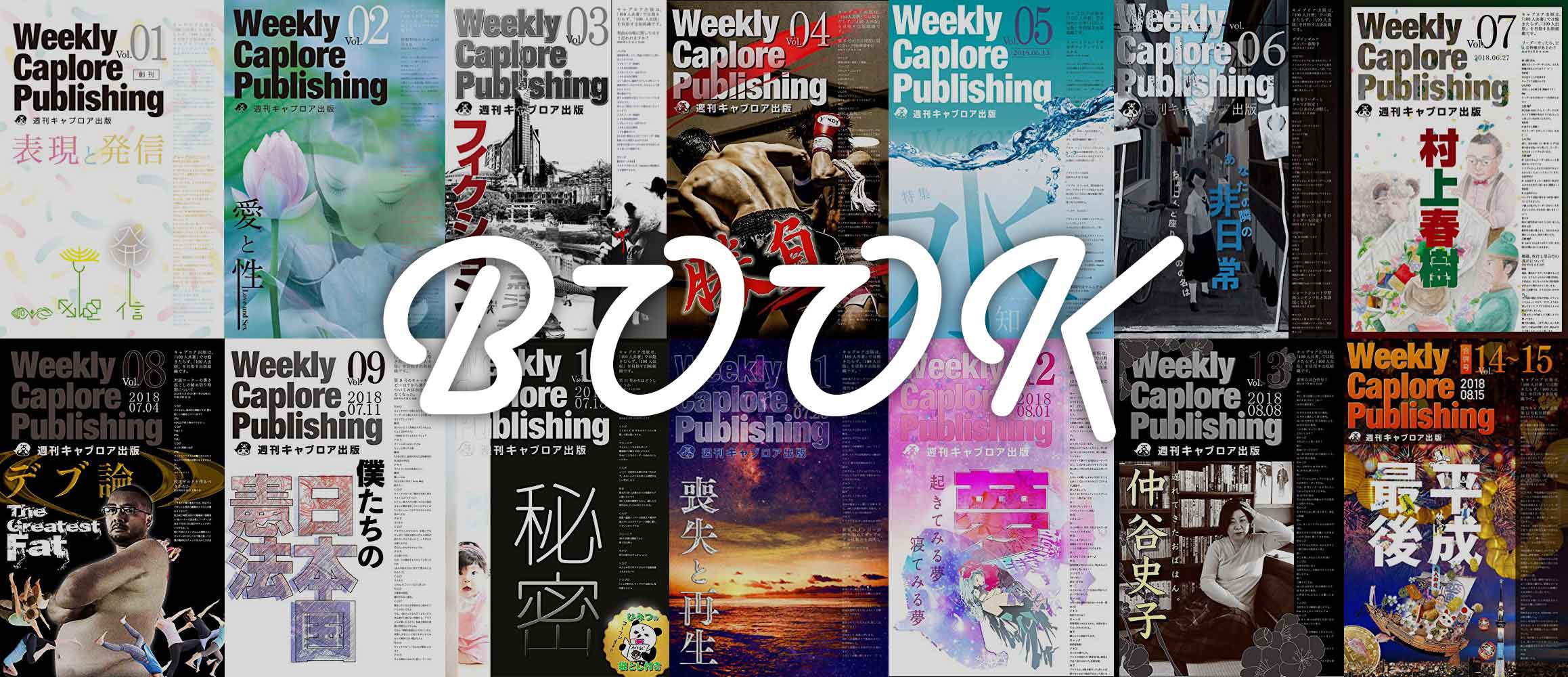友人に「読んでほしい」と渡された一本のテキストには、みんなに仲直りしてほしいという男の想いが綴られていた。──オイラが彼を友人だと思うのは、その優しさを感じるからだ。けれど、そこにはやはりかなりトンチンカンな行動が混ざってしまっている。指を詰めて送りつけるという振る舞いだ。
この文章の狙いは、界隈の私闘をいったん畳み、当事者を〈評議〉に招き、物語の重心を「痴話げんか」から「革命準備」へと移すことにあった。ならば、その意図に本当にふさわしいのは、どんな言葉であり、どんな行動だったのか。オイラが当てたいと思った言葉が、これからの応答文だ。
この記事は、アキノリ将軍未満(以下、ア将未)氏の note に掲載された
「〇九〇一諫言と同志諸君への訴え ~みんなそんなことより革命しない?~」への応答記事です。まずは元のテキストをお読みいただくことを強くおすすめします。そのうえで、ここから先の応答をご覧ください。
あわせて、今回の一連の騒動に触れたときの最初の感想も紹介します。
指を詰めるという演出──「男らしさ」と「誠意」の倒錯
— TarCoon☆CarToon (@TKMS_all4A) October 22, 2025
友人が指を詰めた。
理由を聞くと、「詫びを入れるなら指ぐらい詰めたらどうだ」と言われたからだという。
古い任侠的コードをなぞるような話だが、そこに感じたのは「男らしさ」ではなく、むしろ「女々しさ」であった。…
指を詰めるという演出──「男らしさ」と「誠意」の倒錯
友人が指を詰めた。
理由を聞くと、「詫びを入れるなら指ぐらい詰めたらどうだ」と言われたからだという。
古い任侠的コードをなぞるような話だが、そこに感じたのは「男らしさ」ではなく、むしろ「女々しさ」であった。
この行為は、誠意の表明というよりも、「詫び」という儀式を通じて他者を納得させようとする演出にすぎない。
つまり、詫びることそのものよりも、「詫びたことを見せる」ことに目的がすり替わっている。
それは、自己犠牲を演じることで他者の怒りを宥め、場の主導権を取り戻すための行為でもある。
本来の謝罪とは、自己の行為を内省し、関係の再構築を試みるものであるはずだが、ここでは暴力的な演出によって誠意を「演出する」自己保存の戦略となっている。
この構造は、いわゆる「弱者特権」や「被害者特権」を利用した言説と同型である。
本来、弱者であることや被害者であることは、その立場における痛みや葛藤を語るための出発点であるべきだ。
しかし、それが「免罪符」として振る舞い始めるとき、そこにあるのは倫理的な内省ではなく、他者を支配する新しい暴力である。
「詫び」を暴力の延長線上で行うことと、「被害」を盾に発言権を独占することは、構造的には似ている。
いずれも「正しさの演出」を通じて他者を沈黙させる点において、同じメカニズムで機能している。
だからこそ、この友人の行為は「男らしい」のではなく「女々しい」。
それは、主体的な覚悟ではなく、他者の期待に対する過剰適応であり、社会的コードへの従属にすぎない。
指を詰めることによって自分の誠意を「証明」しようとする姿は、むしろ自分の行為を言葉で引き受ける勇気の欠如を露呈している。
暴力を自己演出に転化し、痛みを記号化することでしか関係を保てない社会の哀しさが、そこにはある。
でもオイラは資本家でありスポンサーなので、寿司を贈る!
指は合図になるか、手順は言葉になれるか
これは、君に「読んでほしい」と渡された『〇九〇一諫言と同志諸君への訴え』への応答だ。オイラは君を友だちだと思っている。だからこそ、感情の渦の外側に半歩だけ立って、いま必要だと思う言葉を置いていく。ここでの目的は断罪でも礼賛でもない。どちらの陣営の肩も持たないまま、場を壊さずに前へ進むための作法をいったん見取り図として描き直すことだ。
まず、あの行為”指を詰める”が場に与える「効き方」から確認しておきたい。古い任侠のコードをなぞる身振りは、物語を一撃で反転させる。血は視線を奪い、喧噪を止める──そう信じたくなる。しかし、そうはならない。沈黙は生まれない。市ヶ谷駐屯地での三島由紀夫の檄が、自衛官たちの一斉の野次と、上空を旋回する報道ヘリのローター音にかき消されたように、劇的な呼びかけはしばしば静けさではなく雑音を増幅する。結果として、反論は乱れ、検証は拡散し、議題は宙吊りのまま漂う。静けさに見える一瞬は秩序ではない。合意の到来ではなく、ただの凍結だ。それは、言葉がただいま機能停止中であることを知らせる警告音に近い。沈黙を「勝利」と取り違えると、僕たちは議論を前に進める力を失う。沈黙は勝利ではない。ただの話し合いの停止にすぎない。
ここで、あえてあまりにも当たり前のことを言葉にしておく。いまの時代に指を詰めるのは、ふつうに“やり過ぎ”だと受け取る人が多数派だ。支持を得たいのであれば間違った判断だ。これは善悪の問題ではなく、受け止められ方の問題だ。痛みは視線を集めるが、同意は連れてこない。もし人が一瞬ついてくるとしても、それは短い同情であって、長くは続かない。せいぜい、保護本能を刺激された人びと──「可哀想な女の子や子どもを守らなきゃ」と感じた層──がしばらく寄ってくる程度だ。おっさんには寄ってくるわけがない。演出は開幕の合図にはなっても、舞台を最後まで支える筋書きにはならない。ここに、君の覚悟と世間の直感のズレがはっきり現れている。
もう一段踏み込む。謝罪とは本来、自分の過失を言葉で引き受け、関係を縫い直すための手順であるはずだ。ところが暴力的な演出が前面に出ると、手順は後景に退き、残るのは「詫びたことを見せる証拠写真」だけになる。SNSはその写真を拡散し、やがて「見せること」自体が目的にすり替わる。誠意の温度は、画像のコントラストに置き換わり、言葉の仕事は剥がれ落ちる。オイラたちが何度も繰り返してしまった最悪のパターンだ。
ここで危ういのは、痛みが免罪の通貨として機能してしまう点だ。本来、弱さや被害の経験は語られてよいし、そこからしか始まらない対話もある。けれど、その経験が他者を黙らせる装置として振る舞い出すとき、それは別種の暴力へと裏返る。痛みは免責の総量ではない。まして、主導権の買い戻しでもない。
では、いま何が要るのか。ここからが、オイラの結論だ。
今回の出来事とその余波を見渡して、オイラにはひとつの結論が浮かび上がった。革命に要るのは、演出ではなく手順、血ではなくルールだ。これは、君が実現しようとしていることに歩調を合わせて考えた末に得た、いまこの瞬間の結論である。そしてこの結論は、君とオイラが共に歩む勢力のあいだで共有すべき最低限の取り決めとして置かれるべきだ、と。
ここでいう手順/ルールは、高邁な理念のことではない。むしろ退屈なほど具体的で小さな作法の束だ。列挙してしまえば、拍子抜けするくらい簡素で、しかし肝心要のところだけが残る。
- 人格攻撃をやめる:相手の生活・身体・属性を消耗品にしない。批判は内容に限定する。
- 一次情報で確かめる:伝聞や切り抜きに寄りかからず、関係者の同意が得られる範囲で事実確認をする。
- 誤りは訂正する:撤回と謝罪のフォーマットを前もって定め、速やかに適用する。
- 役割を分ける:中立の進行役、要点を正確に残す記録係、検証のためのファクトチェック係を分担する。
- 時間を刻む:発言順と持ち時間、論点の〆切、見直しの期日を最初に置く。
- 公開範囲を合意する:議事録を全文公開するのか要約にするのか、どこまでを外に開くのかを事前に取り決める。
どれもヒロイズムからは遠い。だが、退屈に耐える力こそが結束の最低線だ。結束が「同じ痛みの共有」ではなく「同じルールへの同意」から立ち上がるのだとすれば、我々が鍛えるべきは昂揚ではなく、段取りを回し切る根気である。
ここで、君の檄が内包していた二つの強さをあらためて見ておきたい。
ひとつは、身体を担保に言葉の比重を増す強さ。もうひとつは、敵味方の双方に〈評議〉への参加を呼びかける包容の強さ。前者は注目を保証するが、同時に議題を上書きしがちだ。痛みが大きいほど、周囲は口を閉ざし、議論は止まる。後者──包容の強さ──を生かすなら、必要なのは開かれた誘いである。契約の鎖ではなく、のれんの布。強制ではなく、余白。誰もが出入りでき、他者の声が入り込むための意図的な未決定の領域だ。のれんには細かい約款は書かない。大書すべきは三語で足りる──寛容・自己抑制・不文律。
寛容は、相手の存在を先に許容すること。自己抑制は、こちらの火力を自分で絞ること。不文律は、紙に書かずとも共有される恥の感覚。どれも派手さはないが、場を壊さないための最低限の足場だ。紙の契約ではなく、日々のふるまいの癖に落とし込めることが大切だと思う。
では、そののれんを潜った先で、実務として何をするか。オイラの提案は単純で、標語にすれば「まず止める、次に確かめる、最後に決める」の三段だ。
- 止める─── 人格攻撃や当てこすり、外野からの揶揄を止める。
- 確かめる── 一次情報を突き合わせ、当事者が合意できる最低限の公開範囲を整える。
- 決める─── 議題を欲張らず、まずは三点だけに絞る。①対外発信の作法、②若手育成の役割分担、③相互批判のルール。この三点で合意をつくる。
小さく始めて、壊さない。壊れない場は派手ではないが、長く持つ。そして長く持つことが、運動にとっていちばんの希少資源なのだと、オイラは考える。
ここまで書いても、なおオイラは否定も肯定も保留する。オイラにできるのは、友だちとして見守ることだけだ。見守るとは放置ではない。演出ではなく手順を、血ではなくルールを、面倒くささごと何度でも差し出すことだ。君が呼びかけた〈評議〉は、約束ではなく招待として受け取る。鎖ではなく、出入り自由ののれん。ふらりと入ってこられる入り口があるだけで、人は争いを少しだけやめられる。
なぜなら、通るべき通路が整えば、人は自然にそこを通るからだ。通路がなければ、人は互いの庭を踏み荒らす。我々が今必要としているのは、供犠の舞台ではなく、通路の工事だ。コーンを立て、白線を引き、段差をならす。退屈だが、歩ける。歩ける場所からしか、対話は再開しない。
オイラは君の勇気を値切らない。けれど、その勇気を反応の高速道路ではなく、手順の側道へと迂回させたい。側道は遅く、地味で、景色も代わり映えがしない。だが、崩れない。崩れないものの上にしか、長い関係は組めない。言葉の信用を、我々は壊してはいけない。一回の供犠で簡単に上書きされないように。言葉は血の代用品ではない。言葉は合意の設計図になれる。オイラはその古くて新しい当たり前に、もう一度、箸を置きたい。
最後に、私的なしるしだけを書いておく。寿司を食おう。これは契約でも、約束でもない。のれんの端に括った小さな札のようなものだ。呼吸の合う夜、ふらりと潜る目印としてここに残す。イカでも、コハダでもいい。噛んでいるあいだ、言葉は少しだけ控えめになる。その沈黙は凍結ではなく、熟すための間だ。そこからまた次の段取りを考えよう。
問いをひとつだけ残して、この応答を閉じる。
正しさは誰の犠牲で担保されるべきか。それとも、公開された手順で担保されるべきか。
オイラは後者に賭けたい。結論は断じない。だが、方角は示す。演出ではなく手順、血ではなくルール。君がやろうとすることを本当に前へ進めるなら、我々のあいだで最初に共有すべき最低限の取り決めは、たぶんその一行から始まる。何度でもやり直せるように、手順を先に置く。ここからだ。
TarCoon☆CarToonより
この項目の表示は制限されます。この部分を閲覧できるのは、TarCoon☆NetWorkのメンバーに限られます。