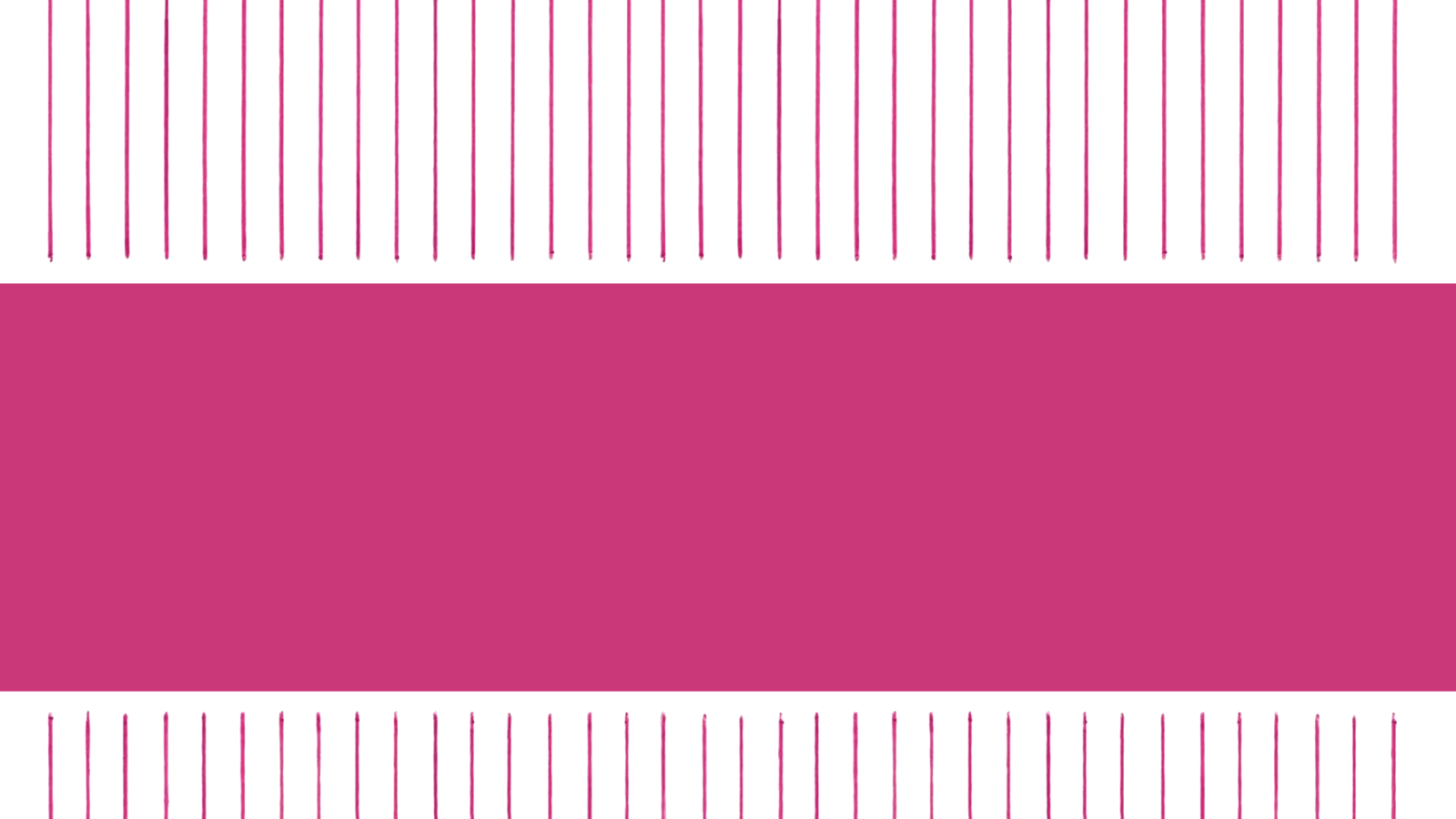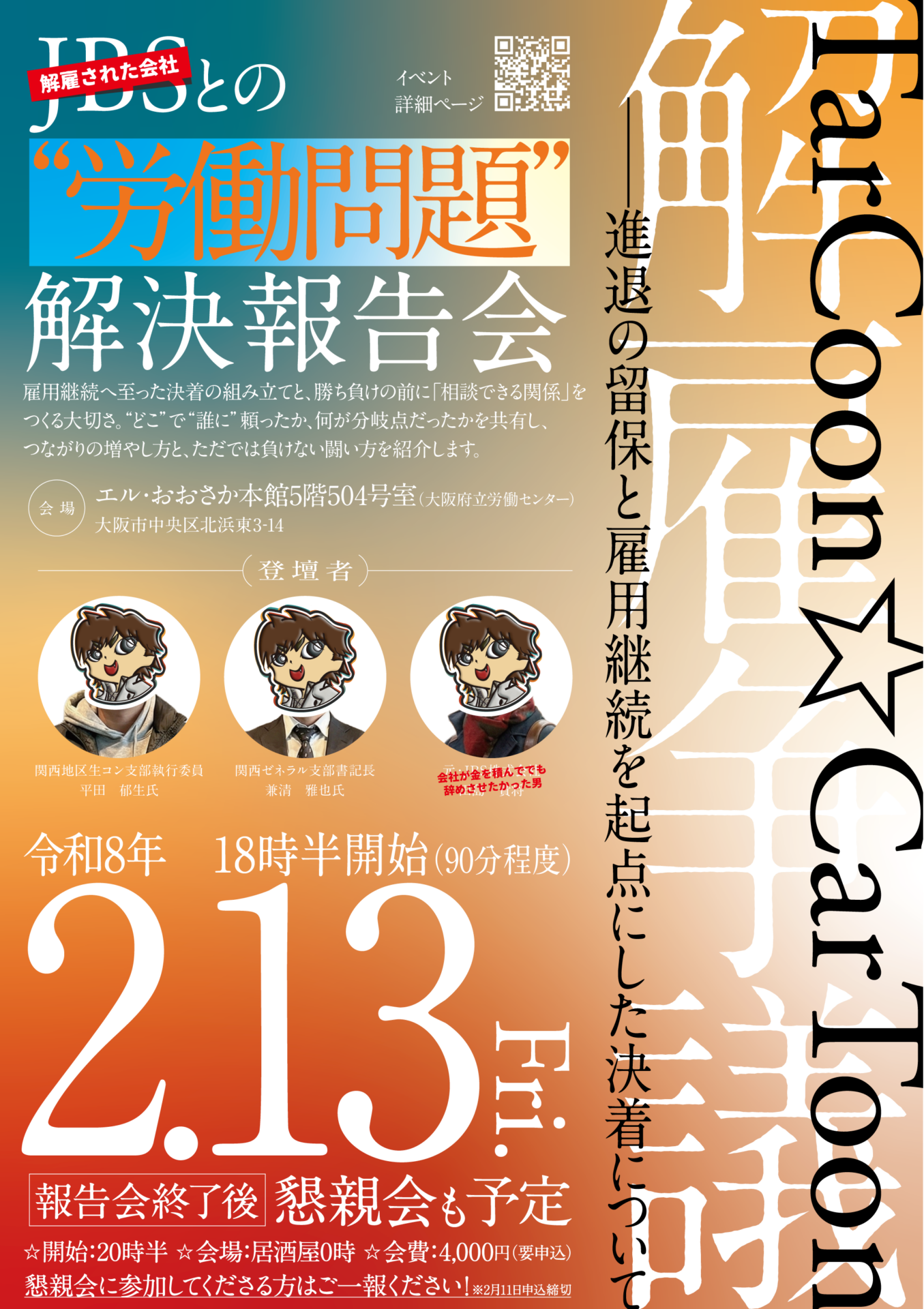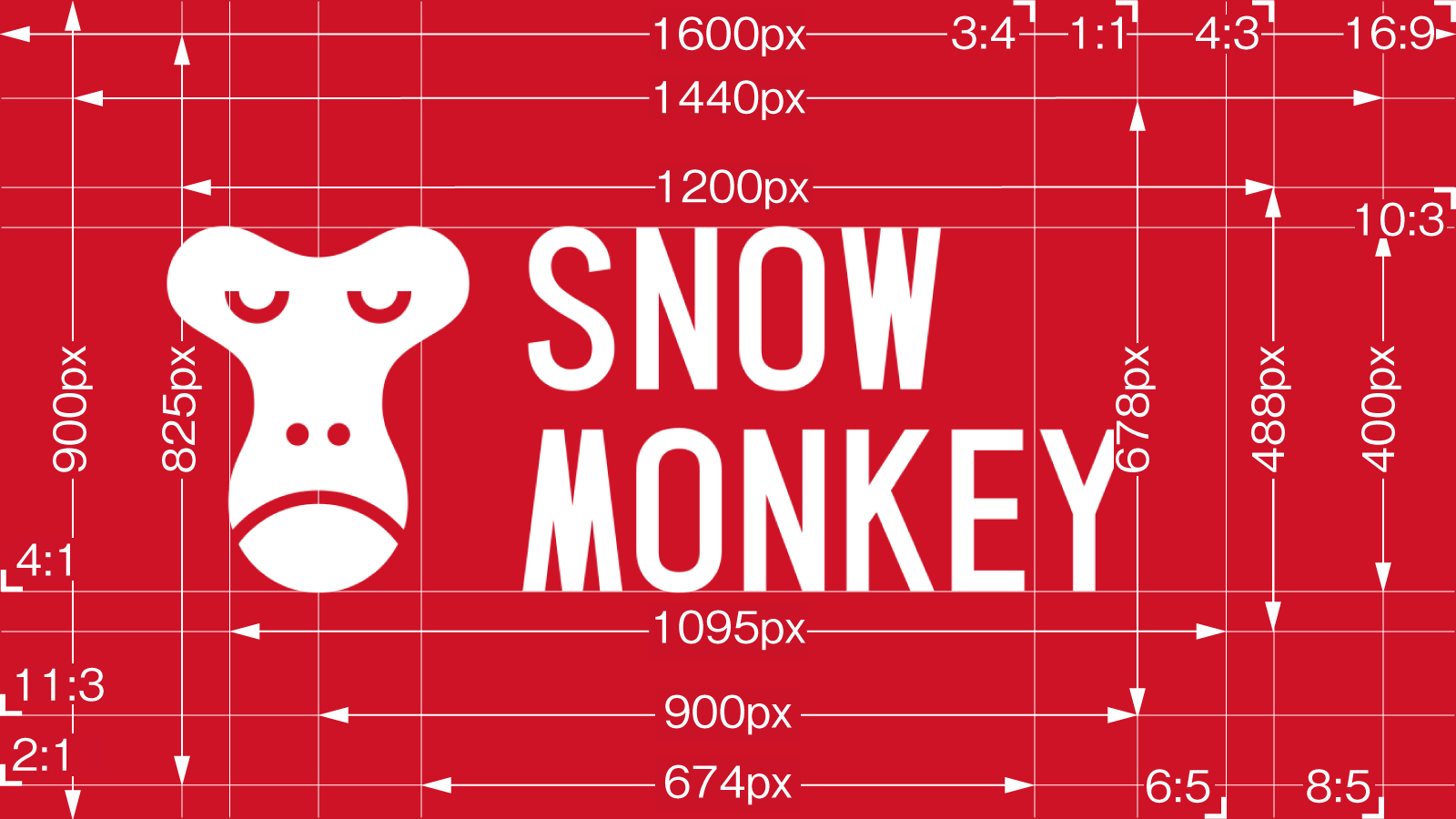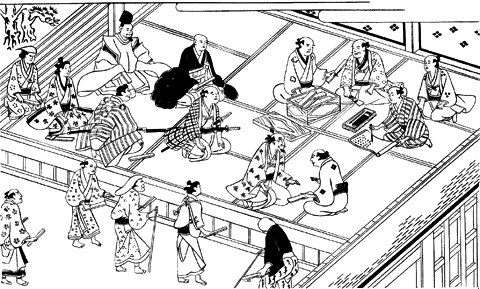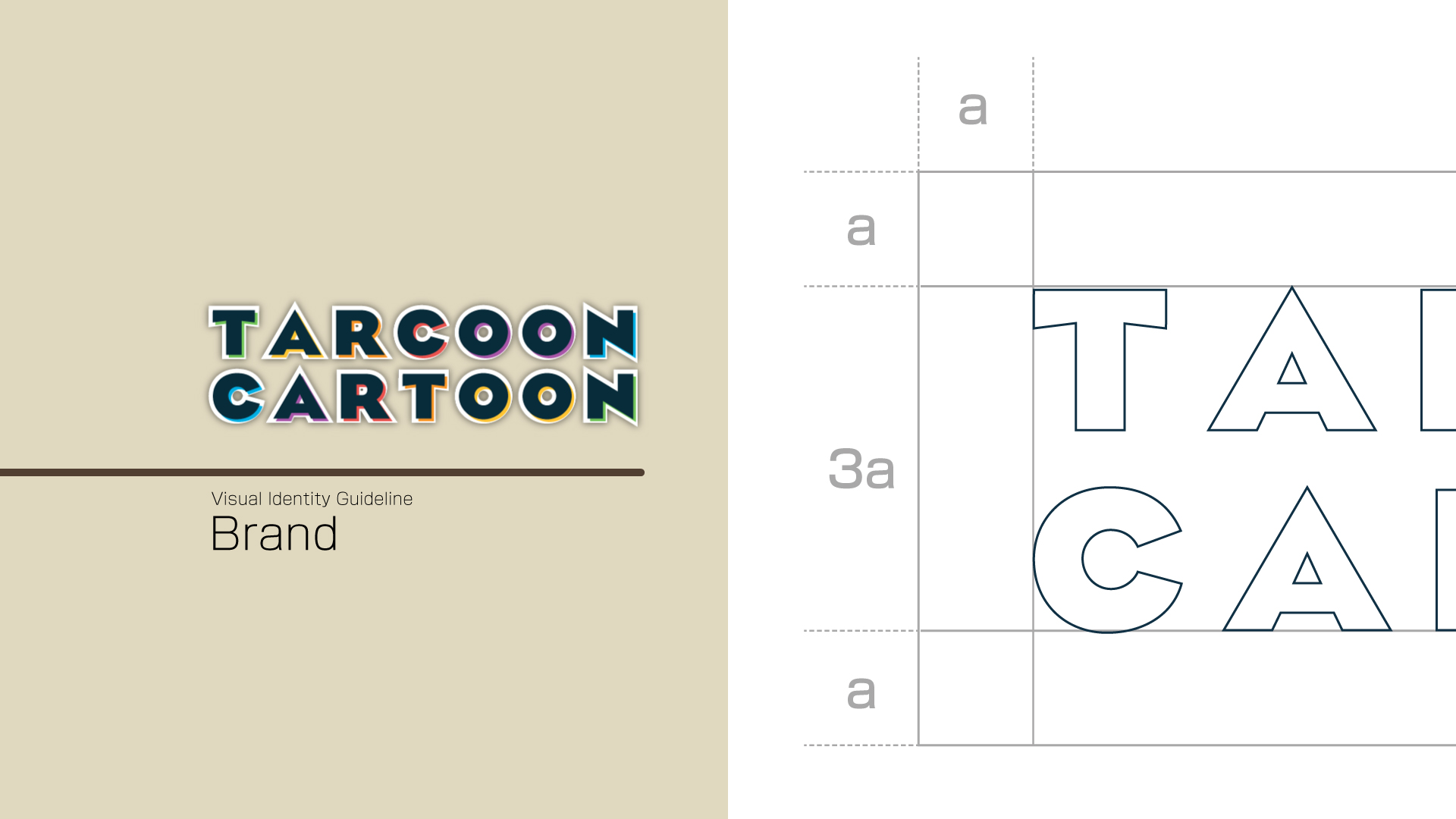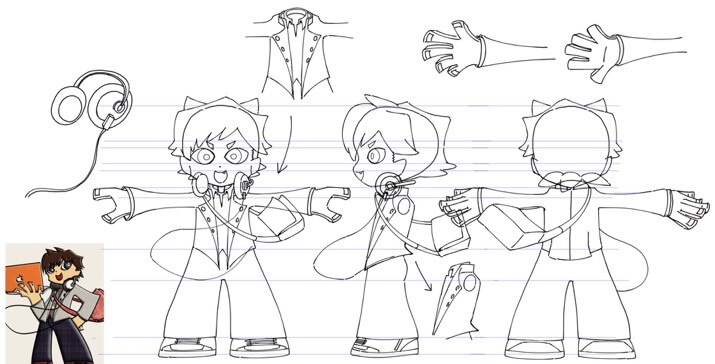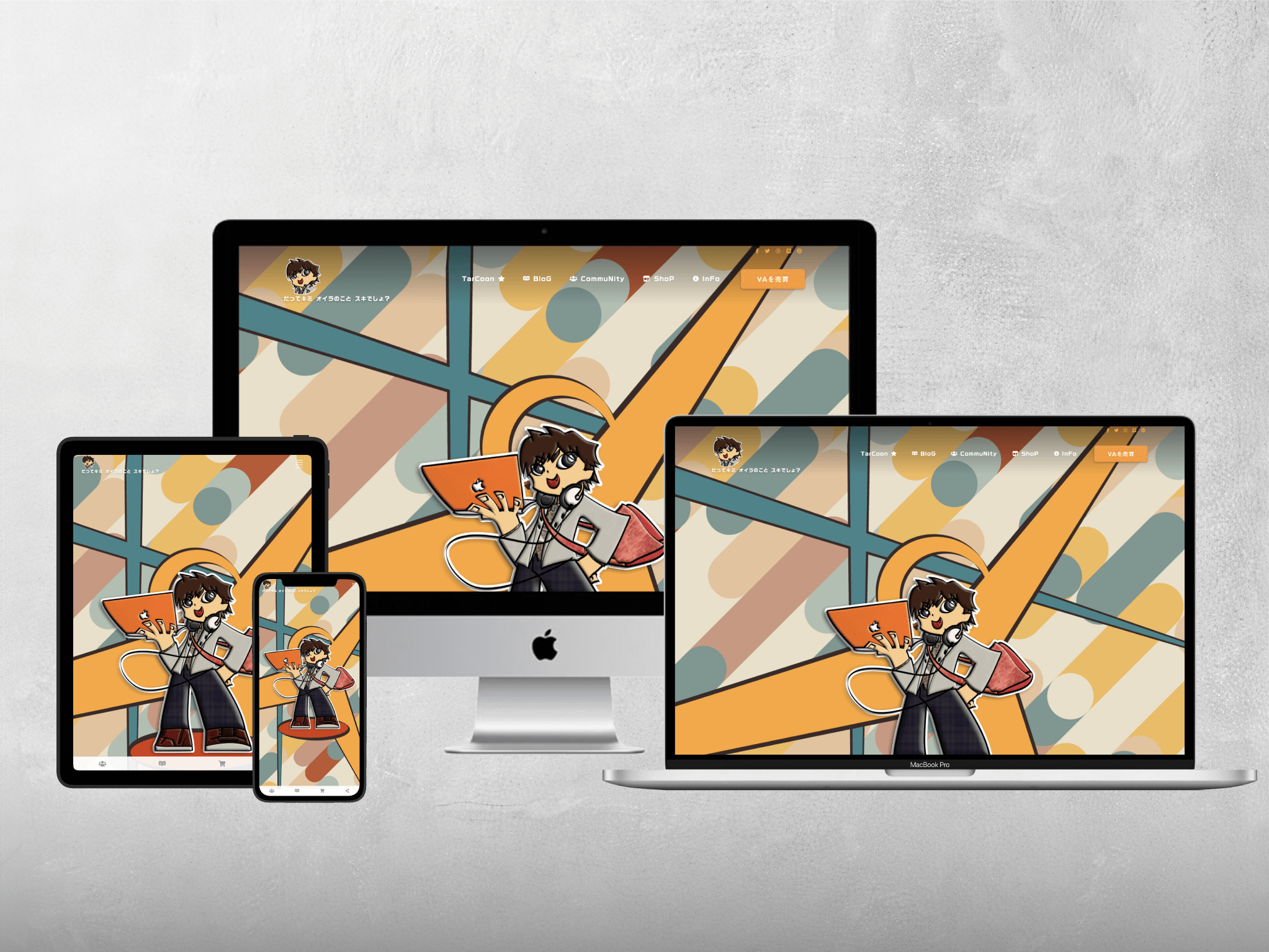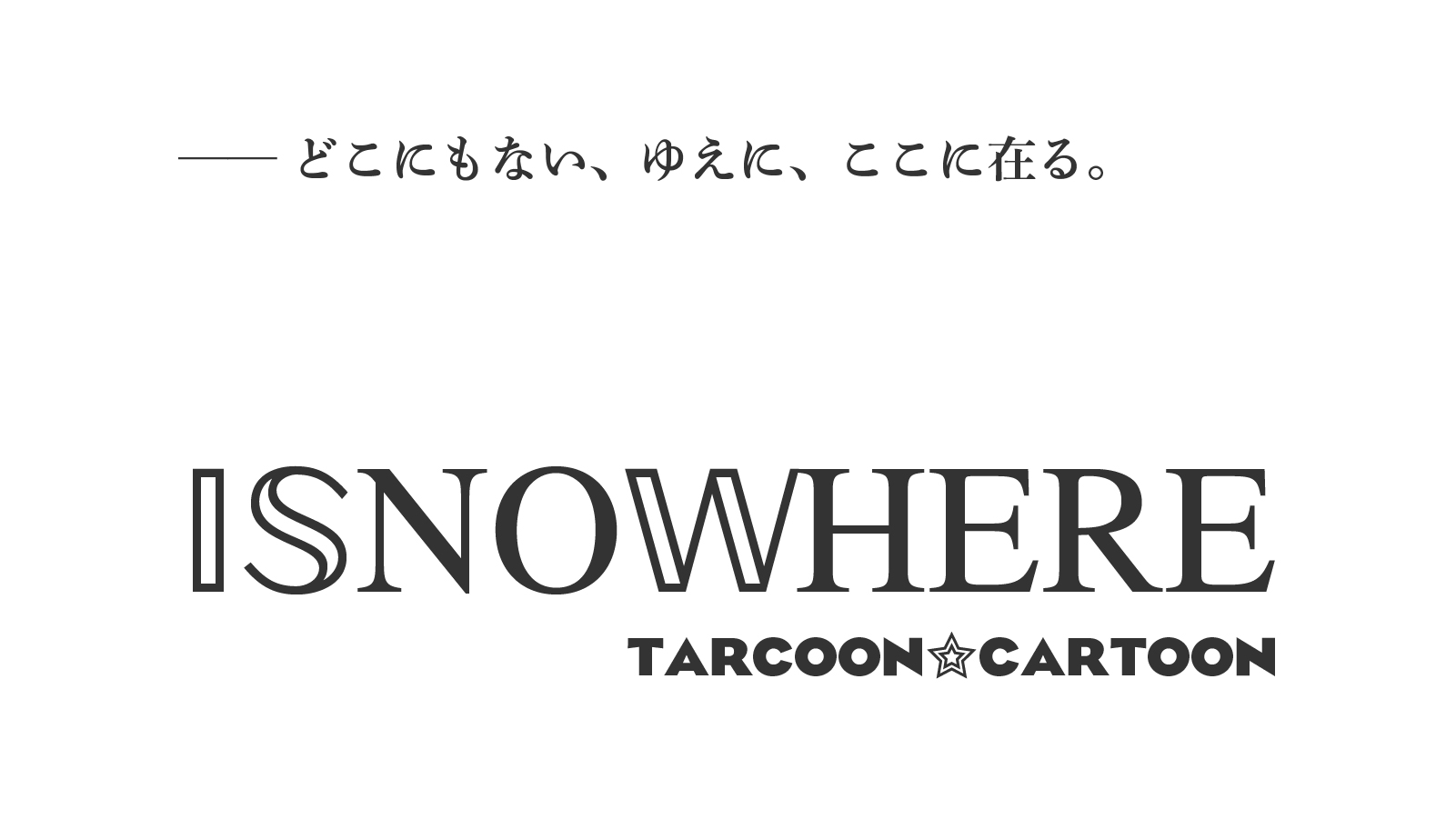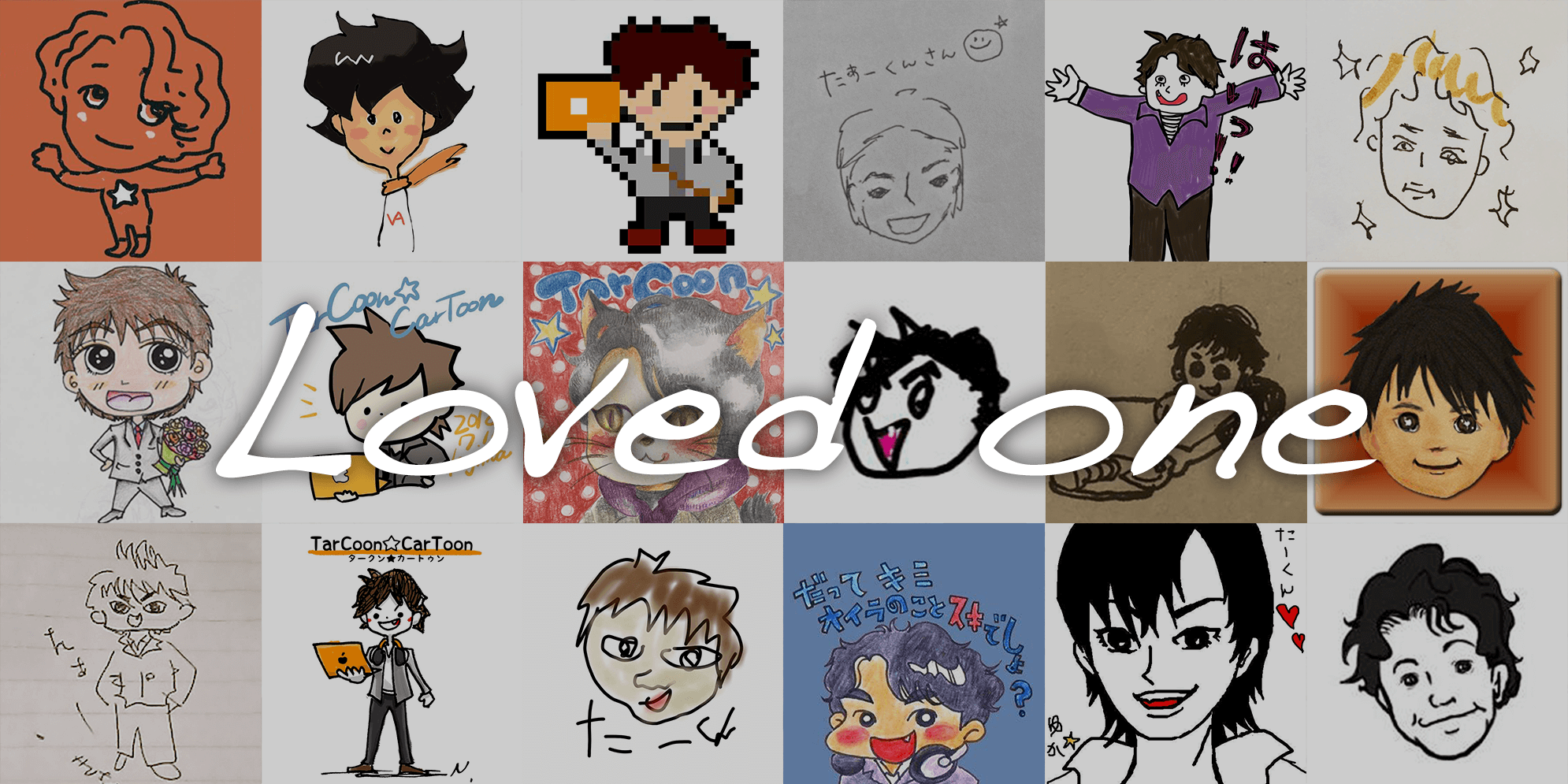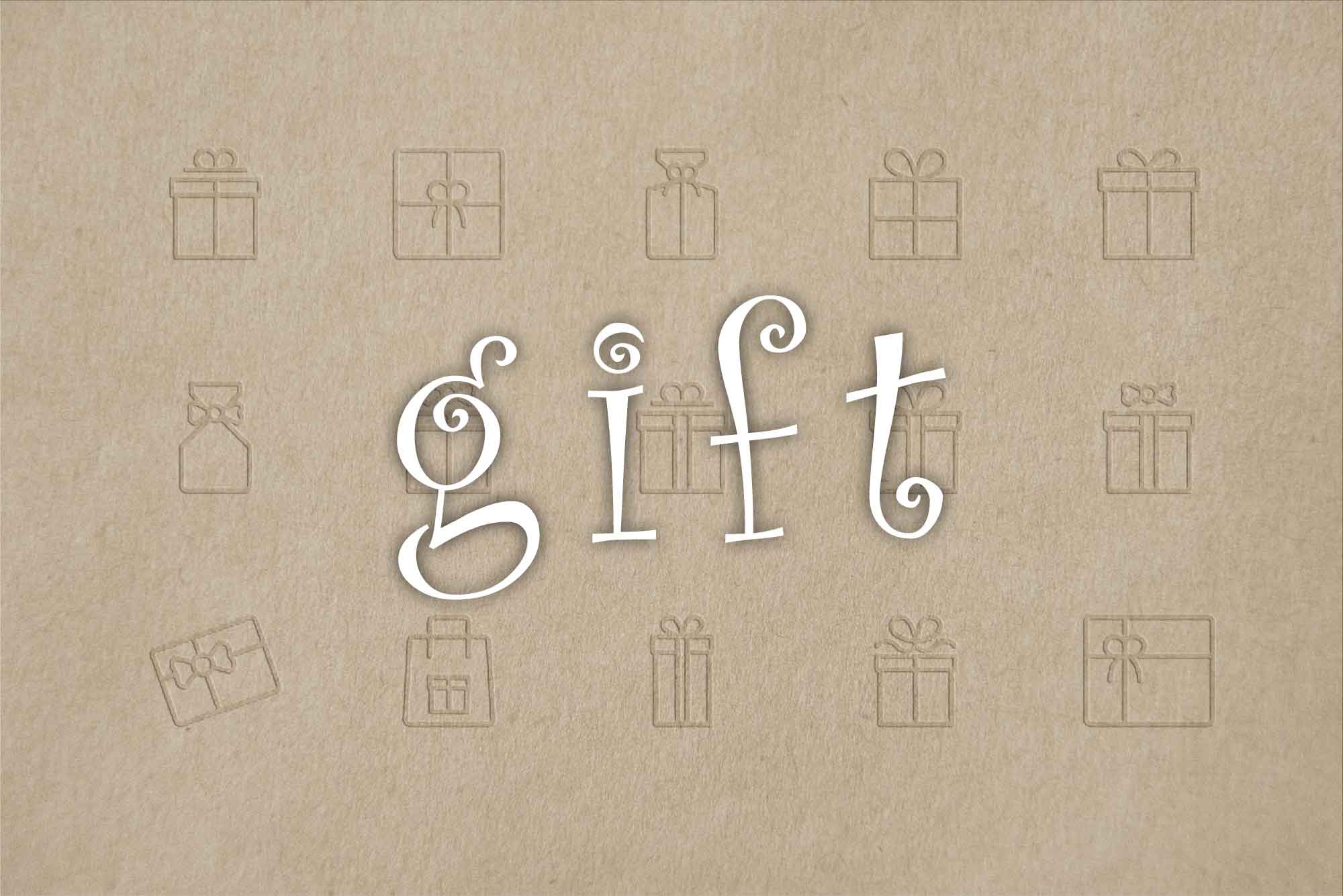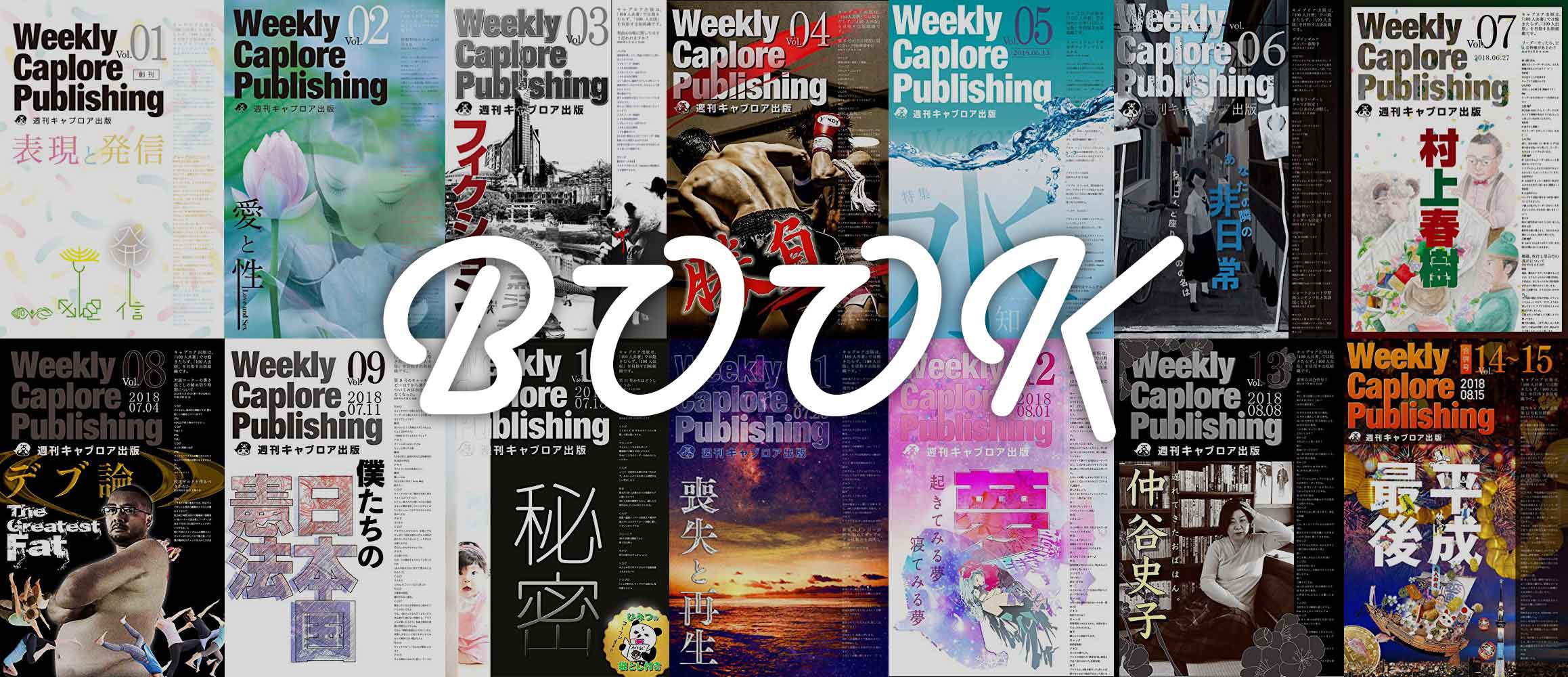「わかりあえるはず」という信念は、いつから「わかりあえないなら沈黙せよ」という圧力に変わったのだろう?SNSでの応酬、引用RTの連打、通知欄を埋め尽くすラッシュ──それは暴力にも見えるけれど、ひょっとすると“届かなかった善意”のかたちだったのかもしれない。ありがた迷惑、誤配、過剰な親切。うまく言えないまま、誰かにぶつかってしまった言葉には、思想の原風景が眠っている。
本記事では、電子文芸誌『ハツデン...!』6月号「思想」特集への寄稿をもとに、TarCoon☆CarToonとして「未完成な思想」「ズレと共鳴」「ラブラッシュと呼ばれる通知攻撃」などを手がかりに、現代における“思想の手触り”を問い直す。思想とは、正しさや整合性ではなく、“うまく伝わらないけれど、それでも関わりたい”という衝動にこそ宿るのではないか?
「思想とは、ありがた迷惑の別名である」──この仮説のもとに、わかりあえなさを生きる技術について、オイラなりに考えてみた。
本記事は、『ハツデン...!』への寄稿文「わかりあえなさの中で灯す──思想とは、ありがた迷惑の別名である。」を加筆・再構成したものです。ズレたまま語る勇気について、TarCoon☆CarToonとして綴りました。
「わかりあえなさの中で灯す」── それでも関わりたいという衝動にこそ思想は宿るのではないか?
— TarCoon☆CarToon (@TKMS_all4A) June 26, 2025
初田塾出版のZINE『ハツデン…!』7月号に寄稿しました!
今回は思想特集。是非読んで下さい!
→ 購入先:https://t.co/uKyv36ylZs
→ サイト:https://t.co/dP2OYlIPOG#ハツデン #初田塾出版 #Zine pic.twitter.com/XKAgWqhfxi
*本記事は、雑誌『ハツデン...!: 思想』内で、「わかりあえなさの中で灯す──思想とは、ありがた迷惑の別名である。」というタイトルで寄稿しています。こちらの本もお読みください。
わかりあえなさの中で灯す──思想とは、ありがた迷惑の別名である。
思想とは、本当に頭の中にあるだけのものなのか?
オイラは時々そう問いかけたくなる。いや、むしろ、言葉になる前の衝動や、相手を思ってついやってしまった“ありがた迷惑”のなかにこそ、思想の火種は眠っているのではないかと思っている。
たとえば、「イナゴ系」と呼ばれるネット上の人々。彼らのふるまいはしばしば「攻撃的」だとか「迷惑だ」と一括されてしまうけれど、そのすべてが悪意から生まれているとは、オイラには思えない。むしろそこには、不器用な善意──言葉にならない共鳴欲や、方向を間違えた親切心──がある。そしてその“ズレ”が、不和を生み、誤解を拡げ、炎上というかたちをとって表れる。でも、それは一種の「誤配された思想」じゃないか?つまり、うまく言えなかっただけで、そこには「伝えたい」がちゃんとあったんじゃないかって。
この視点で捉え直すとき、オイラはある雑誌の名前を思い出す。
その名も『ハツデン!』。発行しているのは、電子書籍出版グループ「初田塾出版」。そして、その代表を務めるのが初田龍胡という人物だ。彼が掲げるのは、知の敷居を下げ、思想や表現の“初期衝動”を肯定する場づくり。名の通り、『ハツデン!』は「初(ハツ)=未熟さ」と「発電=言葉のエネルギー」を掛けあわせたような雑誌であり、完成された思想よりも、むしろ未完成で不格好な言葉たちこそ、歓迎してくれる。だからこそ、この雑誌には思想というテーマがふさわしい。
思想は、頭の中だけじゃなく、行き場のない善意や、ズレた感情にも宿る。
そして、誰かのありがた迷惑すら──その距離の失敗すら──オイラにとっては、思想のひとつのあり方に見えるのだ。
ハツデン!という未完成な言葉の居場所
『ハツデン!』という誌面は、ただの電子文芸誌ではない。そこには明らかに、「発電(=思考の始動)」というメタファーが重ねられている。
発電とは、摩擦や熱を伴うものだ。予定調和からではなく、誤差や揺れ、未熟さといった“扱いにくいエネルギー”がなければ、決して始まらない。だからこそ、思想もまた、整った言葉や明晰な理論としてではなく、もっと不器用で、もっと予測不能な感情の中からしか立ち上がらないのだと思う。
『ハツデン!』が目指すべき誌面とは、まさにこの“始まりの衝動”に対して寛容であること。思想を「完成された体系」ではなく、「言葉になる以前の気配」として迎え入れる場所。
そのためには、表現の拙さや語りの不安定さ、そして「どうにも噛み合わない感情」こそを、思想の兆しとして捉える必要がある。
たとえば、「イナゴ系」と呼ばれる行動──SNS上での粘着的ふるまいや誤解を生む言動──も、あれは一種の「未完成な思想」なのだとオイラは見ている。
「自分の言葉ではうまく言えないけど、何かが間違ってる気がする」──そんな漠然とした違和感に突き動かされるかたちで、彼らは動く。結果的にそれが攻撃に見えたとしても、そこには確かに“問い”がある。問いの形をした悲鳴かもしれないし、拙い助け舟かもしれない。
たとえば、ネット空間でしばしば見られる「通知攻撃」も、そのひとつだ。
引用RTやメンションを何度も繰り返し、相手の通知欄を埋め尽くすあの行為。
多くの場合、それは「議論」ではなく、「強制的な承認の欲望」としてあらわれる。けれど、その背後には「どうしても見てほしい」「この言葉を受け取ってほしい」という、歪な共鳴欲があるように思えてならない。
通知攻撃は、他者との関係を“築く”のではなく、“即時に成立させようとする”。その拙速さが暴力的に見えるのは確かだ。でも、うまく伝えられなかった思想が、かたちを変えて爆発してしまっただけかもしれない。
やり方は間違っている。でも、その衝動の根っこには、やはり思想の火種が眠っている。
思想とは、本来、そういうものだったのではないか?
論理的整合性や倫理的正しさの前に、わかりあえなさを抱えたまま、それでも関わり続けようとする姿勢。その姿勢こそが、思想を思想たらしめる。
つまり、「わかりあえなさ」から目を逸らさず、それを受け入れる勇気がなければ、本当の意味での思想は育たない。
『ハツデン!』の誌面は、この「わかりあえなさ」を恐れない場所であってほしい。
感情が衝突し、言葉がうまく届かず、誤解が誤配を呼ぶ──そんな“うまくいかなさ”の中にこそ、思想は息をしている。
思想とは、同意の言葉ではない。むしろ、ズレのままでそこに立ち続けようとする意思だ。
『ハツデン!』は、そのズレを、ただの失敗ではなく、発電の火種として受け止める誌面であるべきだと思う。
わかりあえなさから思想は生まれる
オイラ自身、「イナゴ系」と言われる人たちから、これまで直接的な“被害”を受けたことはない。それどころか、彼らのふるまいのなかに、どこか切実なものを感じている。たとえば、人恋しさ。誰かとつながりたいという衝動。あるいは、「どうにかして伝えたい」という不器用な表現欲。そうした想いが、結果として届き方を間違えてしまい、誤解や衝突を生んでしまう──オイラには、それがまるで“一方通行の祈り”のように見えるのだ。その祈りは時に、お節介として届く。ありがた迷惑として拒まれる。だけど、だからといって、それを「思想ではない」と切り捨てることは、果たして正しい態度なのだろうか?
思想とは、本来もっと粗いものだと思う。整えられた制度や、整合性のとれた主張として現れる前に、もっと揺れた状態──感情に駆られ、衝動に突き動かされ、誰かにぶつかってしまう、その瞬間にこそ宿る火種ではないか。むしろ、その「ズレ」こそが、思想を思想たらしめる条件ではないか?
オイラが見たいのは、正しさに回収される以前の、生の思想だ。それは、感情のこじれや、言い間違い、タイミングのズレ、沈黙といったかたちで現れる。たとえば、ありがた迷惑──それは、他者のためを思ってやったことが、うまく伝わらず、拒絶されてしまう行為だ。けれど、そこには「自分を越えて、誰かに届こうとした」倫理的な跳躍がある。この跳躍は、決してスマートではない。しかし、倫理とはそもそも、きれいに整った関係性のなかには宿らない。むしろ、ズレているからこそ、そこに応答の余地が生まれる。思想とは、この応答の余白を開き続けるための態度なのではないかと思う。
『ハツデン!』という場が大切にしてほしいのは、まさにこの「ズレた跳躍」に宿る倫理だ。正論でも、整った美辞麗句でもない、不出来な表現。伝わらない善意。届かない優しさ。そうした“うまくいかなさ”を、切り捨てるのではなく、「思想の未完成なかたち」として迎え入れる誌面であってほしい。ありがた迷惑という言葉には、たしかに迷惑のニュアンスがある。けれどそれは同時に、「ありがたかったかもしれない」という可能性を、どこかに残している。その余白、その矛盾こそが、思想を生む。完成された正しさよりも、ズレを抱えたまま、それでも関わり続けようとする行為にこそ、思想は宿るのだ。そして、『ハツデン!』は、そういう思想の“発電所”であってほしい。
ズレを思想に変える技術
思想とは、誰かと完全にわかり合うことでもなければ、合意を勝ち取ることでもない。むしろ、ズレをズレとして引き受け、それに耐えながら、なおも関係を手放さない──そんな粘りの姿勢にこそ、思想の本領があるとオイラは思っている。意見を一致させるのではなく、ズレたままでそこに居続けること。それは簡単なことじゃない。説明しきれない感情、言語化しきれない価値観、共通前提の喪失──そうした“不通”の中に留まり続けることは、時に不安で、時に滑稽で、時に孤独だ。けれど、思想をほんとうに必要とするのは、そういう瞬間なのだ。
TarCoon☆CarToonとして、オイラがトリックスターの役割を担うのは、整合性を示すためではない。正しさの代理人になることも、答えを提示することもオイラの仕事じゃない。むしろ、ズレや誤解、失敗や混乱──そうした未整理な現場に入り込み、そこに「言葉にならない何か」を灯して回ること。それが、オイラの思想的実践だ。
イナゴ系がしばしば破壊してしまうのは、「わかり合えるはずだ」という幻想だ。そしてその破壊が、敵意として、攻撃として、ネット空間に現れることもある。だけどその一方で、オイラはこうも思う──「わかり合えなさ」の告白にこそ、思想の深度がある、と。
『ハツデン!』という誌面がもし、「語ることの不確かさ」や「共有されない感情」に耐えうる場所になるなら、それは思想の生態系にとって、とても重要な実験場になる。そこでは、誰もが「語るに足る未完成」を持ち寄り、「わからなさ」を開き続けることができる。思想は、閉じることで固まる。そして固まった思想は、やがてエコーチェンバーのように、自分たちだけの正しさに耽溺していく。でも、『ハツデン!』がやってほしいのは、そうじゃない。「わかり合えないかもしれないけれど、それでも語る」──その姿勢こそが、閉じた空間をゆるやかに解きほぐし、ズレを通じて思考を撹拌していく。
オイラがこの文章でやりたいのも、まさにそれだ。ズレを笑い、誤解を面白がり、未完成を語る。
TarCoon☆CarToonというトリックスターは、そういう「うまくいかなさ」に寄り添いながら、思想の火種を持って歩く存在だ。正しさの中心に立つことはない。けれど、周囲に漂う声なき声を拾い上げ、そこに言葉を添えていく。思想とは、時にそうした道化の手つきでしか、現れないことがある。
ズレを恐れるな。
ズレを生きろ。
思想とは、そのゆらぎを面白がる力なのだから。
あなたはズレを抱えられるか?
最後にもう一度、はっきりと言っておきたい。
ありがた迷惑には、思想がある。それは、自己の枠を越えて、誰かに干渉しようとする行為。相手にとって嬉しいかどうかはわからない。けれど、それでも関わりたい──そんな思いが、ズレたかたちで表れてしまうことがある。その不器用さを、「失敗」として切り捨てるのではなく、「思想のかけら」として受けとめたい。オイラはそう思っている。
たとえば、ネットでよく問題視される“通知攻撃”。メンションや引用RTを連投して相手の通知欄を埋め尽くすあの行為。多くの人がそれを「暴力的」「迷惑行為」と見なすけれど、オイラはちょっと違う名前で呼んでいる。「ラブラッシュ」──そう、これは一種の“愛の洪水”なんじゃないかと。もちろん、受け取り手によっては苦しいものにもなる。だが、送り手は往々にして本気なのだ。「見てほしい」「伝えたい」「届いてほしい」。その衝動が高まりすぎて、言葉がぶつかってしまう。ラブラッシュとは、コントロールを失った愛情のかたち。思想が未完成なまま、ただ“関わりたい”というエネルギーだけが先行したときに、言葉が加速し、通知となって噴き出す。それは迷惑かもしれない。けれど、オイラにはときどき、うれしくもある。だって、こんなにも“オイラに関心がある”ってことじゃないか。それって、もしかすると、ものすごく誤配された思想のかたちなんじゃないかって。思想とは、整った主義主張ではなく、通じなさの中からにじみ出る何か──それが「ありがた迷惑」や「ラブラッシュ」というかたちをとることがある。そのとき、わたしたちに求められるのは、「何が正しいか」を判断することではなく、その衝動をどう受け取るかを選ぶ自由なのだ。「うるさいな」と思えば、それは攻撃に見える。「必死に伝えようとしてるんだな」と思えば、それは愛にすらなる。思想とは、伝え方の問題であると同時に、受け取り方の問題でもある。
『ハツデン!』は、そうした“受け取り方の技術”を耕す場所でもあってほしい。ラブラッシュすら思想として受けとめられるような、大きな土壌を。だから最後に、オイラからあなたに問いかけたい。
あなたは、ズレたまま、誰かと居られますか?
うまく伝わらない気持ちを、そのまま抱えていられますか?
ありがた迷惑を、思想として受けとる勇気を持っていますか?
思想とは、きっとその問いを引き受けるところから、はじまる。
(この記事は2025年5月11日に執筆したものです。)