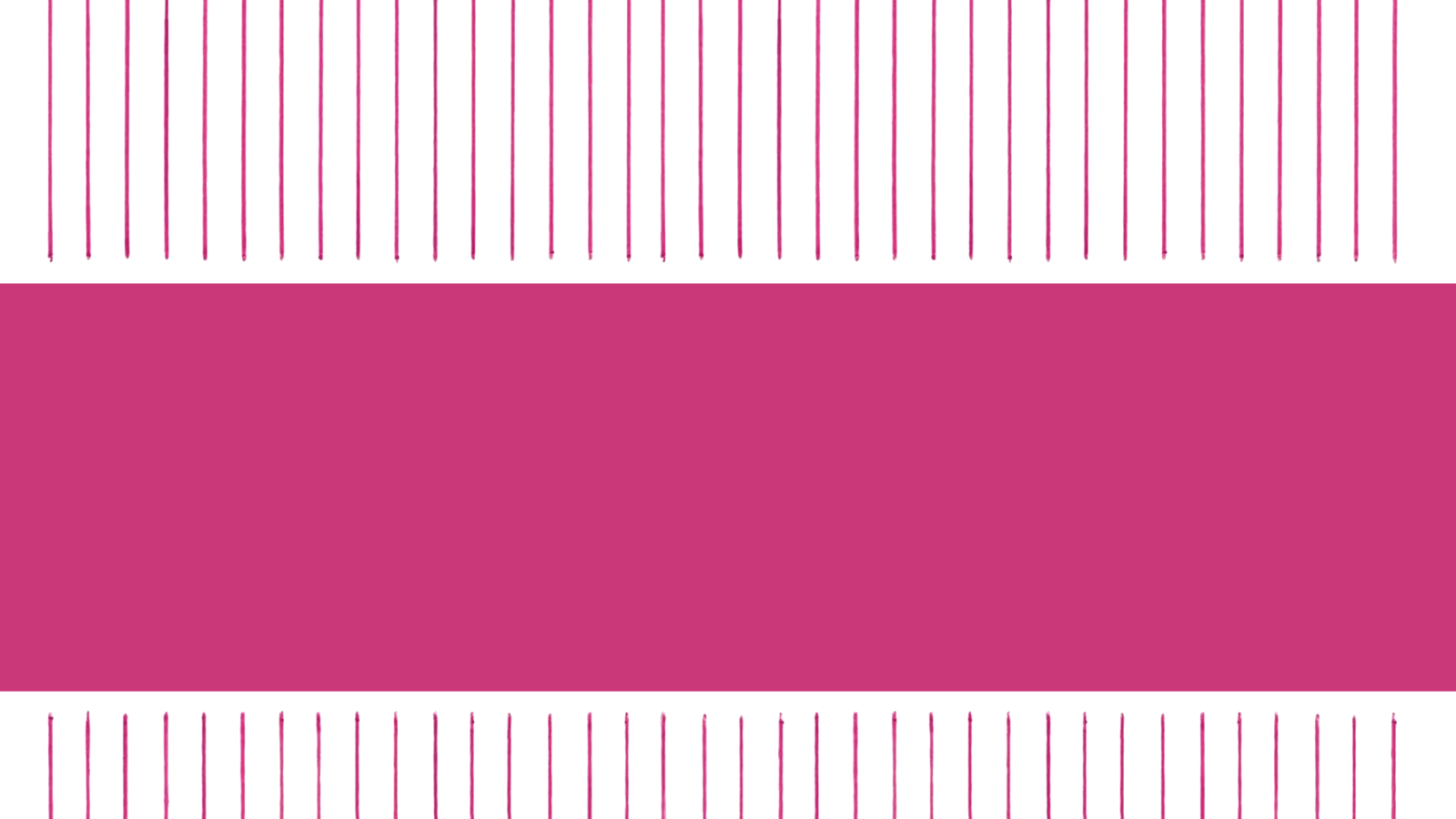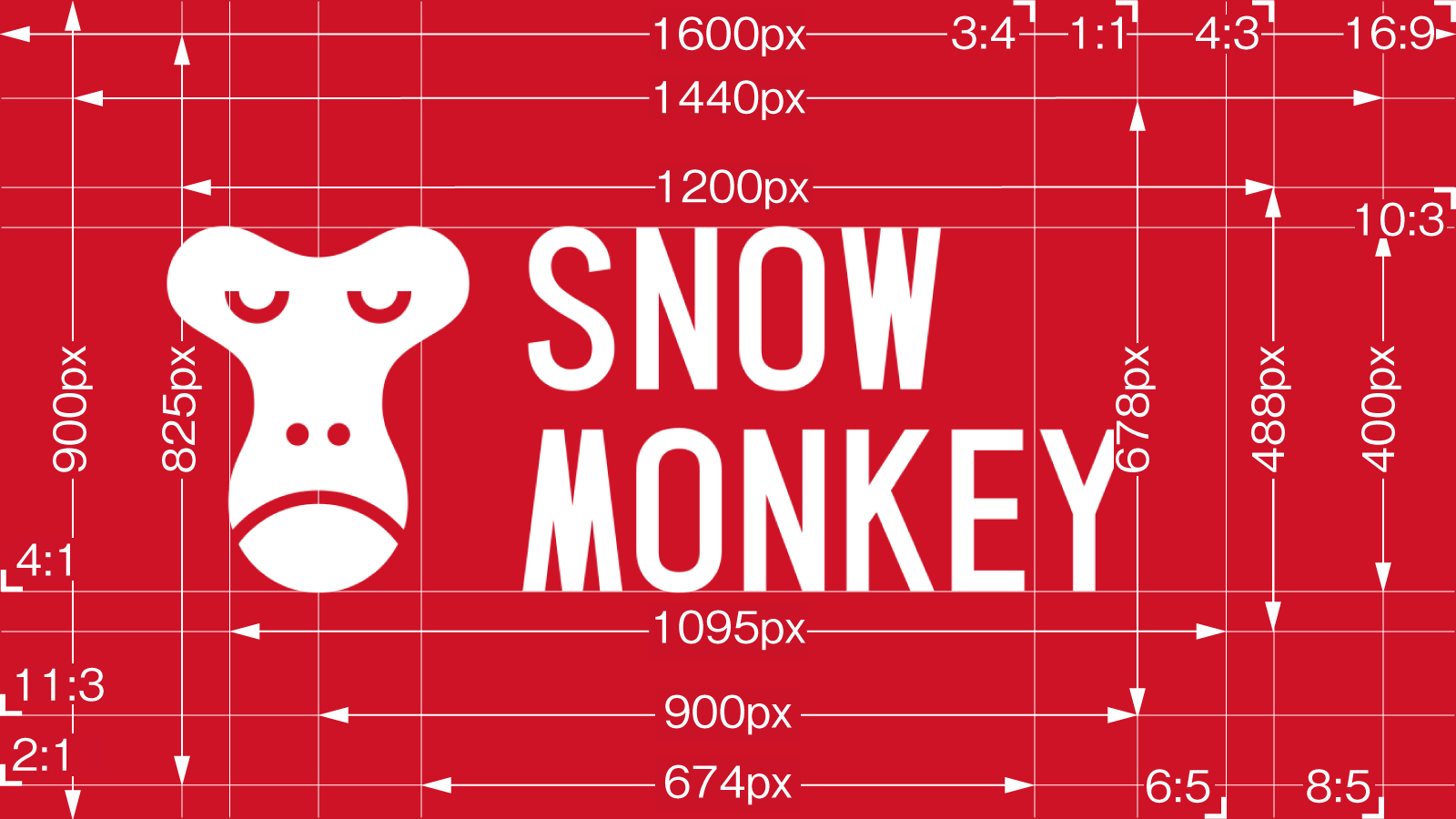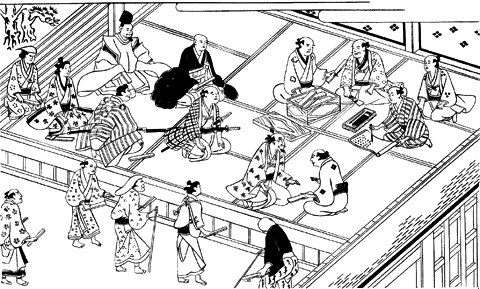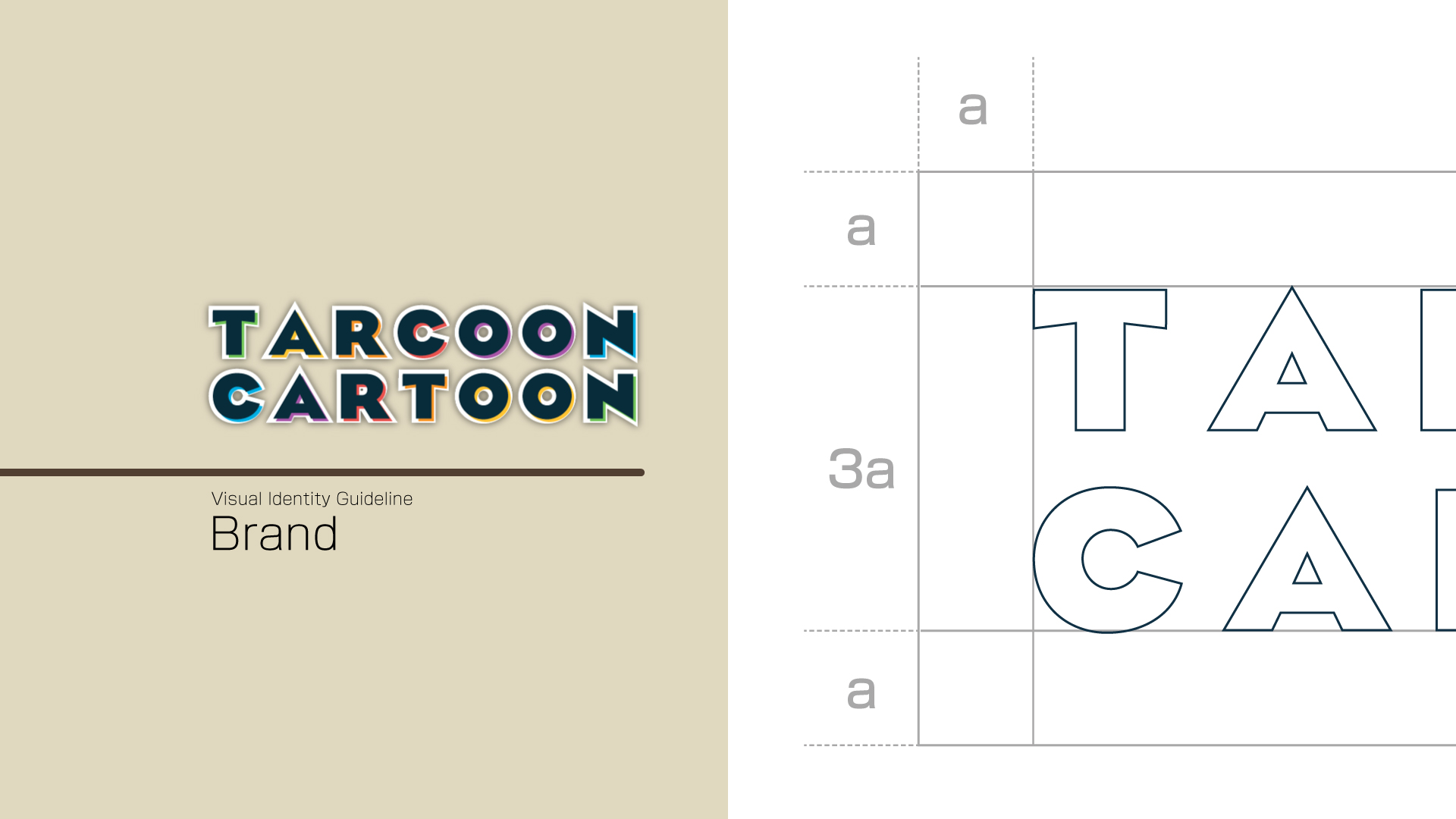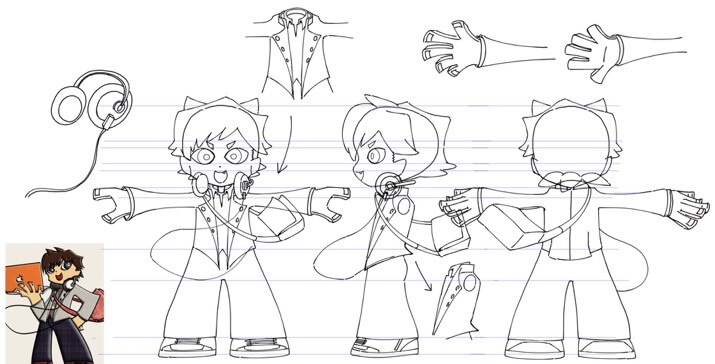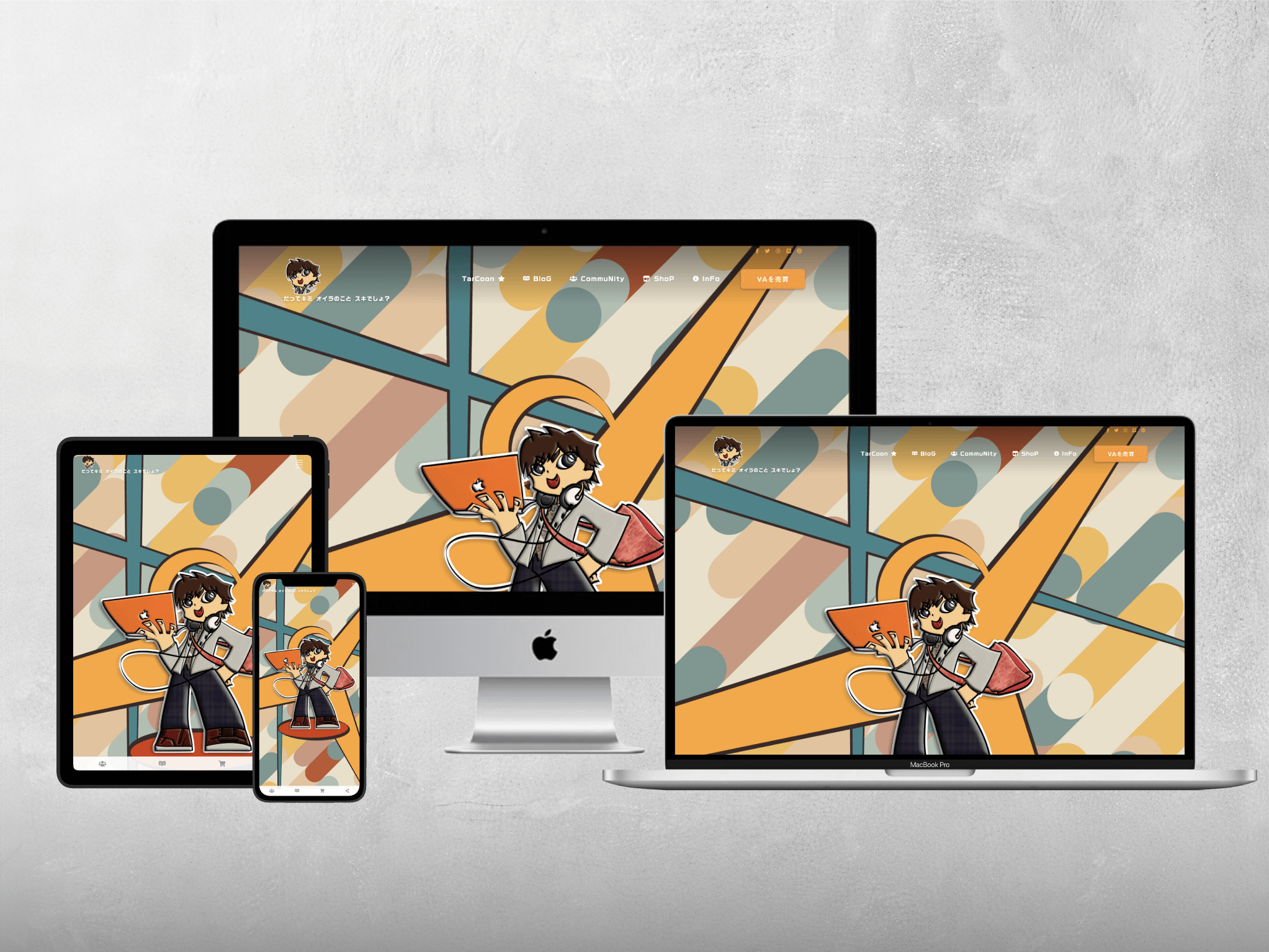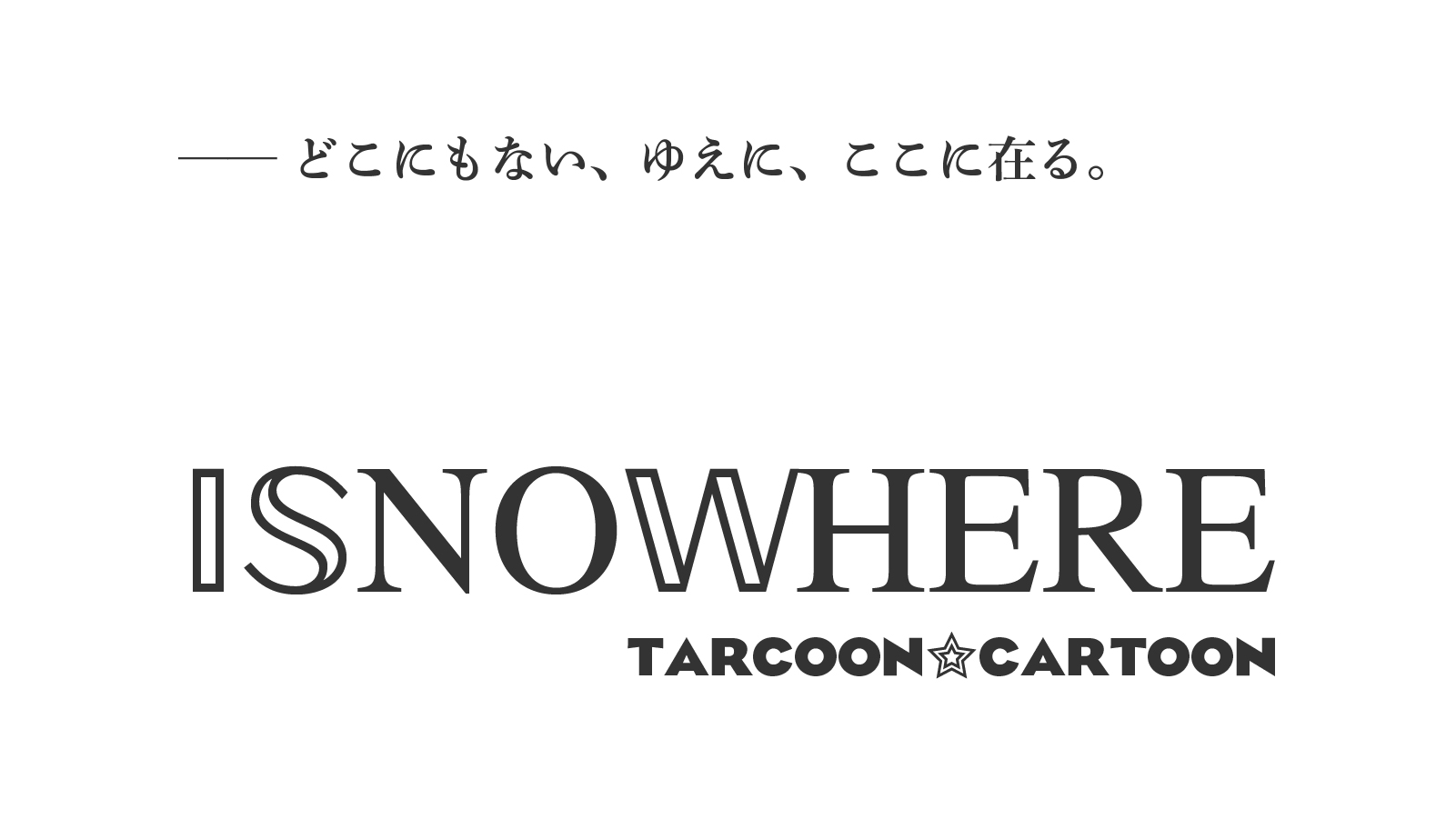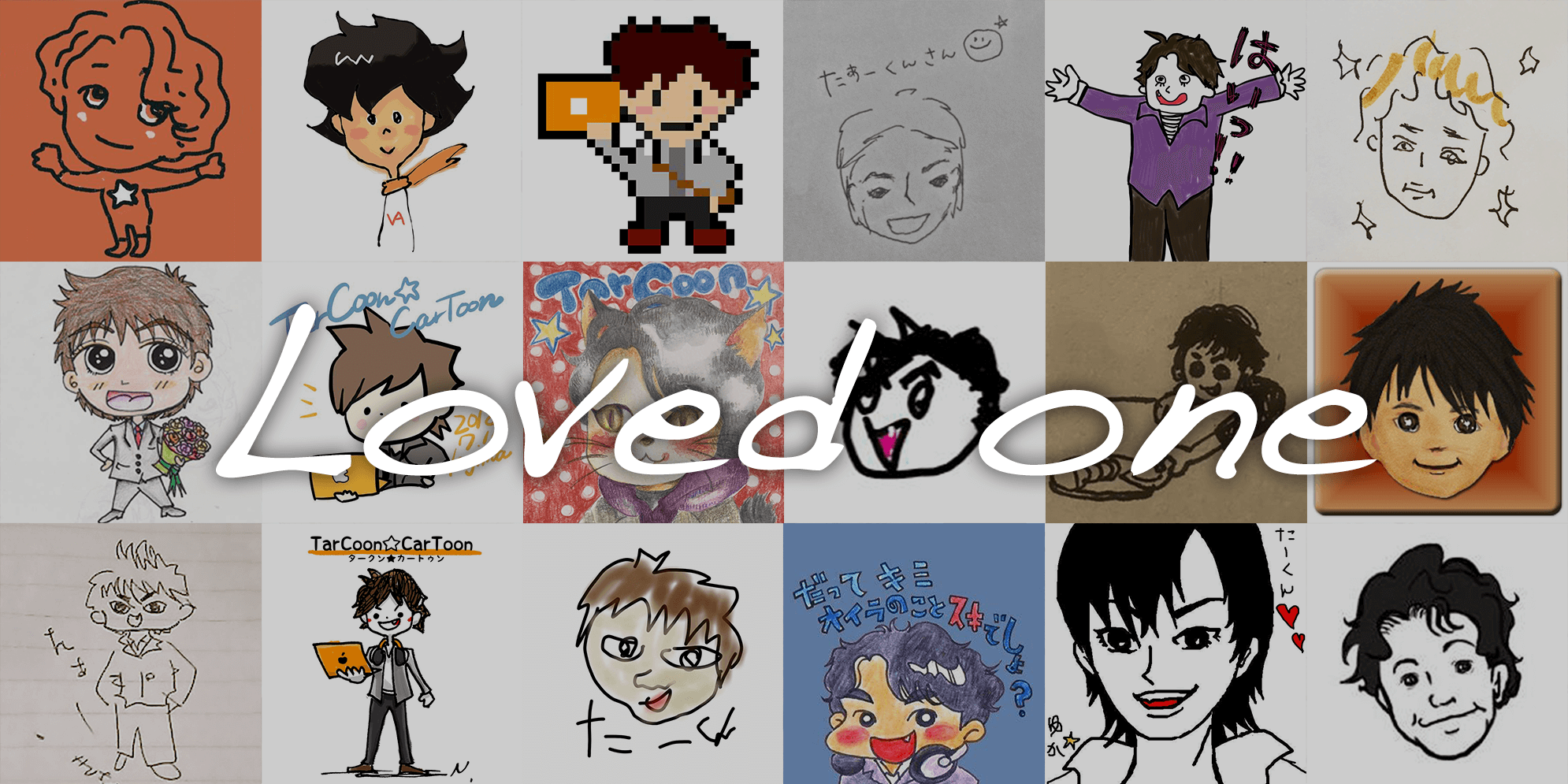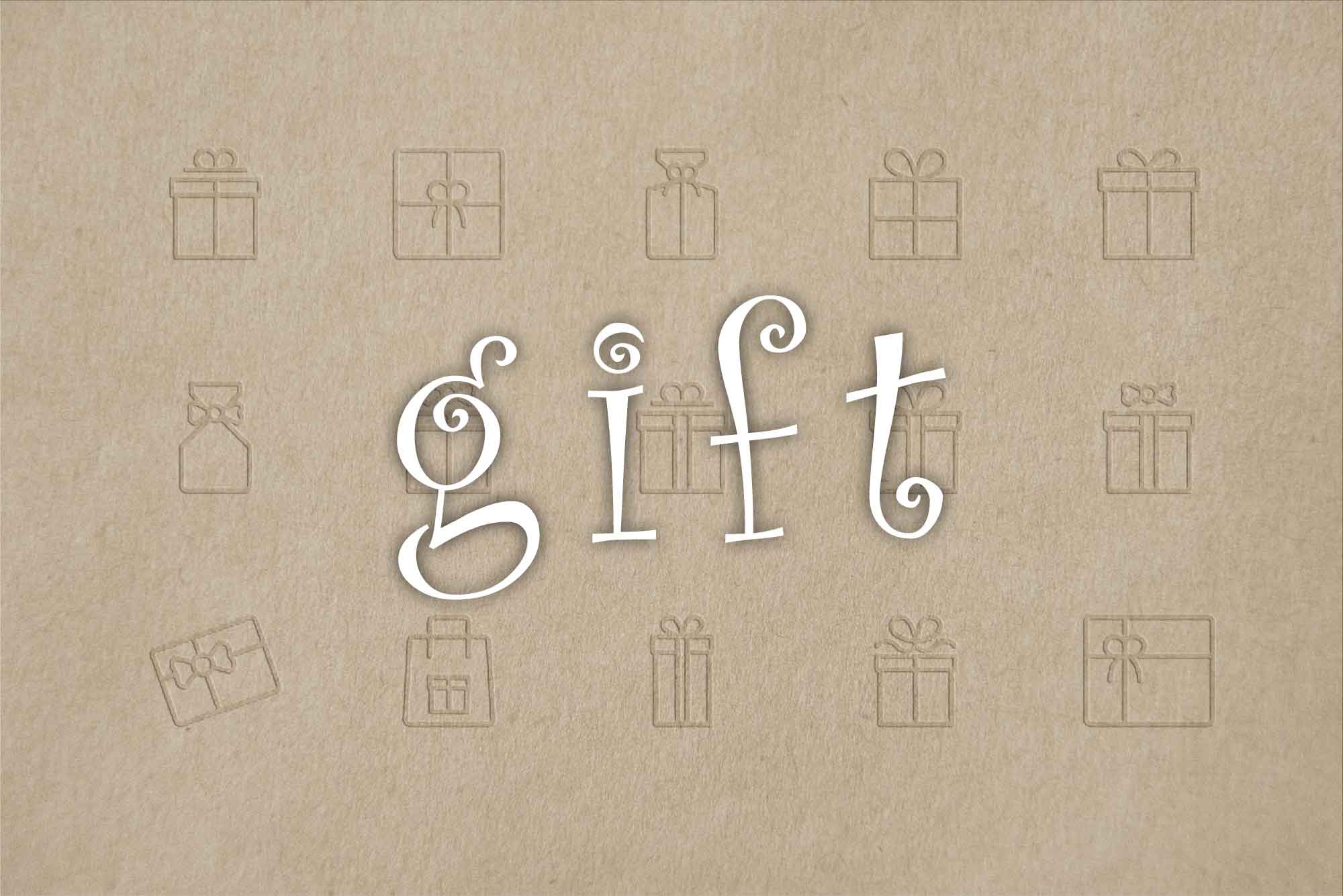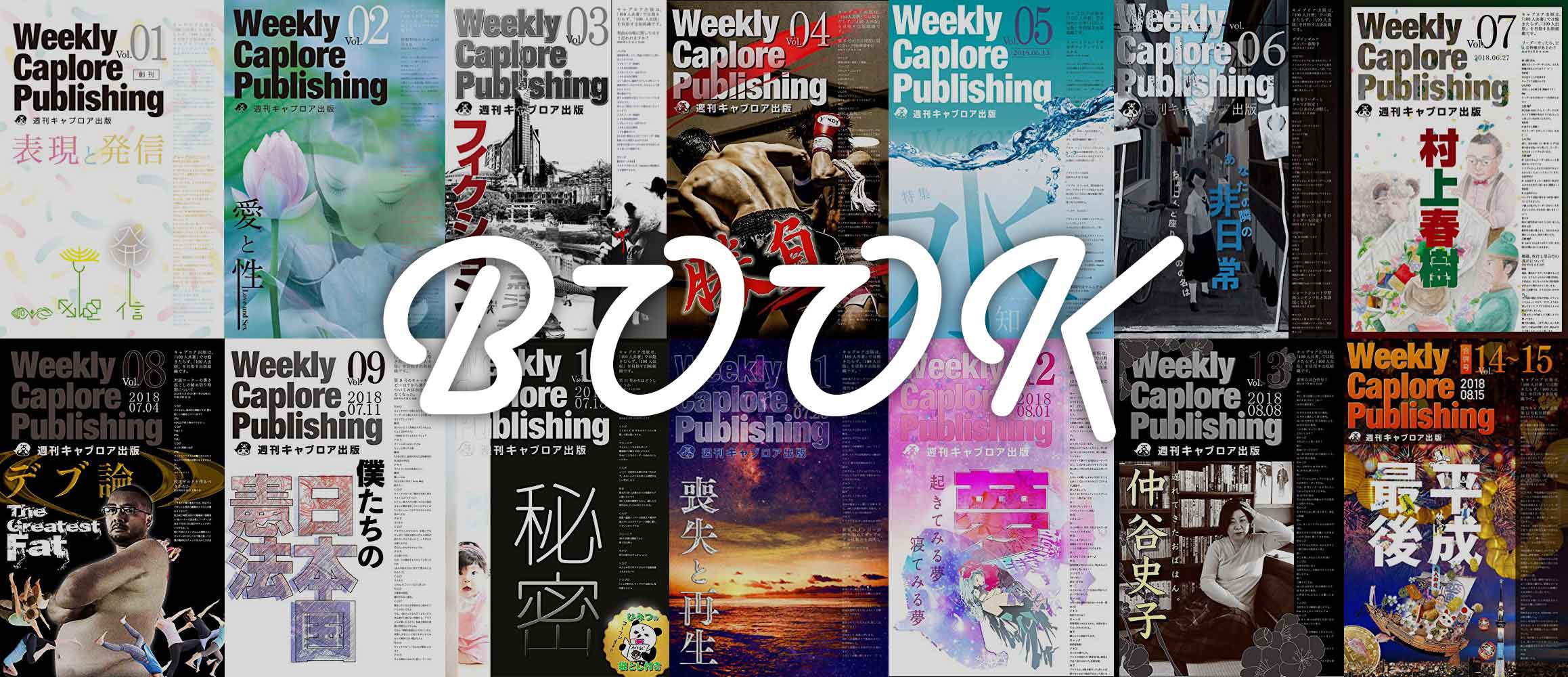私たちが日々SNSで目にする言葉は、瞬時に生まれ、拡散され、そして消費されていく。かつて文学とは、時間をかけて紡がれるものだった。しかし、今ではたった数秒で生成され、共有され、無数の反応の波に飲み込まれる。こうした環境の中で、「文学としての言葉」はどこへ向かうのか? そして、作家の「個」は、この流れの中でどこまで保たれるのか?
本記事では、SNSが文学の主要な流通経路となった時代における「SNS新文学」というテーマを掘り下げる。AIによって文章が生成されることが当たり前になり、誰もが瞬時にテキストを生み出せる今、作家の「個」とは何か? 言葉はもはや「誰のものでもない情報」として漂流し、消費されるばかりなのか? それとも、変化し続ける環境の中で、新たな表現の可能性を見出すことができるのか?
AIが生み出す言葉の中で、「作家の選択」はどこに残るのか? そして、SNSという無数の声が響き合う場において、文学はどのような役割を果たし得るのか? 速さと流動性の時代において、「個」としての言葉を紡ぐことは可能なのか?
本記事では、「AI×文学」「SNS時代の作家性」「流動する言葉の価値」 を軸に、現代における文学の可能性を探る。
*本記事は、古田更一氏とはじらい氏による雑誌『UROBOROS』への寄稿した文章の加筆修正版となります。本文は2025年4月7日(月)出版後に公開予定です。お楽しみに!
*本記事は、雑誌『UROBOROS: 新文学』内で、「AI時代の文学のあり方。消費される言葉と「個」の行方 ──テーマ『新文学』UROBOROSに寄稿して」というタイトルで寄稿しています。こちらの本もお読みください。
はじめに──文学を信じるとは「個」を信じることか?
オイラは、文学を信じるとは、人間の「個」を信じることだと考えている。文学とは、単なる言葉の羅列ではなく、書き手の意志や経験、価値観が染み込んだ「個」の表出である。そして、読者はそこに触れ、時に共感し、時に異なる価値観に戸惑いながらも、書き手の「個」と対峙することで、新たな思考を得る。だからこそ、文学は個人の営みであり、「個」の力が込められた言葉こそが、読者の心を動かしてきた。
しかし、今、その前提が揺らいでいる。AIが文章を生成し、SNSが文学の主要な流通経路となった現代において、言葉は瞬間的に生まれ、消費され、そして忘れ去られる。長く書き手の「個」と結びついていた文学という営みは、情報の奔流の中で薄まり、匿名的で断片的なものへと変質しつつあるのではないか。
例えば、SNS上で日々無数に投稿される短文は、かつての文学の形式に似ている。短歌や俳句のように凝縮された表現が好まれ、140文字や280文字の枠の中で、人々は思いの丈を綴る。しかし、そこに「個」はどこまで宿るのか? 書き手の思想や感情が介在しているかに見えて、実際はアルゴリズムによって最適化され、拡散されやすい言葉が選ばれた結果ではないのか? あるいは、AIによる文章生成が進化し、人間と区別がつかないレベルになった時、それは「文学」として成立するのか?
文学を信じることは、書き手の「個」を信じることだという考えが揺らぐのは、まさにこの点にある。書き手の意図や個性が消え、ただ受容されやすい表現が量産される世界において、オイラたちは何を「文学」として認識するのか。AIが書いたものを文学と呼べるのか? そして、SNS文学の消費構造の中で、作家の「個」はどのように位置付けられるのか?
この問いに向き合うことは、AI時代の文学のあり方を考える上で避けられない。そして、それは単なる技術の問題ではなく、「個」という概念をどのように定義し、それを保持するかという本質的な問題にも関わってくる。文学とは、人間の営みとして成り立つものなのか? それとも、言葉がそこにある限り、誰が紡ごうとも文学たりえるのか? オイラは、その境界線を見極めるために、AI時代の文学について考えていきたい。
変わり続ける主題──文藝誌 UROBOROS の試み
今回掲載させていただいている文藝誌『UROBOROS』は、当初「キャンセルカルチャー」というテーマで寄稿文を募集していた。しかし、募集の途中で「エコーチェンバー」へと変更され、さらに最終的には「SNS新文学」へと移行した。この二度のテーマ変更は、寄稿を考えていたオイラにとって少なからず驚きだった。
オイラ自身、寄稿する際にはその時々のテーマに沿った内容を書くべきだと考えていたし、選んだテーマに対して深く掘り下げて書こうとする以上、途中で主題が変わるのは正直、戸惑いを感じる部分もあった。せっかく考えたアイデアが使えなくなることには迷いもあったし、テーマが定まらないまま書き進めることに対して、「本当にこれでいいのか?」という疑問も浮かんだ。実際、オイラはテーマに合わない内容は掲載したくないと思ったし、どのような形で書くべきかを再考することを余儀なくされた。
もしかすると、オイラと同じように戸惑った人がほかにもいたかもしれない。何度も書き直すことにうんざりし、「もうやってられない」と感じた人がいてもおかしくない。だが、それでも『UROBOROS』はこの変化を選び、結果として三つの異なる主題を経て最終的な形に至った。その流れを振り返ると、そこには単なる迷走ではなく、意図的な試みがあったのではないかと考えた。
オイラはテーマ変更のたびに、それに応じた原稿を作成し、すでに執筆・入稿していた。最初のテーマ「キャンセルカルチャー」に対しては、『キャンセルする側とされる側、その境界に立つ者とは?』という原稿を執筆した。次に、「エコーチェンバー」のテーマに合わせて、『共鳴領域にズレを仕掛ける。対話を閉ざさず広げる視点』という原稿を仕上げた。しかし、最終的にテーマは「SNS新文学」に変更されることになった。
これらの原稿は、当初の変更によって『UROBOROS』では発表されることがなかったが、今回、執筆した内容の意義を鑑み、改めて公開することといたしました。ぜひご一読いただけますと幸いです。
- 『キャンセルする側とされる側、その境界に立つ者とは?』
https://tarcoon.me/tarcoon-cancel/ - 『共鳴領域にズレを仕掛ける。対話を閉ざさず広げる視点』
https://tarcoon.me/tarcoon-echochamber/
こうして振り返ると、テーマの変更が単なる「思いつき」ではないことは、変更されたテーマの関係性を見ればわかる。「キャンセルカルチャー」「エコーチェンバー」「SNS新文学」。これらは、いずれも現代の言葉の流通や消費に関わる問題系であり、決して無関係なものではない。むしろ、互いに強く結びついている。
「キャンセルカルチャー」とは、特定の言葉や振る舞いが糾弾され、排除される現象だ。一方で、「エコーチェンバー」とは、特定の価値観を持つ集団内で同じような言葉が反響し続け、外部の視点が排除される現象を指す。これらは一見、正反対の現象のように見えるが、本質的には共通した構造を持つ。「特定の言葉が強化され、別の言葉が排除される」という意味では、どちらも「言葉の選別と流通の偏り」を生み出す。そして、こうした偏りが生じる場として最も顕著なのが、SNSだ。つまり、最終的なテーマ「SNS新文学」は、前の二つのテーマの延長線上にあるとも言える。
こうして見てみると、『UROBOROS』がたどったテーマの変遷は、現代の言葉のあり方を反映しているように思える。SNS上で流通する言葉は、極めて速いスピードで消費され、次々と新たな話題へと移り変わっていく。この流動性の中で、文学はどのように成立しうるのか? もし『UROBOROS』が「時代に即した文学のあり方」を探求する場だとするならば、主題の流動性そのものが、その試みの一部だったのではないか?
文学は、従来「持続するもの」として捉えられてきた。古典文学は何十年、何百年も読み継がれ、作家は一つの主題やスタイルを生涯かけて磨き上げる。しかし、現代の言葉の流通速度を考えたとき、「持続する文学」という発想自体が、もはや時代と噛み合わなくなっているのではないか?
もしそうだとすれば、『UROBOROS』が試みているのは、「言葉がすぐに消費される時代において、文学はどうあるべきか?」という問いの実践なのではないか。固定されたテーマのもとに作品を集めるのではなく、「変化し続けること」そのものをコンセプトとすることで、文学の新しい形を模索しようとしているのではないか?
この視点に立つと、オイラが感じた混乱や、寄稿者たちの戸惑いすらも、『UROBOROS』の表現の一部だったと言える。もし文学の場が「変化し続けること」そのものを実践しているのならば、それは文学の新しい形を提示しているのではないか?
AI時代の文学における「個」の役割──どこまでを区切るべきか?
この「変化し続ける文学の場」という問題意識は、AI時代の文学における「個」の問題とも密接に関わっている。言葉の流動性がかつてないほど加速する今、文学とは何か、作家の「個」とは何かという問いは、単なる技術論を超えて、表現の根本に関わる問題へと発展している。
AIが文章を書くことは、もはや特別なことではない。小説や詩、評論ですらAIが生成し、それなりにまとまりのある文章を作り出すことができる時代に、文学はどのようにして「人間の表現」としての価値を保持するのか。それは、単に「AIが書いた」か「人間が書いた」かという単純な二元論で語ることのできる問題ではない。むしろ、重要なのは、「AIが書く」こと自体ではなく、「AIを使って何を表現するのか?」という点にある。
すでにAIを用いた執筆活動は、多くの作家によって実践されている。『UROBOROS』の編集を務める古田更一氏もその一人だ。彼はAI(Grok)を積極的に活用し、執筆を行っており、さらにその実践を体系化し**『Grok哲学』**という本を出版している。つまり、AIを用いた執筆は、もはや未来の話ではなく、すでに現実として行われているのだ。
オイラは、AIを作家の「個」を奪うものではなく、むしろ「個を引き出す」ツールとして捉えている。AIは無数の可能性を提示し、その中から作家が選び、編集し、意味を与えることで「個」が成立する。たとえば、AIによって生成されたフレーズやアイデアを作家が取捨選択し、そこに独自の文脈や解釈を与えることで、「自分の表現」として確立することができる。これは、画家が既存の色彩や形態を用いながらも、それを独自に組み合わせ、新たな作品を生み出すことと似ている。
しかし、ここで問題となるのは、「どの範囲で『個』を区切るべきか?」という点だ。AIを用いた創作が一般化し、誰もが簡単にテキストを生み出せる環境では、「この文章は誰のものか?」という問いが曖昧になりやすい。AIが補助した文章に、どれだけの「作家の意図」が反映されているのか。その境界線があいまいになることで、「個」としての作家性が希薄化してしまう可能性がある。
特に、もし「個」の単位をコミュニティ単位で定めてしまうと、作品はエコーチェンバー化しやすくなる。たとえば、特定のグループの中でのみ通用する価値観や文体が強化され、外部の視点が排除されることで、文学としての広がりを失ってしまう危険がある。SNS上の文章は、しばしばその傾向を持つ。フォロワーの多い作家やインフルエンサーの言葉が、共感する層の間で反響し、拡散される一方で、異なる視点を持つ人々には届かない。これは、文学が「読者を限定し、特定の文化圏の中でのみ流通する」状況を生み出すことにつながる。
こうしたリスクを回避するためには、「個」としての作家性を明確にし、単なる「コミュニティ内の言葉」ではなく、「自分の言葉」として表現することが必要になる。AIを活用することで、むしろ作家の個性を強化することも可能だ。たとえば、AIに対して「このテーマで文章を作成してほしい」と指示を出す際、その指示内容こそが作家の視点や価値観を反映することになる。また、生成された文章のどこを取捨選択し、どのように編集するかも、作家の「個」を示す重要な要素となる。
この点で、『UROBOROS』の試みは示唆に富んでいる。主題が流動することで言葉の新陳代謝を促し、特定の価値観に固定されることなく、変化し続ける場を提供している。これは、AI時代の文学においても重要な示唆を与える。つまり、文学が単なるコミュニティの自己強化装置にならないためには、AIを活用しながらも、作家としての「個」を明確に打ち出すことが求められる。
では、AI時代における「個」とは、どのようにして保証されるべきなのか? それは、「この人が書いた」とわかるようにすることだけではない。単に著作権や署名の問題ではなく、作品が持つ「書き手の選択の痕跡」を明確にすることが求められる。AIが生み出した文章に作家の意思がどのように反映されているのか? どこに選択があり、どこに編集の痕跡があるのか? それが見える形で提示されることこそが、AI時代の文学における「個」の保証につながるのではないか。
つまり、「個」を区切るということは、「この人の手による表現である」という証明をどこまで明確にできるかという問いでもある。そして、それは単に技術的な証明ではなく、作品の内容や編集のプロセスにおいて、作家自身の選択がどれほど介在しているかを示すことによって可能になる。
AIが書くことが当たり前になった時代において、文学における「個」は、ただ「自分の言葉を持つ」ことではなく、「言葉を選び取る」という行為そのものによって成立するのではないか? そして、それをどこまで明示できるかが、AI時代の文学の本質的な課題となるのではないか?
まとめ──AI時代の文学を「個」として成立させるために
AIが書き、SNSで消費される時代において、文学はどのようにして「個」としての価値を保持することができるのか? これは、単に「人間が書いたものとAIが書いたものを区別できるか」という表層的な問題ではない。むしろ、AIの関与が当たり前となった今、「作家の役割とは何か?」という、文学の根幹に関わる問いに直面している。
オイラの結論は、「AIが作る」ことそのものが問題なのではなく、「どの範囲で『個』を確保するか?」が問題なのだということだ。つまり、AIの有無にかかわらず、最も重要なのは、作家の意図や選択がどれだけテキストに反映されているか という点である。
すでに、『UROBOROS』の編集者である古田更一氏は、AI(Grok)を活用して執筆を行い、『Grok哲学』という本を出版している。彼の実践は、AI時代における「作家の関与とは何か?」を問い直す一つの試みと言える。AIを利用することで、作家が「自分自身の視点を強調し、選び取る行為」に意識的になるならば、それはむしろ「個」を強めることにつながるのではないか。
「作家の選択が反映されたテキスト」とは何か?
AI時代の文学において、「この人が書いた」と言えるためには、どのような条件が必要なのか? それは単なる「署名」や「著作権」の問題ではない。むしろ、作品の内部において、作家がどのように関与したか、どこで選択を行い、何を切り捨て、何を強調したかというプロセスが重要になる。
- AIが生成したテキストをそのまま発表するのではなく、「編集の痕跡」が明確に残されること。
→ 作家がどこで選び、どこで意図を加えたのかが、読者にも伝わる形になっているか。 - 作家の「声」がどのようにAIの出力を超えて表れるのか。
→ 文体やテーマの選択、視点の偏り、繰り返し使われるモチーフなど、作家固有の要素がAIの出力に上書きされているか。 - 「個」の痕跡が可視化される形式を持つこと。
→ 例えば、AIによる提案と作家の編集過程を並べて提示することで、「どこに人間の意思が働いたか」を明示する手法も考えられる。
「個」が喪失していく危機感
だが、問題はそれほど単純ではない。「AIをどう使うか?」という問いの背後には、「そもそも人間自身の『個』は保持されているのか?」という、より根源的な問題が潜んでいる。
AIは確かに作家の可能性を広げるツールになり得る。しかし、一方で、最後の選択を下し、編集を施すことができる主体としての「人間」が、次第にその力を失っていっているのではないか という不安も拭えない。
SNSの普及によって、言葉は瞬時に生まれ、拡散され、消費されていく。かつて、言葉を紡ぐことは、熟考と推敲を要する営みだった。作家は「書くこと」そのものに時間をかけ、自らの思考や経験を言葉に浸透させていた。 しかし、今や多くの言葉は、即座にアウトプットされ、即座に流れていく。タイムライン上の投稿は、AIによって自動生成されたニュースと並列に並び、あるいは短縮され、加工され、最適化された形で表示される。
言葉は「考えを深めるための手段」ではなく、「素早く消費するための情報」へと変わりつつある。そうした流れの中で、作家が「言葉に自分の意図を埋め込むことができなくなっている」のではないか? AIの進化によって、我々は「効率的に」文章を生成し、「より適切な」表現を選ぶことができるようになった。だが、その結果として、人間自身の「個」は希薄になってはいないだろうか?
以前、オイラは『文学を信じることは可能か——「文学への希望」を読んで』という感想文の中で、「文学を信じない文筆家」に絶望する という言葉について考えたことがある。
「文学が、そして文筆家が、文学を信じていないように見えること。そのことへの絶望。かつては文学を信じていたかどうかはさておき、少なくとも、今はもう信じられないのではないかという感覚。そして、それが単に文学の問題というより、『人間の個の希薄化』とも関係しているのではないか、という視点。」
- 文学を信じること、個を失うこと ──「文学への希望」を読んで
https://tarcoon.me/literature-and-hope/
AIが生み出す言葉に、作家は何を付け加えることができるのか? かつて、文学は「言葉を通して個を表現するもの」だった。しかし今や、言葉の流通速度が上がり、AIが言葉を代替できるようになったことで、「個」として表現することの難易度が高まっている。もしかすると、文学の未来は、「個の喪失」という問題と切り離せないものになるのかもしれない。
「文学を信じること」とは何か?
文学の危機とは、単に「AIが文章を書くこと」にあるのではない。それはむしろ、「人間が、自分自身の言葉を信じられなくなっていること」 にあるのではないか?
かつて文学は、「個を形成する場」 であった。しかし、今や個の輪郭は曖昧になり、言葉が瞬時に拡散し、消費される中で、「考え、選び取り、表現する時間」そのものが奪われつつある。文学を信じるとは、「文学を信じることができる世界をつくる」ことに他ならない。
もし文学が、AIの時代においても生き延びるとすれば、それは単なる「効率的なテキスト生成」ではなく、「人間がどこまで個を持ち続けられるか?」という問いに向き合うことによってではないか? ならば、文学を信じるとは、「個の喪失に抗い、自らの言葉を生み出そうとする意志を持つこと」 なのかもしれない。
謝辞
このたび、文藝誌『UROBOROS』に寄稿する機会を賜りましたことを、心より感謝申し上げます。まず、本誌の編集を務める古田更一氏およびはじらい氏に、深い敬意と感謝の意を表します。お二方のご尽力により、本誌が言葉と表現の可能性を探究する場として存在していること、そして今回このようなテーマのもと執筆する機会をいただけたことに、改めて感謝申し上げます。
本稿において論じたように、AI時代における文学の在り方や、「個」という概念の行方について考察することは、決して単純な課題ではありませんでした。しかし、『UROBOROS』が取り上げた主題の変遷を経験し、その変化の中で思索を深めることができたからこそ、オイラはここまで言葉の消費構造や、文学における「個」とは何かについて真剣に向き合うことができました。もし本誌が、ひとつの固定されたテーマのもとに作品を募集していたならば、ここまで思考を広げることはなかったかもしれません。
また、本誌の編集者である古田更一氏が、AI(Grok)を積極的に活用し、執筆を行っていること、そしてその試みを通じて『Grok哲学』という著作を発表されていることにも、大きな示唆を得ました。AIが文章を生成する時代において、作家の「個」をいかに確保するかという問いは、まさに文学の未来を考える上で避けて通れないものです。その問いに対し、本誌を通じて思索を深める機会を得たことは、オイラにとって大変貴重な経験となりました。
さらに、はじらい氏をはじめ、本誌の運営に関わる皆様のご尽力により、このような場が提供されていることにも、改めて感謝の意を表したいと思います。『UROBOROS』が探究する「現代における文学の可能性」は、単なる評論や創作の場にとどまらず、言葉そのものの在り方や、社会の変化に伴う表現の意味を問い直す実験の場でもあると感じています。そのような貴重な場に参加できたことを、大変光栄に思います。
また、堀川夜鳥氏にも、この場を借りて感謝を申し上げます。良き友人として、智を分かち合い、互いに思索を深める時間をともにできることに、心からの喜びを感じています。 堀川氏の真摯な姿勢、そしてやりたいことに向き合いながら前進していくその姿には、大きな感動を覚えています。こうして言葉を交わし、思索を深め合うことができる関係を持てることに、改めて感謝いたします。また、お茶でもしながらゆっくり語り合いましょう。
本稿の執筆を通じて、オイラ自身が抱えていた文学への問いを深めることができました。それは、AI時代においても「文学を信じることは可能か?」という根源的な問いに向き合うことであり、同時に、「人間の個とは何か?」という哲学的な問題とも結びついています。『UROBOROS』という場がなければ、ここまで自分の考えを掘り下げることはできなかったでしょう。
この場を借りて、あらためて感謝申し上げます。今回の寄稿を機に得た思索の糧を胸に、今後も文学と表現の可能性を探求し続けていきたいと思います。
最後になりましたが、文藝誌『UROBOROS』の発展と、関係者の皆様のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
(この記事は2025年3月10日に執筆したものです。)