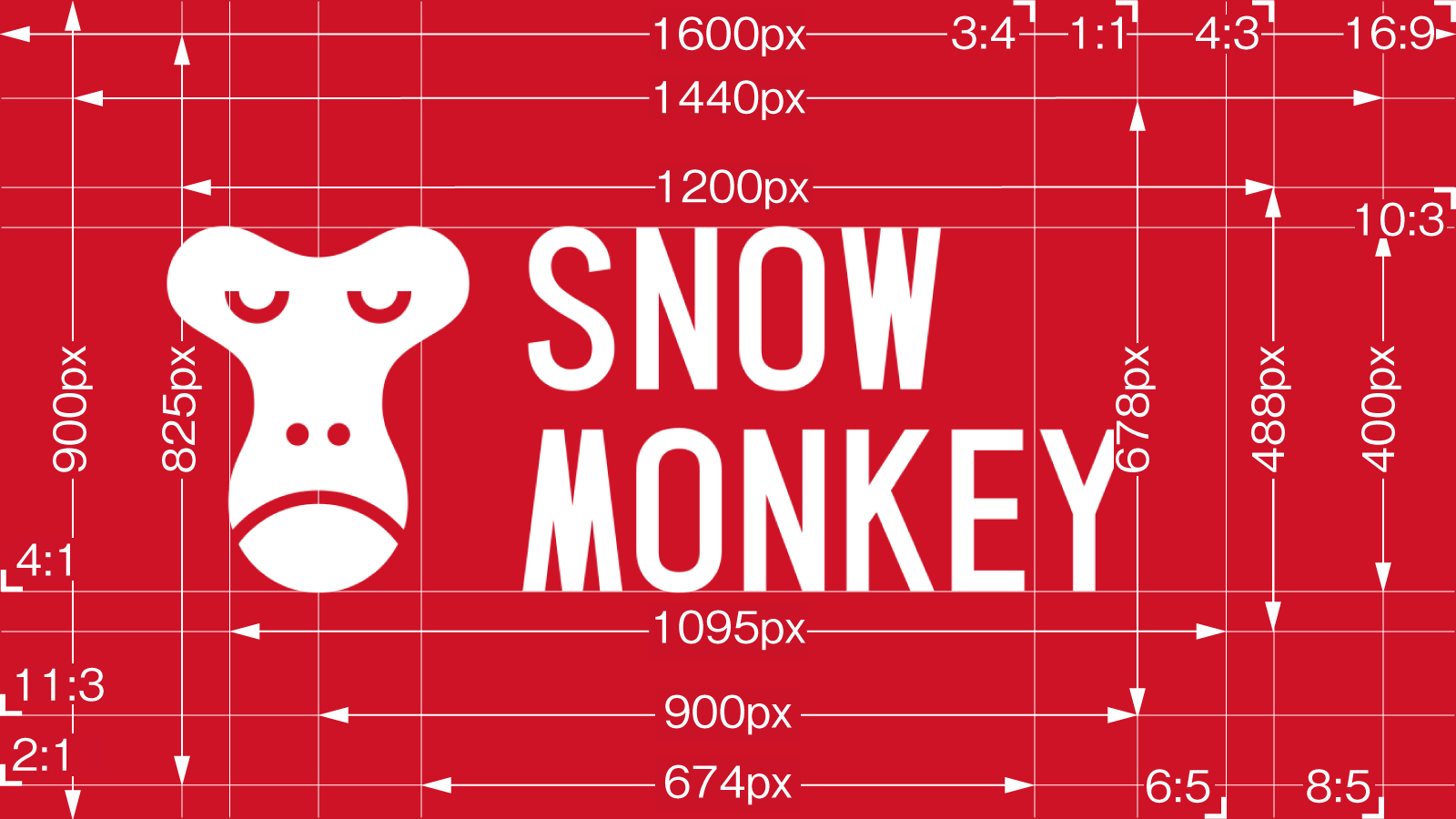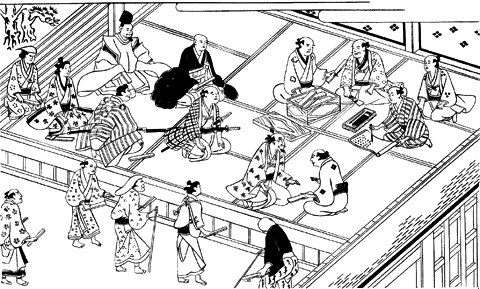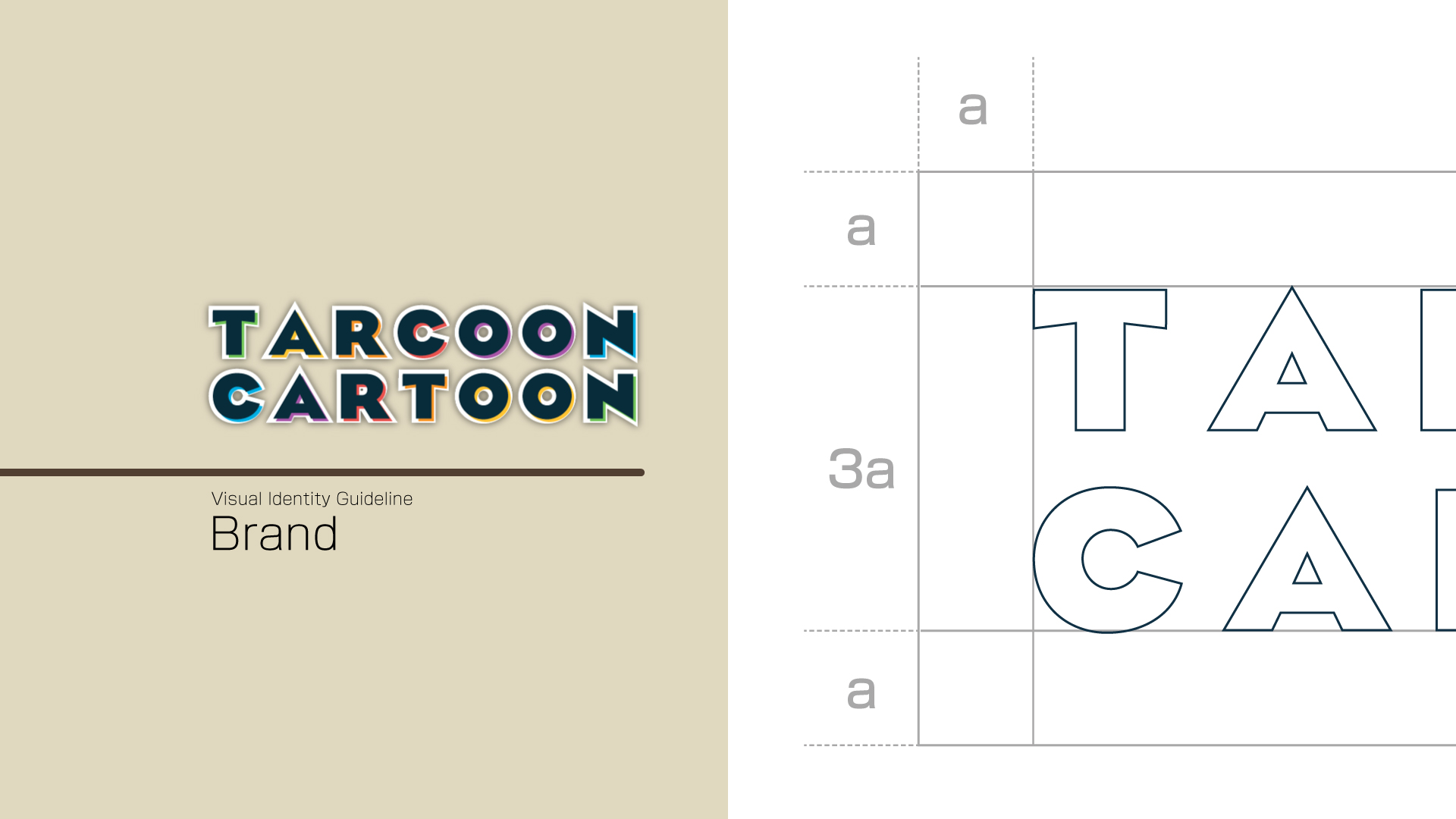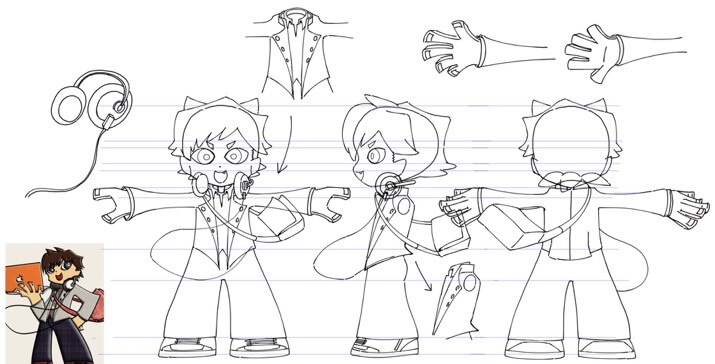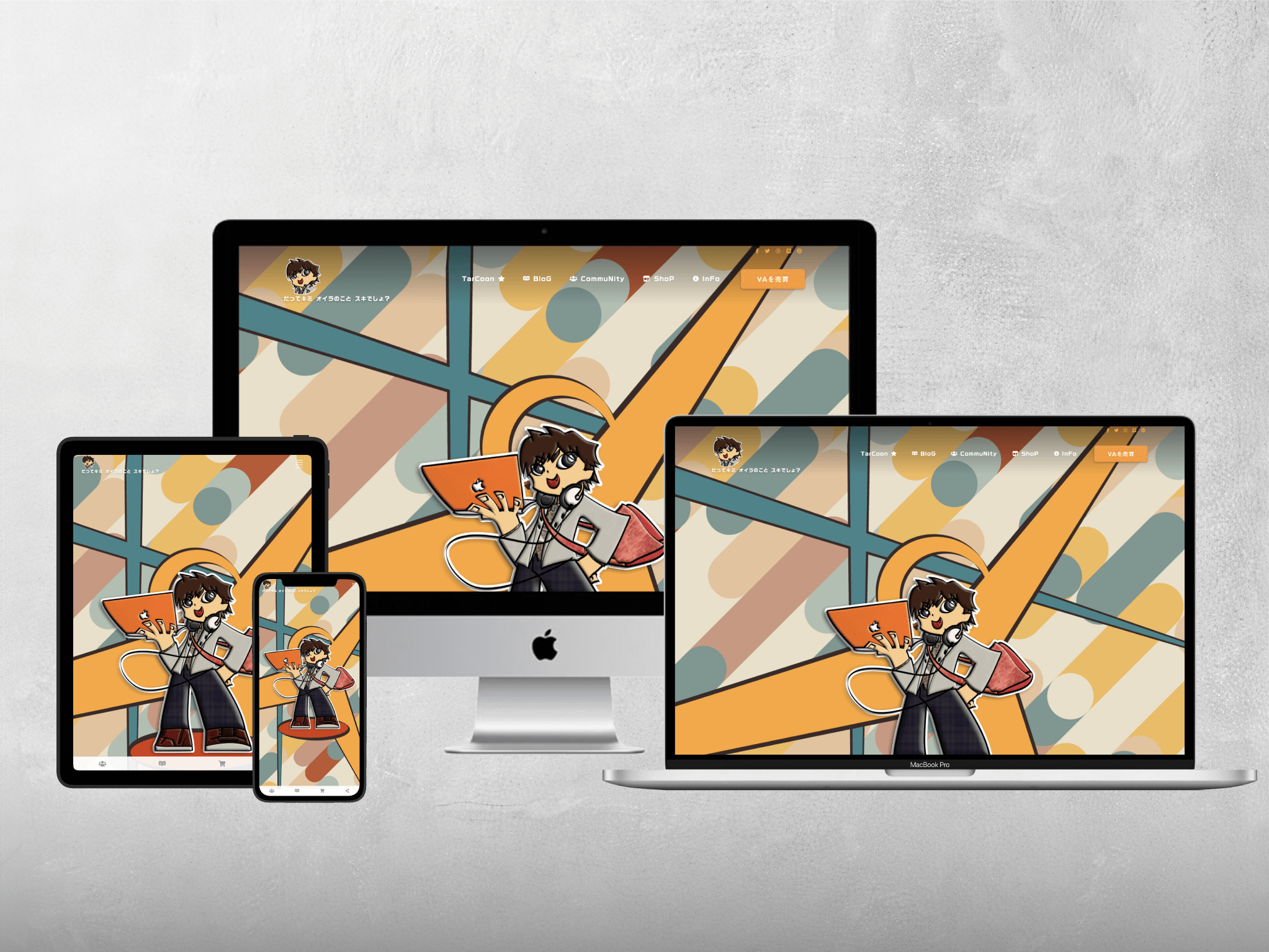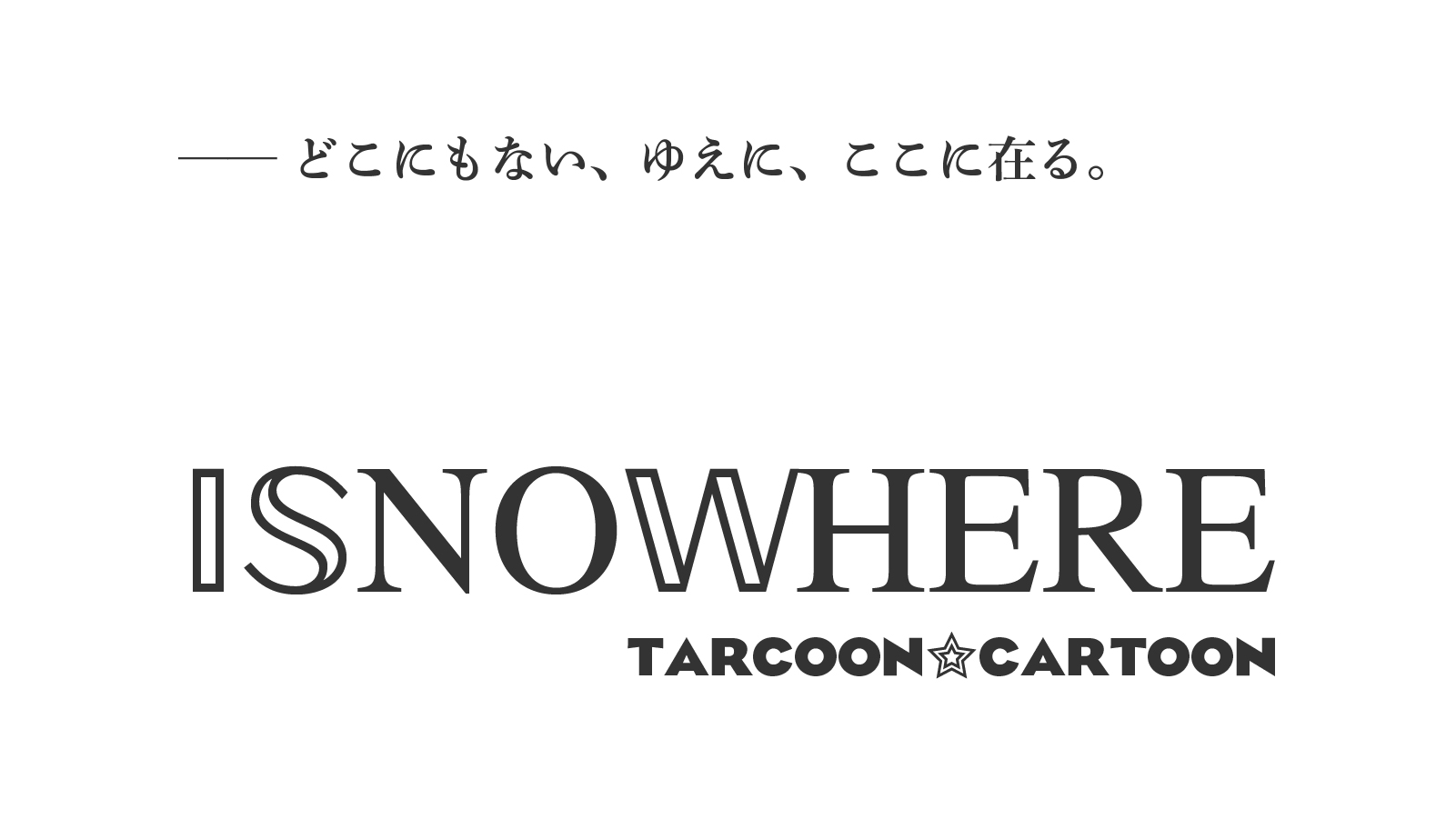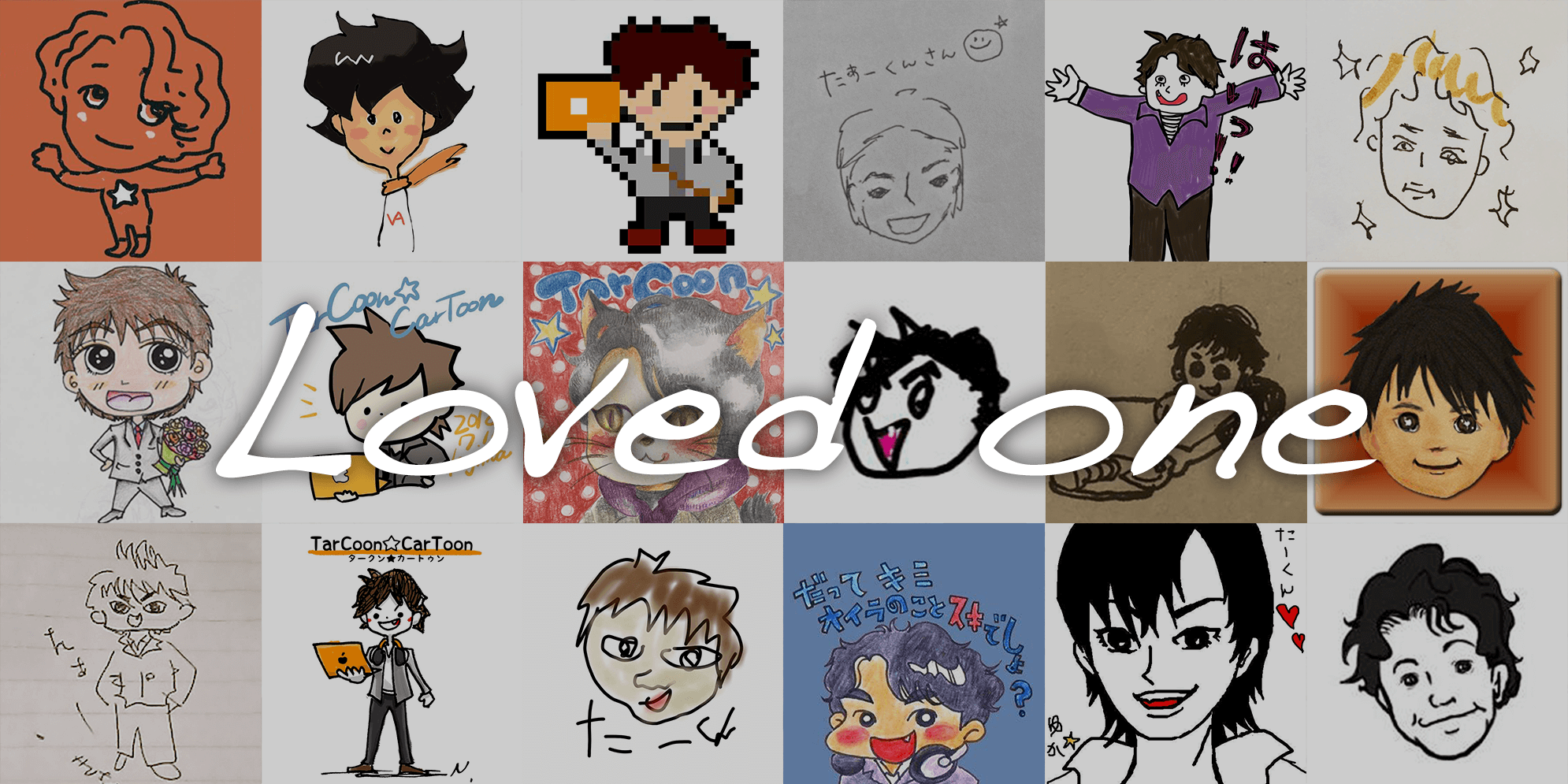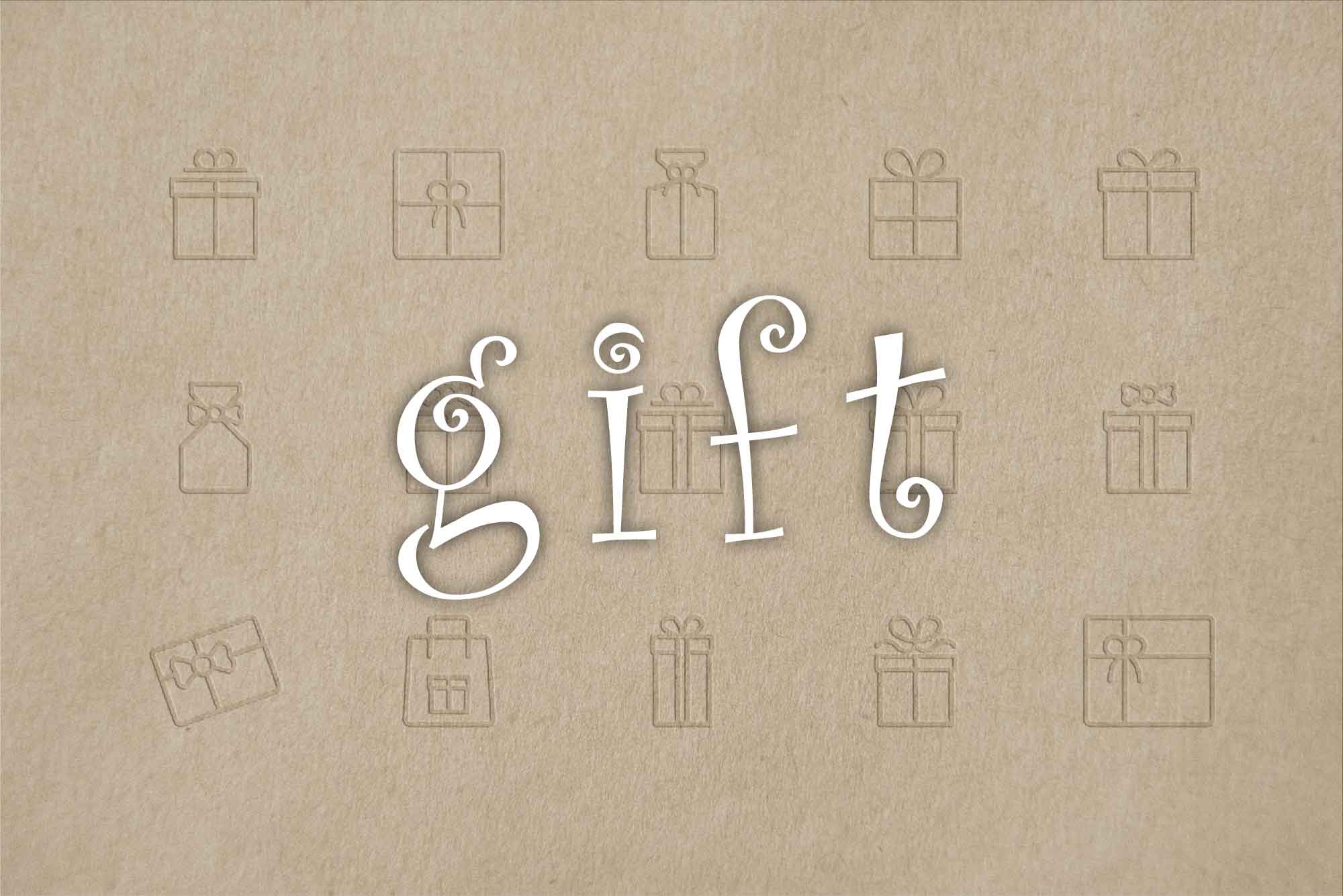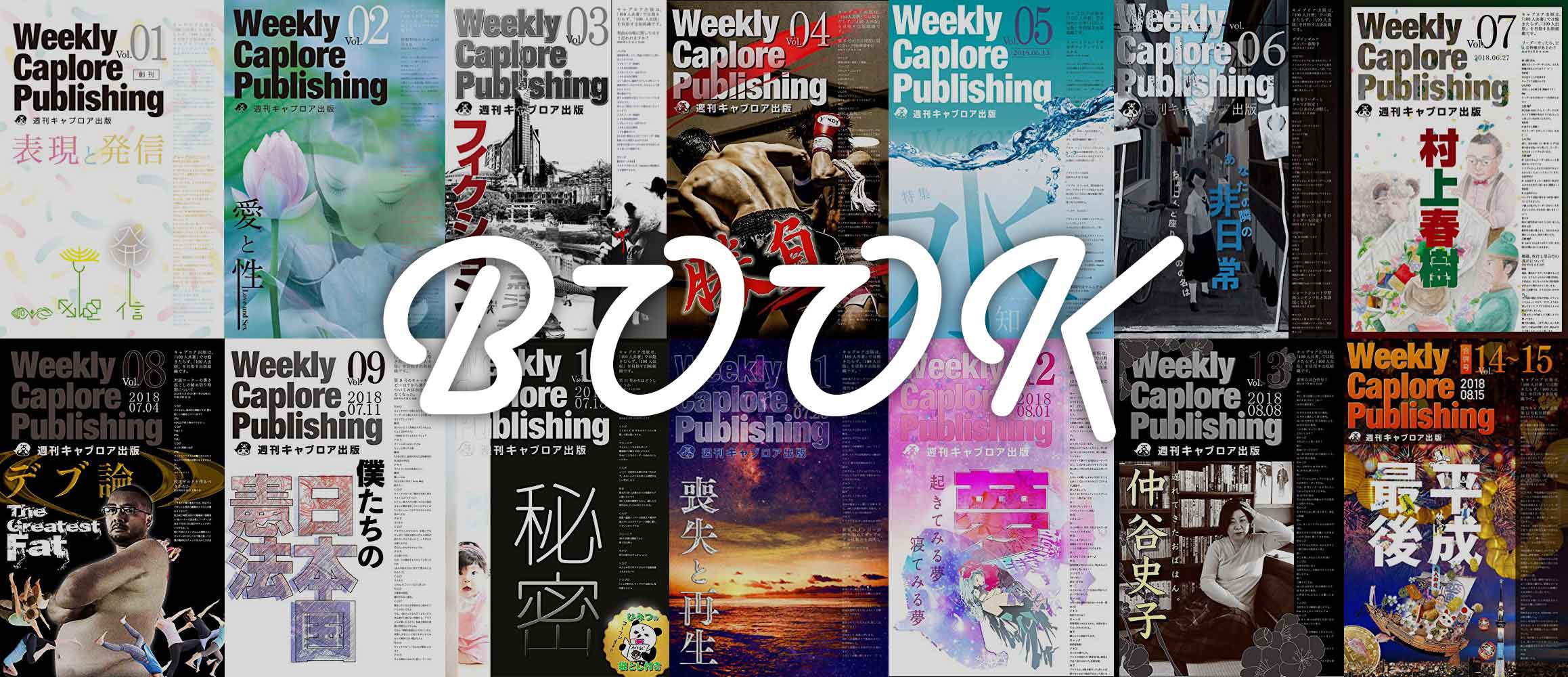友人に読んで欲しいと渡された文章は「勉強のしかた」を語っているようでいて、その奥には「どう生きるか」という問いが静かに息づいていました。友人が塾の始まりに差し出した一篇を読みながら、TarCoon☆CarToonとしても深く心を動かされ、感想を綴りました。よろしければご覧ください。
この記事は、友人からいただいた文章いしだ塾資料「国語、英語、数学の勉強について」の応答記事です。塾に入る生徒が読むために書かれた文章だと思うので読むことはできません。ご了承ください。
だんだん、わかってくる。「学ぶ」ということのはじまりに寄せて
名古屋に遊びに行った時のことだ。
名古屋が世界に誇る奇食の最高峰、喫茶マウンテンで「甘口抹茶小倉スパゲッティ」を前にして、オイラは若干の動揺と共にフォークを構えていた。見た目は完全にスイーツなのに、湯気が立っていて、麺はスパゲッティ。脳が混乱し始めたそのタイミングで、友人が言った。「私、塾を始めるじゃないですか……最初の授業で、これ配ろうと思ってるんですよね」そう言ってスマホの画面を差し出してきた。表示されていたのは、国語・英語・数学について語る一本の長い文章だった。最初は抹茶と小倉の甘さに頭が持っていかれていたオイラも、気づけばそっちの甘味はすっかり忘れて、画面のスクロールを止められずにいた。これは単なる「勉強のしかた」の話じゃない。もっと根っこにある、「なぜ学ぶのか」をまっすぐ見つめる文章だった。
この文章を書いたのは、文藝を愛し、言葉に誠実な友人だ。彼が、これから開くという塾で、生徒たちに最初に読ませたいと語ったとき、オイラはうなずきながら、けれど少しだけ胸の奥が静かに疼いた。なぜなら、それは「成績を上げるため」でも、「効率よく覚えるため」でもない、もっと深く、もっと遠くを見据えた学びのための言葉だからだ。そして同時に、それは、自分自身に向けられた言葉でもある。
文章の中では、国語、英語、数学という三教科が一つずつ取り上げられていく。けれどそれは、教科ごとの細かい勉強法を紹介するというよりも、それぞれの教科がもつ独自の「世界の見方」や「理解の仕方」について語られているのだ。
国語の章では、「話せるからといって、言葉を使いこなせているとは限らない」という指摘から始まる。日本語を話せることと、日本語で“生きる”ことのあいだには、大きな隔たりがある。トラブルの原因は言葉にあり、トラブルを終わらせるのもまた、言葉である――このような直感的で重たい真理が、穏やかな文体で差し出されているのを読んで、オイラは胸の奥が静かに波打つのを感じた。
また、彼が「もの」と「こと」の違いについて語る箇所では、言葉だけではない、世界の成り立ちそのものに触れるような気配がある。言葉に宿る霊性、曖昧で、理屈では捉えきれない「もの」の世界と、はっきりと区切られ、理論化されていく「こと」の世界。そのあいだで人は揺れ、言葉もまた、その揺らぎを内包している。
英語の章では、「ものの見方が違う」という話が展開される。「I’m coming」という表現に代表されるように、英語には、“私”でさえも説明される対象として現れる第三者的な視点がある。一方で日本語では、“私”が前提として語られていく。この違いを通じて、異なる文化に触れることは、単に翻訳の技術を習得することではなく、新しい視点を手に入れることだという理解が示されている。
そして数学の章では、「数学は“情緒”や“数覚”で理解するものだ」という、一般的なイメージとは少し異なる考えが示される。理詰めではなく、感覚で捉える学問。教わるだけではなく、自分の手を動かして、自分の中に“わかる”という感覚が根づくまで向き合うもの。そのような態度こそが、本当の意味で数学を学ぶということなのだと、彼は語っている。
これらすべてに共通しているのは、「だんだん、わかってくる」という、時間と経験に対する静かな信頼だ。何度も読むこと、何度も書くこと、何度も考えること。そのくり返しのなかで、あるときふと訪れる「わかった気がする」瞬間を、大切に抱えながら進んでいくこと。オイラはそれを、どこか音楽のような感覚で読んでいた。すぐに理解することではなく、ゆっくりと共鳴していく学びの旋律。そして、読み終えてからずっと考えていたのは、なぜ彼は、この文章をTarCoon☆CarToonに読んでほしいと思ったのか、ということだった。
オイラは、TarCoon☆CarToonという名前で活動する中で、ずっと「人間をどう再発見できるか」を考えてきた。芸術やユーモアや風刺を通して、あるいは哲学的な問いかけを通して、既に“知っているつもり”の世界を、もう一度見直すようなプロジェクトを続けている。だから彼はきっと、この文章に込めた「知らないことを知るということの大切さ」が、オイラにも響くと信じてくれたのだろう。あるいは、オイラが「わからなさを、わからないままに抱えていること」の価値を伝えようとしていることと、彼の文章が不思議なほど似ていると感じてくれたのかもしれない。彼のこの文章には、慰めがない。でも、見捨てるような冷たさもない。むしろ、「わからないままでいる」ということに、とても誠実で、やさしいまなざしがある。だからこそ、生徒たちにも届くだろうし、オイラのように、問い続ける人間にも響くのだと思う。
この文章を読んで、改めて思った。学び続けるということは、わからなさの中にとどまる勇気を持ちつづけること。答えが出ないまま、問いを抱えていくことを、あえて選ぶということ。そして、だんだんと、わかってくる。その「だんだん」のためにこそ、読む。書く。問い続ける。それがきっと、《人間の再発見》というプロジェクトにおける、最初の一歩でもあるのだ。オイラはこの文章を、忘れないだろう。そして、もしTarCoon☆CarToonが誰かに何かを手渡すことがあるなら、こんなふうに、静かで深い言葉でありたいと思う。だんだん、わかってくる。その希望のために、今この瞬間から、もう一度言葉を拾い集めたいと思った。TarCoon☆CarToon《人間の再発見》のために。
(追伸)
この文章は、文藝を愛するあなたの筆ならではの味わいがあって、本当に楽しかった。だからこそ、伝えたいことはそのままに、もっといろんなレベルの子にも届くような別の形でも読んでみたいなと思った。きっと、どんなかたちでも「だんだん、わかってくる」は育っていくだろうからね。